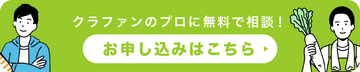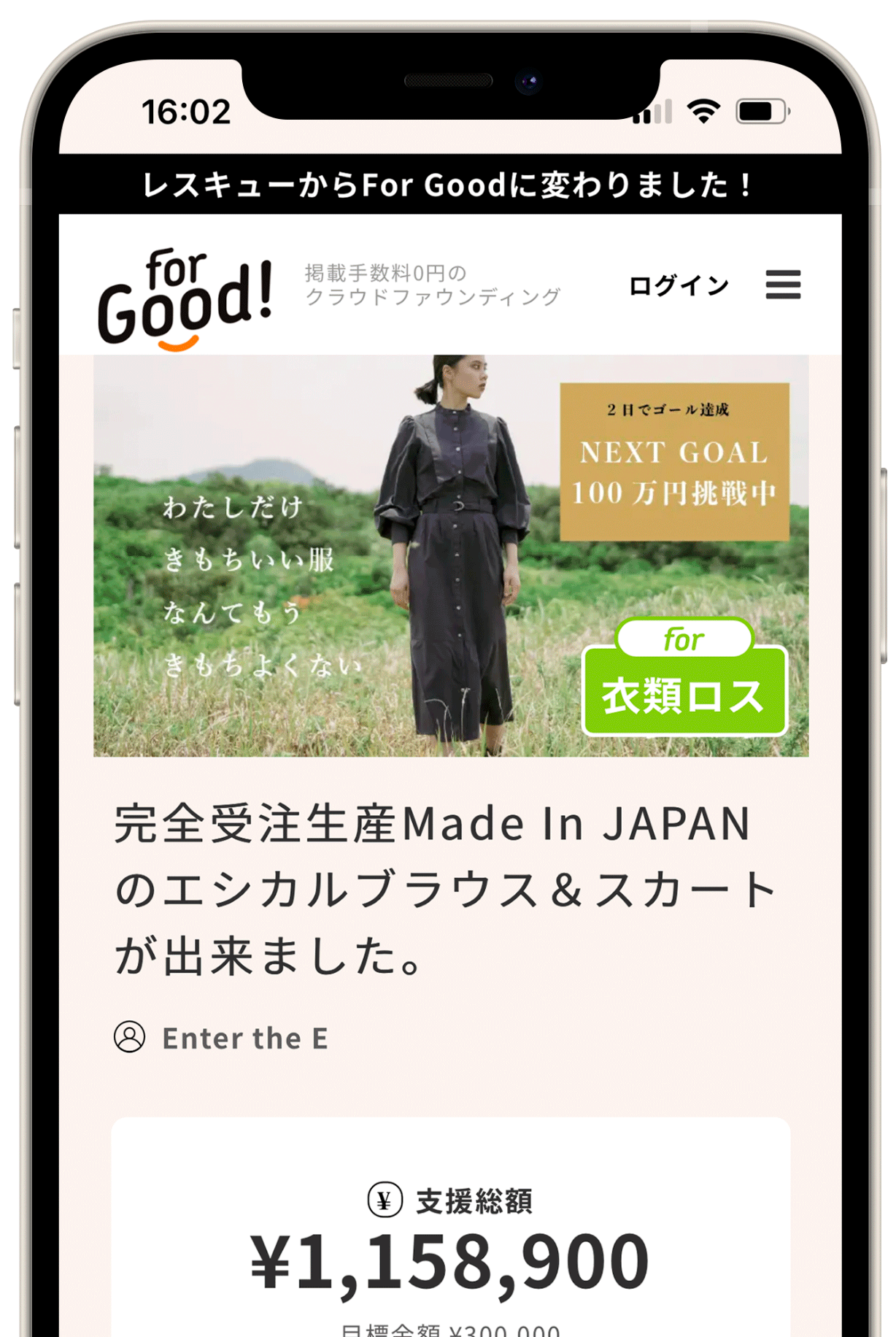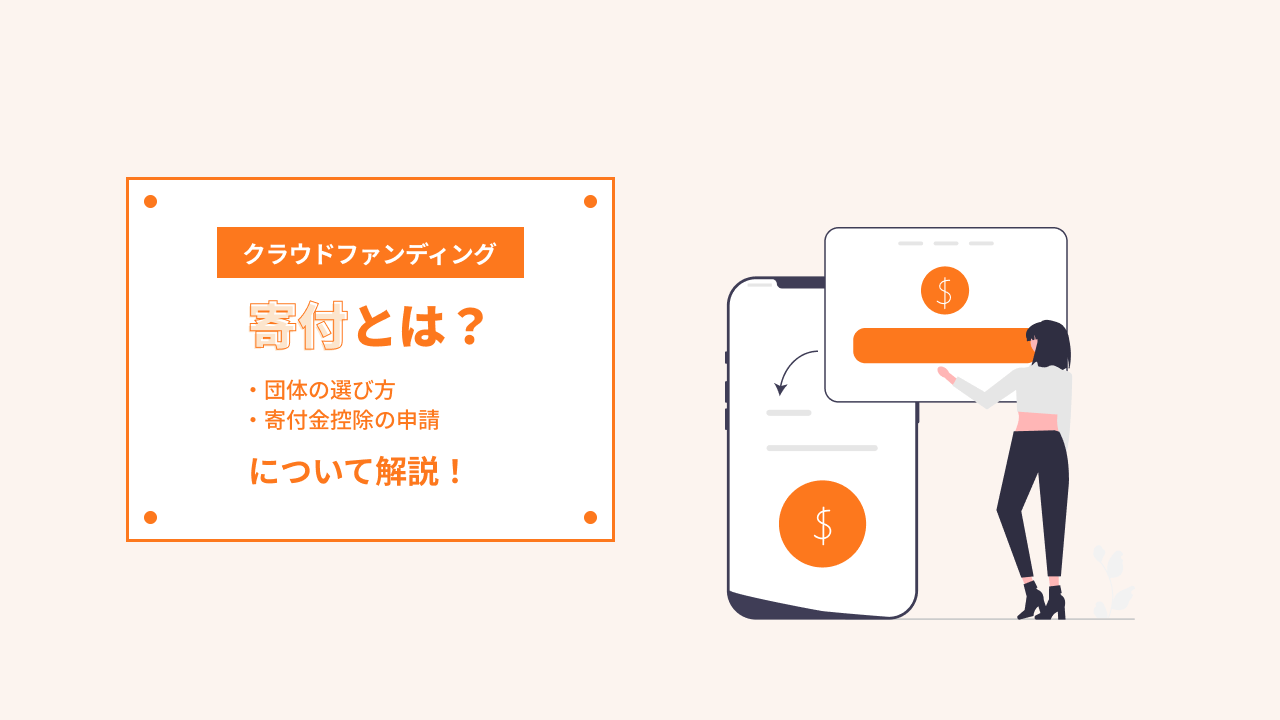
寄付とは?寄付団体の選び方と寄付金控除の申請方法について解説!
「寄付」とは、自らの意志で団体や事業に金品を贈ることです。
「寄付」と似た言葉に「寄贈」と「義援金」がありますが、意味は異なります。
本記事では寄付の意味や特徴、寄付先の団体を選ぶポイント、そして寄附金控除の申請方法について解説します。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
寄付とは募金活動を実施してる団体へ自発的に金銭やモノを贈ること
「寄付」とは、募金活動を実施している事業・団体に金品(金銭や物品)を贈ることです。寄付と間違えやすい言葉やそれぞれの実態など、寄付についての基礎知識を以下で確認しましょう。
間違えやすい「募金」「義援金」「寄贈」「献金」との違い
「寄付」は「募金」や「寄贈」などの言葉と誤用されることがあります。
以下に、誤用が多い単語とその意味を表にまとめました。
|
意味 |
|
|
寄付 |
公共事業や寺社に、金品(金銭と物品)を贈ること |
|
募金 |
金銭を募ること |
|
義援金 |
被災者の手に渡る金銭のこと |
|
寄贈 |
物品を送り与えること |
|
献金 |
目下の者から目上の者へ、金銭を献上すること |
上記の中でも「募金」と「寄贈」は特に似た言葉ですが、寄付とは少しニュアンスが異なっていることが分かります。
また「寄付」「寄附」のように漢字表記が異なる場合がありますが、どちらも「きふ」と読み、同じ意味です。
「寄附」は公的な文書で使われる表記で、日常生活では「寄付」表記が一般的です。
寄付における国際比較
世界の寄付額を比較したとき、現状として日本は順位が低いです。内閣府が令和4年に実施した「市民の社会貢献に関する実態調査」では、日本で寄付が浸透しない理由として以下が挙げられています。
・経済的な余裕がない
・寄付先の団体に不信感がある
・誰かの役に立っていると感じられない
・寄付に関する情報が不足している
・手続きが分かりにくい
このような理由から、日本では寄付が浸透しないと考えられます。
しかし最近では、クラウドファンディングの普及によって誰でも募金や寄付ができるようになりました。そのため、今では寄付は手軽で身近なものです。
また、クラウドファンディングのサイトを見れば寄付先の活動や情報が分かり、手続きもサイト内で完結できます。
もし、寄付先への不信感や情報収集に困っているのであれば、クラウドファンディングのサイトから寄付先を探すことをおすすめします。
寄付の方法
寄付の代表的な方法といえば「募金箱・街頭募金」でしょう。
しかし近年はキャッシュレス化が進み、現金を持ち歩かない人も増えています。
それに伴い、寄付の方法も多様化していて、現在ではインターネットを通じて募金をすることも選択肢の一つです。
インターネット募金には電子マネーでの募金や、ふるさと納税を含むクラウドファンディングが挙げられます。
インターネットであれば場所や時間を選ぶことなく寄付が可能です。
また「寄附金控除」の適用を検討しているのであれば、領収書の発行が必要です。
インターネット募金は街頭での募金と異なり、領収書を発行できます。
そのため、節税を目的に寄付をする人はインターネット募金やふるさと納税をおすすめします。
>>夢を応援して節税も!ふるさと納税ForGoodの詳細はこちら
寄付することのメリットとは
寄付は、事業や団体に金品を贈ることです。
そのため「寄付をすることは損ではないのか」「寄付の利点がよく分からない」と考える方も少なくありません。
以下に、寄付することによるメリットをいくつか挙げました。
1.社会の役に立てる
寄付の代表的なメリットとして「社会の役に立つ」ことが挙げられます。
寄付によって、社会や誰かのために「良いことをした」という幸福感が得られるでしょう。
内閣府の「市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」によると、寄付をした理由で最も多かった回答が「社会の役に立てるから」でした。
金額や回数に関係なく、寄付が誰かの役に立つことは間違いありません。
「なにかの形で社会の役に立ちたい」と考える方にとって、寄付は今すぐにでも取り組めるアクションだといえます。
2.応援している団体の活動を手助けできる
応援している団体の支援につながることも、寄付のメリットです。
とくに、資金難や物資不足が起こっている団体にとっては、寄付は活動の存続につながります。
また、寄付は社会を変えるきっかけとしても機能します。
自分が理想とする社会を目指している団体に寄付をすることで、その理想が現実に近づくことも、寄付のメリットとして考えられます。
・自分や家族と関係のある活動へ支援した人:11.4%
・自身が解決してほしいと思った課題に対する解決を目的に寄付した人:4.4%
出典:内閣府「市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」
上記のように、さまざまな理由で団体や事業に寄付をしていることが分かります。
もし寄付先の団体選びに迷っているのであれば、クラウドファンディングのサイトを見てみてください。自分が応援したいと思える団体や実現してほしい活動を掲げている団体を探せるでしょう。
3.時間や場所にとらわれずに社会貢献ができる
インターネットを利用すれば、いつでも・どこでも寄付が可能です。
キャッシュレス化が進む今、インターネットを通じた寄付は普及しつつあります。
クリック一つで完了するため、手軽に社会貢献できます。
またインターネットからの寄付ならば、他の自治体や海外への寄付も可能です。
これによって、自分が応援したい団体・事業が近くになくても寄附ができます。
クラウドファンディングも同様に、クラウド上で行う為、時間や場所を問いません。
より身近に・より広範囲に社会貢献ができるインターネットからの寄付は、今後さらに重要性が増すでしょう。
4.控除が受けられる
寄付したお金は、課税所得から控除される可能性があります。
特定寄付金に該当する寄付の場合、寄付金額の一部が税金の控除額になり、節税が可能です。社会貢献と同時に節税ができることは、寄付の大きなメリットといえます。
内閣府の「市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」によると、所得税の軽減制度を利用するために寄付した人は16.4%と、全体の3番目に多い理由でした。
節税を目的としていても、寄付自体は誰かの役に立つため、後ろめたさを感じにくい点もポイントです。
クラウドファンディングでは、寄付先の団体形態によっては控除を受けることができます。控除を受けられる寄付先については後述します。
③寄付団体を選ぶ際に注意したい3つのポイントとは
寄付を募っている団体は多くありますが、中には「募金詐欺」「義援金詐欺」などでお金をだまし取ろうとする架空の団体も混在しています。
詐欺被害を避けるため、寄付先の団体が本物であるか見抜くためのポイントを以下で確認しましょう。
1.団体の透明性
「どのような活動をしている団体なのか」「何を目的に活動しているのか」など、団体に関する情報の透明性は重要です。
団体の透明性の高さは、活動の「本気度」を測るための基準といえます。
また、「団体の公式ホームページがしっかりと作成されているか」も判断基準です。
「団体の基本情報が閲覧できない」「そもそもホームページが存在しない」などの場合は、寄付先が偽物の可能性があります。
クラウドファンディングにおいては、サイト上で団体の情報が掲載されています。掲載するまでの流れには、サイト運営側が介入し審査やアドバイスを受けるため、安全といえるでしょう。
2.寄付金の用途
「集められた寄付金の用途が明示されているか」も重要な判断基準です。
多くの場合、寄付ページ内や活動報告書、クラウドファンディングの団体掲載ページなどに記載があり、一般公開されています。
自分の関心がある社会課題に対して、寄付したお金を活用してくれるのかを確認しましょう。
ただし寄付を募りながら、集められたお金が何に使われているか不透明な団体もあります。
こちらも一概にはいえませんが、寄付先としては再考をおすすめします。
3.団体の信頼性
団体の信頼性を確かめることも重要です。
先ほどの透明性とは違い、こちらは団体の「計画性」を測ることを目的としています。
以下は、団体の信頼性を測るポイントの一例です。
・法人格の有無(法人化している団体は信頼性が高い)
・実績や活動期間の長さ
・財務状況
・代表者の情報
特に法人格の有無や実績については、急に準備できるものではないからこそ、信頼性を測る重要なポイントといえます。
なおクラウドファンディングでは、個人でも寄付金を募れます。
そのため、法人格が必ずあるとは限りません。
しかし、第三者である運営側が介入しているので信頼性は保証されていることが多いです。
加えて、団体の計画性や実現性に同意できれば、信頼できる寄付先として選べるでしょう。
④節税ができる!寄付金控除の申請方法とは
寄付をすると「寄付金控除」として、所得控除が受けられるようになります。
節税方法を検討している方であれば、控除を目的とした寄付も選択肢の一つです。
寄附金控除の申請方法や条件について、以下で確かめましょう。
出典:国税庁「寄附金を支出したとき」
特定寄付金への該当
寄付金控除は、全ての寄付が対象ではありません。
指定されている団体への寄付金(特定寄附金)のみが控除の対象です。
特定寄附金に該当する団体形態は以下のとおりです。
<所得控除を受けられる寄付>
1. 国・地方公共団体
2. 指定寄附金・特定公益信託の関連(科学・文化の発展など)
3. 特定公益増進法人(公益社団法人・日本赤十字社など)
4. 特定新規中小会社の関連(災害など事業継続が困難な会社)
5. 認定NPO法人(通常のNPO法人よりも高い公益性)
6. 政治活動
とくに、「特定公益増進法人」「認定NPO法人」「政治活動」には上記に加えて、個別の寄付金控除があります。
それぞれの計算式は以下のとおりです。
◆所得控除
(その年に寄付した特定寄附金の合計額)-(2000円)
◆個別の寄付金控除
・(公益社団法人等寄附金特別控除)=(その年に寄付した、要件を満たす特定寄附金の合計額-2000円)×40%
・(政党等寄附金特別控除)=(その年に寄付した特定寄附金の合計額-2000円)×30%
・(認定NPO法人等寄附金特別控除)=(その年に寄付した特定寄附金の合計額-2000円)×40%
なお、「寄付先が控除の対象団体に当てはまるか」については、管轄の税務署へ確認することをおすすめします。
寄付型クラウドファンディングから寄付先を探す際は、実行者の団体形態を確認しましょう。
必要書類
寄附金控除の申請には「寄付金控除に関する事項」を記入した確定申告書を用意します。
また、申請には「寄付額を証明できる書類」の準備も必要です。
寄付先団体から発行された領収書・受領証などを確定申告書とあわせて提出します。
手続きの方法
寄附金控除の申請は、年末調整ではなく確定申告のタイミングで行います。
寄付先から受け取った領収書・受領証がデータだった場合は、印刷せずデータのままで提出できます。
⑤寄付型クラウドファンディングとは?
起案者が立ち上げたプロジェクトに対し、支援者がオンライン上で寄付を行うクラウドファンディングです。
寄付型クラウドファンディングは寄附金控除の対象であり、節税もできます。
「購入型クラウドファンディング」も存在しますが、モノ・サービスの返礼があり、この点で寄付型とは異なります。
クラウドファンディングサイトによっては、寄付型・購入型をどちらも備えたハイブリット型も多くあります。
ふるさと納税ForGoodは、ふるさと納税を使用して自治体に貢献できるクラウドファンディングです。
寄付型・購入型、どちらも選べるので、地元への貢献や返礼品などさまざまな用途で活用できます。
通常のふるさと納税と同じくワンストップ特例制度で、ご自身の金額枠で地域へ気軽に貢献できます。
⑥まとめ
寄付は、見返りはありませんが「確実に誰かの助けになる」ことです。
日本全体が寄付に積極的ではないというデータはあるものの、日本にも寄付を通じて社会貢献を果たしている人や社会を良くしようと寄付を募っている人がいます。
インターネットからの募金・寄付金控除など、寄付に取り組みやすくなる環境や仕組みも揃い始めています。
まだ寄付の経験がないという方は、社会貢献への「一歩目」として、寄付をしてみてはいかがでしょうか。
クラウドファンディングForGoodは、お金をもらう側が負担のないよう、支援者が代わりに手数料を負担するという、画期的な仕組みをとっています。
寄付型・購入型どちらでも利用可能です。
「誰かに貢献したい」という方も、「お金を集めたい」という方も、ぜひご覧ください。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!