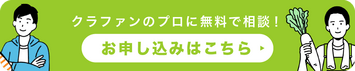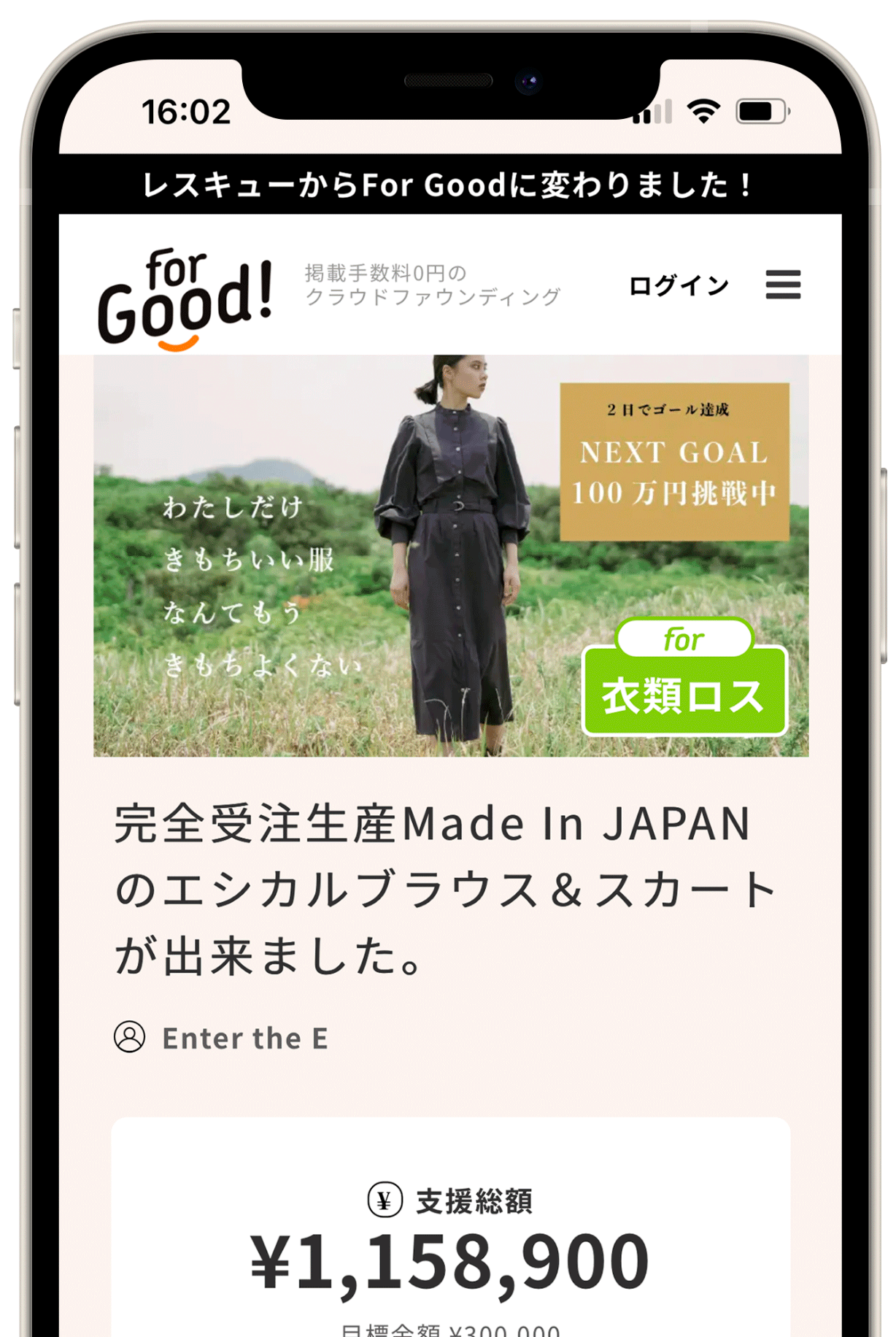クラウドファンディングの返金の仕組みを起案者・支援者別に徹底解説!
クラウドファンディングでプロジェクトを起案したり支援したりする際に「返金ってどういう仕組みなの?」と不安になったことはありませんか。
実は、返金の可否や方法はプロジェクトの形式やプラットフォーム規約によって大きく変わります。
そこで本記事では、下記内容を解説していきます。
・種類別の返金ルール
・返金方法と手続き
・返金が認められる条件
クラウドファンディングの返金の仕組に不安がある方は是非ご覧ください!
返金の仕組はクラウドファンディングの種類によって異なる
「クラウドファンディングは返金されるのか?」という疑問に答えるには、まずプロジェクトの方式や契約の形を理解することが必要です。
同じ“クラウドファンディング”でも、資金の集め方や支援の位置づけが異なれば、返金の可否や条件も大きく変わります。
ここを押さえることで、支援前の判断や、起案者としてのリスク回避に役立ちます。
All or Nothing型 vs All-in型
クラウドファンディングには「目標金額の達成」をどう扱うかによって、「All or Nothing型」と「All-in型」の2つの方式があります。
【All or Nothing型(オールオアナッシング型)】
目標金額に到達した場合のみ支援金が決済され、プロジェクトが実行されます。
未達の場合は決済されず、支援者に自動的に全額返金(または請求取消)されます。
また、起案者もクラファン利用の手数料を払う必要がない場合が多いです。
【All-in型(オールイン型)】
目標金額に届かなくても、集まった資金はすべて起案者に渡ります。
原則返金はなく、途中中止や内容変更があっても返金は起案者-支援者間の任意対応となる場合が多いです。
支援者は「返金されない前提」での参加になるため、事前の確認が重要です。
クラウドファンディング返金関連の比較表
| 方式 | 返金条件 | 支援者のリスク |
|---|---|---|
| All or Nothing型 | 目標未達で自動返金(決済取り消し) | 低い(未達時は資金戻る) |
| All-in型 | 目標未達でも資金は起案者に渡り、原則返金なし | 高い(返金は基本無し・任意対応) |
購入型 vs 寄付型
クラウドファンディングは、支援の目的やリターンの対価性によって「購入型」と「寄付型」に分けられます。
【購入型】
支援は「商品やサービスの予約購入」に近い契約です。
起案者は約束したリターン提供の義務を負い、未提供や大幅な仕様変更は契約不履行として返金請求の対象になる可能性があります。
例:新商品の試作品やイベントチケットなど。
【寄付型】
支援は「寄付」として扱われ、対価性のあるリターンは基本的になく、トラブルが起こらない限り返金義務は発生しないケースが多いです。
例:災害支援、社会活動、福祉団体の活動資金など。
契約形態別の返金義務比較表
| 契約形態 | 返金義務の有無 | 主なプロジェクト例 |
|---|---|---|
| 購入型 | リターン未提供や重大な変更時に返金義務あり | 新商品開発、イベント開催など |
| 寄付型 | トラブルの場合は個別対応で返金 | 災害支援、社会貢献活動など |
詳細はプラットフォームの規約を確認する
同じ方式・型であっても、プラットフォームによって返金条件は異なります。
・返金処理の自動化の有無
・補償制度や保証の範囲
・リターン遅延・不備や中止時の取り扱い
これらは運営会社ごとの規約で細かく定められているため、支援前・起案前には必ず目を通すことが大切です。
クラウドファンディングの返金方法や手数料は?
返金の仕組みを理解したら、次は「実際にどのように返金されるのか」を知っておくことが重要です。
方式によっては自動的に返金される場合もあれば、当事者同士で話し合いが必要になる場合もあります。
ここを押さえておくことで、支援者は安心して参加でき、起案者はトラブル時の迅速な対応が可能になります。
All or Nothing型で未達の場合は自動返金
All or Nothing型は、目標金額に到達した場合のみ資金が実行者に渡る方式です。
そのため、目標未達のプロジェクトは成立せず、支援金は自動的に返金されます。またこの時、起案者側にもクラファンサイト利用の手数料はかかりません。
クレジットカード決済であれば請求が取り消され、銀行振込やコンビニ決済の場合もプラットフォーム側で返金処理が行われる場合が多いです。
支援者や起案者が特別な手続きをする必要はなく、プラットフォームが自動で返金を完了するのが大きな特徴です。
トラブルの場合は起案者-支援者間で個別対応
一方で、プロジェクトが成立した後に発生するトラブル、例えばリターンが届かない、内容が大きく異なる、活動が中止されたといった場合は状況が異なります。
多くのプラットフォームでは、返金は起案者と支援者の間で直接行うよう求められます。
プラットフォームはプロジェクトごとのトラブルに対して責任を追わないことがほとんどです。
銀行振込や電子決済サービスを利用し、双方が合意のうえで返金が進められるのが一般的です。
プラットフォームが仲介や補償を行わない場合が多く、起案者の誠実かつ迅速な対応が信頼維持のカギとなります。
All or Nothing型でもトラブルによる返金時は起案者にクラファン手数料が発生する
All or Nothing方式で目標金額が未達の場合は、支援金が全額返金されるのと同時に起案者にクラウドファンディング利用手数料の負担も発生しません。
しかし、プロジェクトが成立した後に、起案者の責任で中止や失敗となった場合は事情が異なります。
基本的に、この場合はプラットフォーム利用手数料は返ってこないと考えてください。
中止理由によっては例外的に手数料負担が免除されることもありますが、リターン提供時のトラブルや起案者のミスによる中止では返金されないのが一般的です。
例として、手数料10%のプラットフォームで100万円の支援を集めた場合、プロジェクトが中止になって返金対応を行うことになっても10万円の手数料は戻らないことになります。
こうした損失を避けるためにも、リターンの準備や提供体制は事前に十分整えておくことが重要です。
このように、返金の方法は方式や状況によって大きく変わります。
次に、起案者がどのような場合に返金義務を負いやすいのかを具体的に見ていきましょう。
起案者に返金義務が生じやすいケース
クラウドファンディングでは、契約形態によっては法律的に返金義務が発生しない場合もあります。
しかし、起案者の行動やプロジェクトの進行状況によっては、法的にも社会的にも返金対応が求められる場合があります。
ここでは特に返金義務が生じやすい3つのケースを紹介します。
リターンを提供できなかった場合
購入型クラウドファンディングでは、支援は商品の予約購入やサービス提供契約に近い性質を持ちます。
そのため、約束したリターンを全く提供できなかった場合、契約不履行(債務不履行)として返金義務が発生する可能性が高いです。
例えば、製造トラブルで商品が完成しなかった、イベントが中止になったといったケースがこれに該当します。
虚偽記載や不当表示をしていた場合
プロジェクトの説明や画像が実態と著しく異なっていた場合、支援者は契約の取消しや返金請求が可能な場合があります。
「〇〇に資金を使います」と明記しておきながら別の用途に流用した、写真や仕様で誤解を招く表現をしたといった場合は、詐欺や景品表示法違反にあたることもあります。
このような行為は返金義務だけでなく、法的責任を伴うリスクも大きくなります。
プラットフォーム規約違反をした場合
クラウドファンディングの各プラットフォームは、独自の利用規約で返金に関するルールを定めています。
例えば、特定ジャンルの禁止や、進捗報告の義務、資金の使途制限などです。これらに違反した場合、プラットフォームから返金指示が出ることがあります。
規約違反は信頼失墜につながるだけでなく、今後のプロジェクト掲載が難しくなる可能性もあります。
これらのケースでは、起案者の対応次第でトラブルが拡大することもあれば、誠実な対応によって信頼を保つことも可能です。
次は、支援者側から見て返金が認められやすいケースについて解説します。
支援者への返金が認められやすいケース
クラウドファンディングは原則として自己責任での支援ですが、一定の条件下では返金が認められやすい状況があります。
ここでは、支援者が返金を受けられる可能性が高い代表的なケースを解説します。
目標未達のAll or Nothing型で自動返金される場合
All or Nothing型は、目標金額に達した場合のみ成立する方式です。
目標未達であればプロジェクトは不成立となり、支援金は決済されず、クレジットカードの請求も自動で取り消しになります。
支援者が特別な手続きを行う必要はなく、プラットフォーム側で全額返金処理が行われます。
起案者が明確にリターン契約を破った場合
購入型クラウドファンディングでは、支援は商品の予約購入に近い契約とみなされます。
そのため、リターンが全く届かない、または大幅に異なる内容で届いた場合は、契約不履行として返金を請求できる可能性があります。
ただ、プラットフォームごとに起案者への責任や契約の形式が定められているので確認しましょう。
例えば、仕様が大きく変更された商品や、告知していたイベントが中止されたケースなどです。
プラットフォームに補償制度が用意されている場合
一部のプラットフォームでは、条件を満たすと返金や再送付などの補償を受けられる制度があります。
対象となるのは、未配送・初期不良・重大な仕様違いなどのケースが多く、申請期限や証拠の提示が必要です。
支援前に補償制度の有無や条件を確認しておくことで、トラブル時の安心感が高まります。
こうした条件に該当する場合、返金の可能性は比較的高くなります。
次は逆に、支援者への返金が認められにくいケースについて見ていきましょう。
支援者への返金が認められにくいケース
クラウドファンディングは、プロジェクトの性質や契約形態によっては返金がほぼ期待できない場合があります。
ここでは、特に返金が認められにくい3つのケースを紹介します。
All-in型プロジェクトで未達でも資金が渡っている場合
All-in型は、目標金額に届かなくても集まった資金がすべて起案者に渡る方式です。
そのため、プロジェクト成立後は原則として返金義務がなく、支援者都合での返金は認められません。
支援前にこの方式であるかどうかを確認することが重要です。
支援者自身の勘違いや後悔による返金希望
「思っていた内容と違った」「やっぱり必要なくなった」といった支援者の心変わりや誤解は、返金理由として認められません。
購入型であっても、契約上は起案者に落ち度がないため、法的に返金義務が生じないのが一般的です。
リターンの遅延や軽微な変更があるだけの場合
製造や配送の遅れ、素材や仕様の小幅な変更などは、重大な契約違反とみなされにくいため返金対象外となることが多いです。
ただし、遅延や変更が大きく、事前説明もない場合は返金請求の余地が生まれる可能性があります。
こうしたケースは、支援前にしっかりと方式や内容を確認していれば回避できることも多いです。
次は、支援者が返金可否を判断するために確認すべきチェックポイントを整理します。
支援者が返金に確認すべきチェックポイント
返金の可否は、支援前の情報収集である程度判断できます。
ここでは、支援前に必ず確認しておきたい4つのポイントを整理しました。
これらを押さえておけば、不測のトラブルでも慌てず対応できます。
All or Nothing型かAll-in型か
クラファンの方式によって返金の仕組みは大きく変わります。
・All or Nothing型:未達なら自動返金、達成の場合は原則返金無し
・All-in型:未達でも資金が渡り、返金は原則なし
支援前に方式がどちらかを必ず確認しましょう。
プラットフォームの利用規約
返金の条件や手続きはプラットフォームごとに異なります。
・自動返金の条件
・補償制度の有無
・トラブル発生時の対応フロー
規約を読まずに支援すると、想定外の条件に縛られる可能性があります。
プロジェクトごとの返金ポリシー/リスク説明の明記
起案者が独自に返金ルールを設けている場合があります。
・リターン遅延時の対応
・内容変更時の方針
・中止時の返金可否
本文やFAQ欄に記載があるかどうかを確認しましょう。
実行者の実績や信頼性
返金以前に、実行者が信頼できるかどうかは最重要です。
・過去のプロジェクト実績
・SNSや公式サイトでの活動記録
・過去支援者からのコメントやレビュー
信頼できる起案者はトラブル時の対応も丁寧な傾向があります。
これらをチェックしておけば、返金の可否だけでなく、安心して支援できるかの判断材料にもなります。
最後に、返金義務やルールを理解し、トラブルを防ぐためのまとめをお伝えします。
まとめ|返金の義務やルールを理解してトラブルを防ごう
クラウドファンディングは、プロジェクト方式や契約形態によって返金の可否が大きく変わる仕組みです。
支援者にとっては安心して支援するために、起案者にとっては信頼を守るために、返金のルールを理解しておくことが不可欠です。
・方式の確認は必須:All or Nothing型かAll-in型かで返金リスクは大きく変わる
・契約形態を把握:購入型は売買契約に近い契約形態の可能性あり、寄付型は寄付金扱い
・規約とポリシーを事前チェック:プラットフォーム規約や起案者独自の返金条件を必ず読む
・信頼性を見極める:過去の実績や発信内容から、安心できる起案者か判断する
返金トラブルの多くは、プロジェクト起案前・支援前に情報を確認していなかったことが原因で発生します。
事前に方式・規約・返金条件を理解し、信頼できるプロジェクトを選ぶことで、後悔のないクラウドファンディング体験につながります。
クラウドファンディングに興味がある方は、
ぜひ「For Good」で一緒に取り組みましょう!