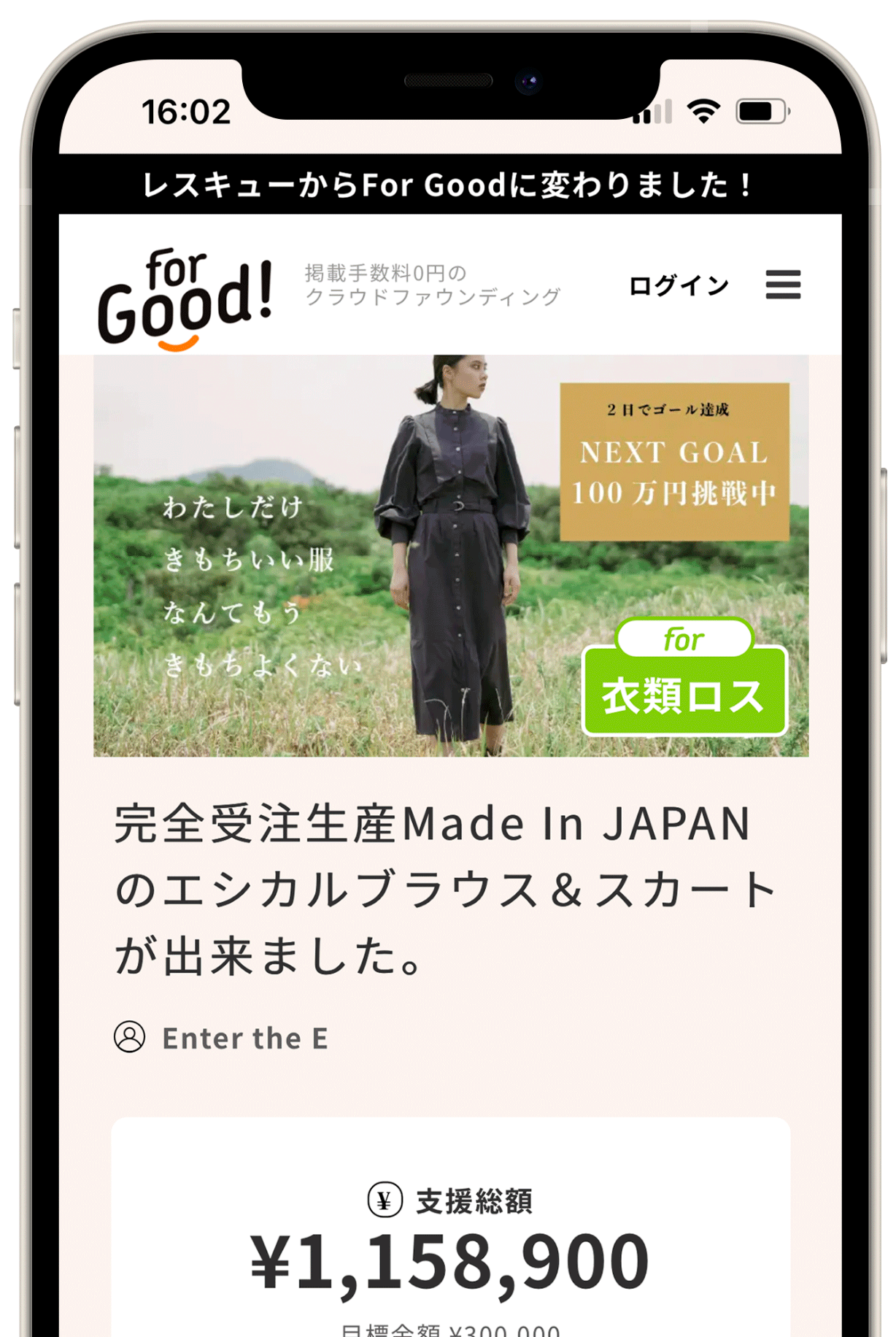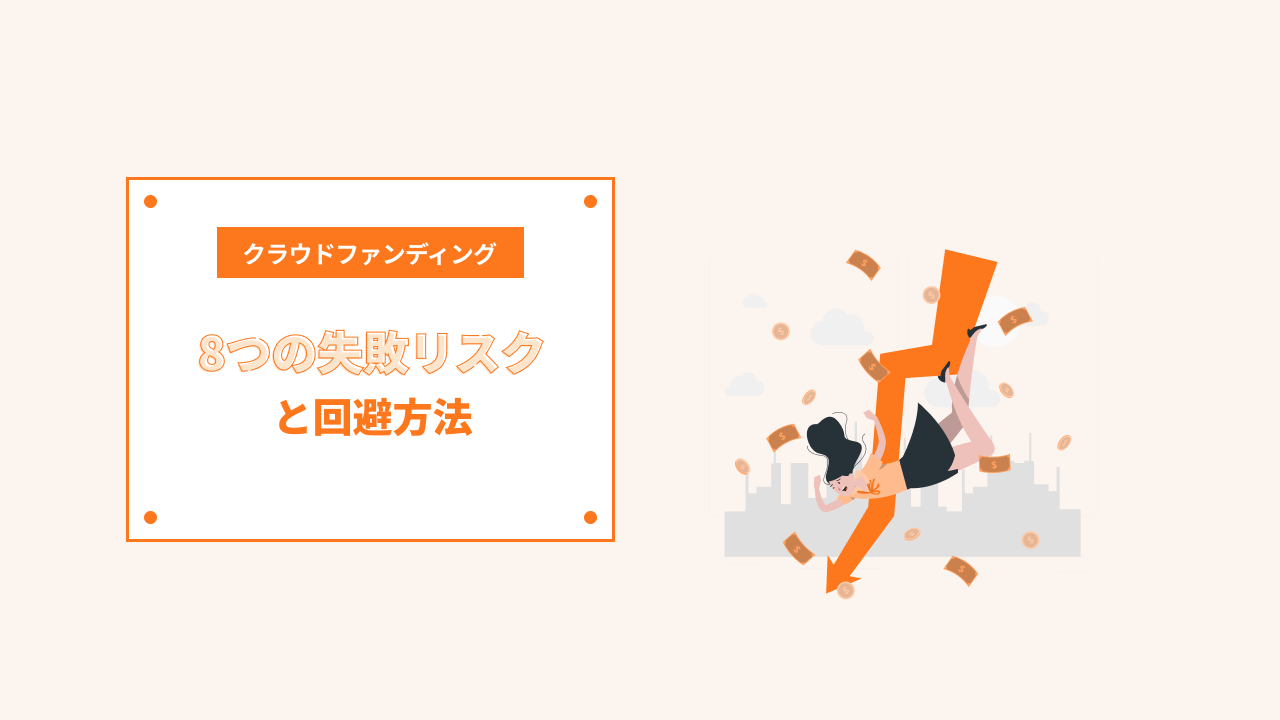
クラウドファンディングを失敗したらどうなる?8つの失敗リスクと要因を解説
クラウドファンディングをやるなら失敗しないように備えたいと思っていらっしゃいますよね。
クラウドファンディングでは、事前準備からプロジェクト実行まで様々な失敗に繋がる要因があります。しかし、準備をし着実に進めていくことで、想像を上回る成功に繋がる事例もこれまでに多くあります。
今回は、失敗の要因をご紹介していきますので、クラウドファンディングを成功させるために是非参考にしてください。
\プロジェクトに関するご相談を無料で実施中/
目次
Q.目標金額を達成せず失敗したらプロジェクトは実行できない?
A.募集方式がAll-inなら実行可能です。All-in方式は「1人から支援金が支払われた時点」でプロジェクトが成立します。
一方、All or Nothingの場合、目標金額に達しなければプロジェクトは実行できません。ForGoodはAll-in方式のみを採用しているため、目標金額に達成しなかった場合でもプロジェクトを断念せず実行に移せます。

Q.失敗したら集まったお金はどうなる?返金は必要?
A.All-in方式であれば、プロジェクト実行に問題があっても返金は不要です。
受け取った支援金は「目標金額に達していない」「プロジェクトが失敗した」などの場合でも問題なく受け取れます。
All or Nothingではプロジェクトが実行できない場合に返金が必要ですが、ForGoodはAll-in方式のみを採用しています。
Q.失敗したら手数料はかかる?
A.原則、プロジェクト失敗時に手数料はかかりません。手数料が発生するタイミングは、支援金を受け取るときです。
Q.失敗したら借金になる?
A.借金にはなりません。リターンの返礼品や元々の事業計画など、損益計算の結果「赤字」になることはありますが、クラウドファンディングの失敗がすぐ借金につながることはありません。
Q.クラウドファンディングの失敗率は?
A.失敗率は概ね「70〜80%」といわれています。
「目標金額には達していないが、ある程度の資金は獲得できた」ことを成功とするならば、All-in方式の失敗率はこれよりも低くなるでしょう。

ForGoodの「いっしょプラン」は成功率が90%を超えています。
サポーターが伴走して、一緒にプロジェクトの準備・公開を進められます。
初めてクラウドファンディングを行う方でも安心して利用できるため、ぜひご相談ください。
①クラウドファンディングの失敗とは?
クラウドファンディングの失敗とは何でしょうか。
やるからには目標金額を達成させたいと思い、失敗しないように備える方法を考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、目標金額を達成しただけでは、失敗しなかったとは言いにくいかと思います。
なぜなら、クラウドファンディングはあくまでスタートだからです。
クラウドファンディングでプロジェクトを実行するための資金をきちんと調達しても、プロジェクトを実行できなければ、プロジェクトは失敗したと言えるでしょう。
クラウドファンディングでは、事前準備からプロジェクト実行までの間に失敗に繋がる要因が多く存在していますので、失敗要因を知って対策していくことが重要です。

>>クラウドファンディングについて詳しく知りたい方はこちらをお読みください
All in 方式とAll or Nothingとは?
クラウドファンディングにはAll in方式とAll or Nothing方式という2つの方式があります。

All in方式では、目標金額を達成しなかった場合でも集まった支援金を全額受け取ることができますが、
All or Nothing方式で挑戦した場合にはプロジェクトに失敗した場合はお金を受け取ることができません。
For Goodでは、
①実行者さんの想いに共感して集まった支援は100%受け取ってほしい
②支援金額に関わらず、プロジェクトの実施を決めているプロジェクトに掲載いただいている
という2つの理由から、All in方式を採用しています。
\All in 方式でプロジェクトを始めたい方はご相談ください/
②失敗につながる8つの要因

1. プロジェクト準備が足りない
クラウドファンディングでは、公開前に広報をしていたかで圧倒的に成功率が変わります。
あなたの計画や実行する予定のプロジェクトを多くの方は知りません。
まずは自分のSNSで告知したり、周りの知り合いに話すことでプロジェクトを実施する事を認知してもらいましょう。
プロジェクトを多くの人に見せて、欲しいリターンや共感するポイントをヒアリングしながらフィードバックをもらい、修正を繰り返していきましょう。
これにより事前にたくさんの人を巻き込むことができ、多くの人に支援してもらえるプロジェクトになります。
また、ただ支援をお願いするより、同じ気持ちでプロジェクトに関わってくれる仲間を増やすことができます。
>>事前告知やプロジェクトのブラッシュアップ方法を知りたい方はこちら
2. プロジェクト内容に共感できない
クラウドファンディングは、頑張っているから、目指している社会・未来を作って欲しいからといった「共感」が支援に繋がります。
そのため、「共感」が生まれるプロジェクト内容でないと支援を集めることは難しいです。
・作りたい社会に共感するプロジェクト
・目指している方向性を分かりやすく伝えているプロジェクト
・リターンが欲しくなるプロジェクト
などが支援を大きく集めます。
そのためには支援者に目指す未来を共有し、同じ未来を見せることで、プロジェクトに共感し、心が揺さぶるように設計できるかが重要です。
そうでなければたとえどんなに影響力があっても、テクニックがあってもプロジェクトは失敗してしまいます。
まずは、「共感」を本当に生むプロジェクトになっているのかを確認することが、成功への第一歩です。
3. 目標金額の設定が不適切
プロジェクトの目標金額の設定が適切ではないと失敗の原因になります。
目標金額を設定する際は、まず最低限必要な金額を決定しましょう。

目標金額が早いうちから達成されているかで、プロジェクトページを初めて見た際の印象が大きく変わってきます。
まずは早い段階でプロジェクトを成功させることで、一度目標を達成している実績を作ることができ、盛り上がっている印象を与えられるので、より支援金が集まりやすくなります。
最低限必要な金額以上を集めたい方は、ネクストゴールの設定がおすすめです。
>>こちらを参考に、目標金額の設定をしてみてください
4. 魅力的なリターンを作れてない
リターン設定でクラウドファンディングが失敗するかどうかが変わってきます。
まず第一に「リターンが支援者のニーズを満たしていること」がとても重要です。
どんなに面白いプロジェクト、共感できるプロジェクトでも、支援したいリターンがなければ支援を躊躇してしまうことは想像できるでしょう。
事前に自分の支援者になりそうな人が支援しやすい、金額・リターンの内容になっているのかを確認することが重要です。

リターンを設定する上で気をつけなければいけないのが価格設定です。
いくら大きな金額を調達できても、リターン品の準備や発送にかかる費用が集まった金額をうわまってしまえば、赤字になってしまいます。
特に、All inの場合は達成できなかった場合でもリターンを発送し、プロジェクトを実行する必要があるため、リターンの設定には注意が必要です。
5. スタート5日間で支援が集まらない
プロジェクトの初動もクラウドファンディングが成功するか?失敗するか?に大きく関わってきます。
目標金額の達成率がプロジェクトの掲載開始1週間で20%ほど集まっていると、「このプロジェクトは盛り上がっている!」「しっかり支援金を集められている信用できるプロジェクトだ!」という印象を持ってもらうことができ、より支援が集まりやすくなります。
ここで支援を集めることができないと、盛り上がってないプロジェクトと認識されてしまい、支援が集まりにくくなるため2週間目からの盛り返しが難しくなり失敗しやすくなります。
そうならないためにも、
・適切な目標設定ができているか
・事前に開始と同時に20%集められる支援者を集めておけるか
が重要です。
6. 広報活動が行えていない
プロジェクト開始後は、広報できるかが、失敗しないためにとても重要です。
・個人で拡散・支援のお願いをする
・SNSで開始の告知や進捗状況を報告する
・イベントを開催して直接思いを伝える場所を作る
など、適切なタイミングで適切な広報を行っていきましょう。
逆に、目標から逆算した広報活動を行えば、確実に支援に繋げることができます。
>>プロジェクト開始後の広報活動についてはこちらで徹底解説しています
7. プロジェクト終了後、リターンの対応に問題がある
プロジェクト終了後に実施する「出資者へのリターン対応」も、クラウドファンディング失敗の原因となり得ます。
以下は、実際に発生した「リターン実施時に起きたトラブル」の一例です。
・事前に告知されていた返礼品と、実際に送られてきた返礼品があまりにも違う
・リターンとして設定していた優待券を、後になって「使えない」と主張する
・リターンの送付が遅れた際、現状の報告や個別対応などが一切なかった
以上の例から分かるように、資金が集まったことに満足し、リターンの対応がおろそかになったことがトラブルの原因です。
こうしたトラブルは出資者の怒りを買うばかりか、訴訟にまで発展するおそれもあります。
8. 炎上リスクを対策していない
一般的に、クラウドファンディングにおける「炎上」は稀な事例とされています。
プロジェクトの不履行や不誠実な対応をしない限り、炎上することはあまりありません。
ただし思わぬ部分で行き違いが生じた際、対応に不始末があると炎上の原因になってしまいます。
また、管理しているSNSアカウントでの言動が炎上の原因となることもあります。
「常に誠実な対応を心がける」「不用意な言動は差し控える」など、万が一に備えて炎上の発生を抑えるための対策をしておきましょう。
For Goodでは、自分だけで行って失敗しないか不安という方に向けて、クラウドファンディングの
プロがサポートさせていただく「いっしょプラン」をご用意しております。
いっしょプランとは?
For Goodでは専任担当者による伴走サポート「いっしょプラン」もご用意しております。
利用者の満足度調査では、満足度88%*1を達成しており、ミーティングでの相談サポート、ページ作成とリターン設計のアドバイス、支援者を集める広報戦略ミーティングを実施しています。
*1 2022年12月実行者45人に行った弊社アンケート結果
*² 集まった金額の7%、もしくは最低金額5万円(税別)でご利用いただけます。
>>いっしょプランについて知る
\失敗しないか不安という方に無料相談を受け付けています/
③クラウドファンディングの始め方

以下がプロジェクトを行う際の流れです。
①事前準備
②ページ作成
③広報
④プロジェクト実行
⑤リターン・活動報告
>>プロジェクト実行の流れについては詳しく知りたい方はこちら💡
④クラウドファンディングの失敗|まとめ
今回は、クラウドファンディングを失敗リスクと要因についてご説明しました。
<失敗につながる8つの要因>
1.プロジェクト準備が足りない
2.プロジェクト内容に共感できない
3.目標金額の設定が不適切
4.魅力的なリターンを作れてない
5.スタート5日間で支援が集まらない
6.広報活動が行えていない
7.プロジェクト終了後、リターンの対応に問題がある
8.炎上リスクを対策していない
プロジェクトを実施することを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
\クラウドファンディングを成功させる方法を無料で相談いただけます/