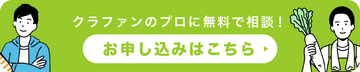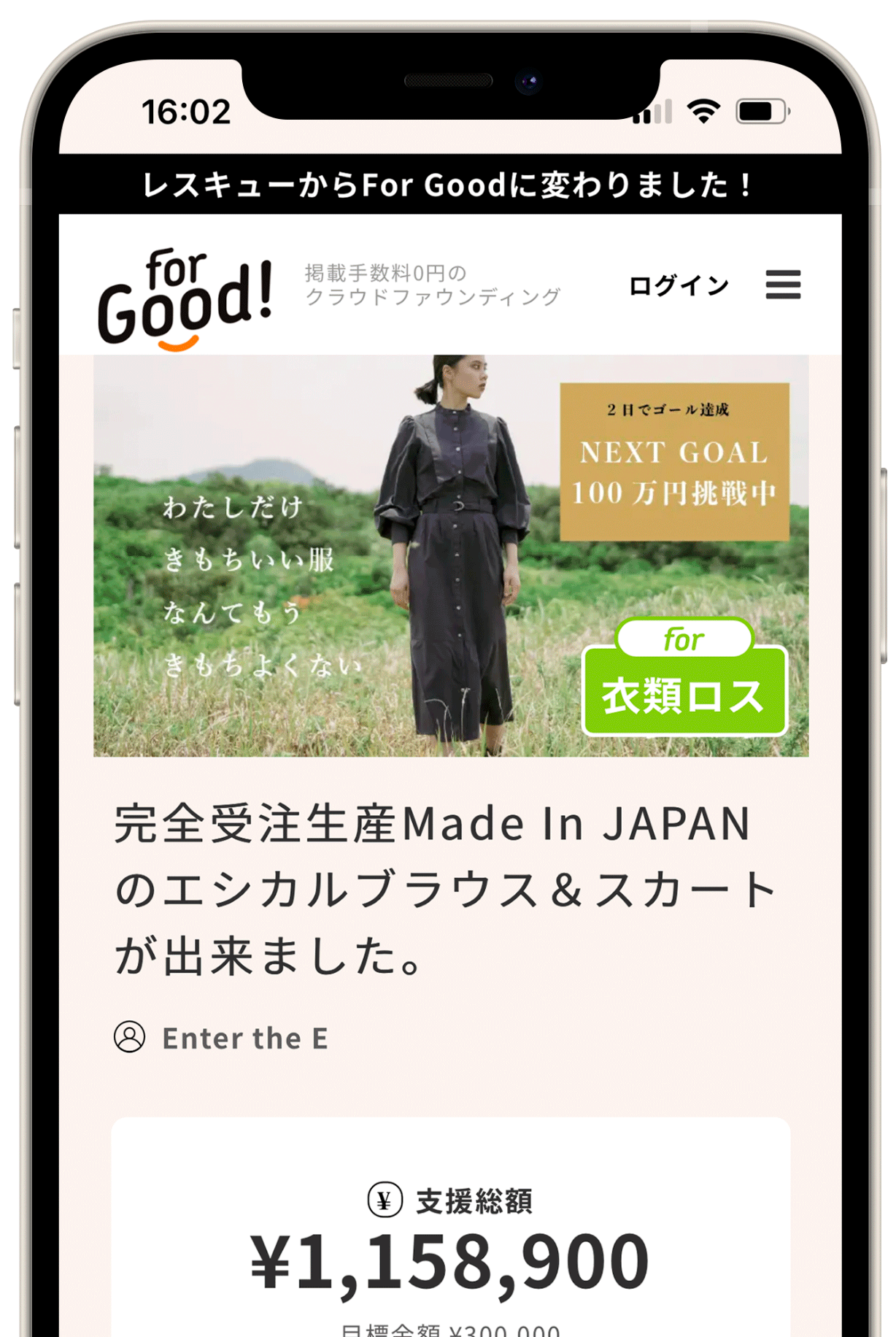種類別|クラウドファンディングの会計処理!経費で落とせる?
クラウドファンディングで支援した費用や、支援者から受け取った金銭を会計上で処理する方法をご存じでしょうか。
この記事では、購入型・寄附型・株式投資型の仕訳例をそれぞれ示して、会計処理の方法を解説します。
クラウドファンディングにかかわる費用に関してはプロに直接聞くのが最も効率的。
実行者の手数料0円「For Good」のアドバイザー(キュレーター)に、無料で相談しませんか?
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
- クラウドファンディングの分類
- 購入型クラウドファンディングの会計処理
- 1. 個人がクラウドファンディングを実行した場合
- 2. 法人がクラウドファンディングを実行した場合
- 3. 個人がクラウドファンディングを支援した場合
- 4. 法人がクラウドファンディングを支援した場合
- 寄附型クラウドファンディングの会計処理
- 1. 個人がクラウドファンディングを実行した場合
- 2. 法人がクラウドファンディングを実行した場合
- 3. 個人がクラウドファンディングを支援した場合
- 4. 法人がクラウドファンディングを支援した場合
- 株式投資型クラウドファンディングの会計処理
- クラウドファンディングの会計処理にかかわる他の質問
- 購入型クラウドファンディングの支援は交際費や広告宣伝費になりますか?
- 任意団体で寄付型クラウドファンディングを実施した場合はどのように会計処理をするべきでしょうか?
- 経費に関する書類はいつまで保管しなければなりませんか?
- クラウドファンディングサービスの事業者に支払う手数料は経費になりますか?
- まとめ
クラウドファンディングの分類
クラウドファンディングに関する費用の会計処理方法について説明する前に、まずクラウドファンディングの分類について解説します。
クラウドファンディングがどの型に分類されるかによって、会計処理の方法が異なるためです。
クラウドファンディングは、大きく分けると以下の3種類です。
|
分類名称 |
特徴 |
|
購入型 |
|
|
寄付金控除型 |
|
|
株式投資型 |
|
より細かい分類や特徴については、以下の記事をご参照ください。
簡単に説明!クラウドファンディングとは?仕組みや種類、メリット等
購入型クラウドファンディングの会計処理
はじめに、購入型クラウドファンディングで発生した支援金や費用の会計処理について解説します。
実行者、支援者ともに個人と法人のどちらに属するのかによって、処理方法が異なります。
また個人の場合、プロジェクト内容の事業性も売上の分類に影響するので注意が必要です。
以下のケースごとに分けて、費用処理方法を解説します。
1. 個人がクラウドファンディングを実行した場合
2. 法人がクラウドファンディングを実行した場合
3. 個人がクラウドファンディングを支援した場合
4. 法人がクラウドファンディングを支援した場合
1. 個人がクラウドファンディングを実行した場合
個人が購入型クラウドファンディングを実施するケースでは、売上の分類が「事業所得」と「雑所得」の2種類に分かれます。
両者を分ける基準は、プロジェクトの事業性です。
プロジェクトの内容が個人の事業と結びつくときは、売上を事業所得として計上します。
一方で、プロジェクト内容に事業性がないときは、雑所得として計上します。
いずれも、商品の原価や製作費用などは経費への算入が可能です。
2. 法人がクラウドファンディングを実行した場合
実行者が法人の購入型クラウドファンディングでは、帳簿に記入する売上の会計処理が2段階で構成されます。
支援金はリターンの提供前に受け取るため、一度「前受金」で処理したのち、リターンの提供時に前受金を取り崩して「売上」の計上をする仕組みです。
以下の仕訳例を参考にしてください。
<50,000円の支援を受けたときの仕訳例>

リターンの提供で発生した経費は、以下のように「支払手数料」で処理するのが一般的です。
<30,000円のプラットフォーム手数料を支払ったときの仕訳例>

取引の都度、仕訳が発生するルールを把握しましょう。
3. 個人がクラウドファンディングを支援した場合
個人が購入型クラウドファンディングを支援したときに、リターンが支援者の事業と関連していれば、支援金は経費で落とせます。
また、リターンの価額が100,000円以上で1年以上使用できるときは、固定資産に計上します。
固定資産は、耐用年数に応じて減価償却費の計上が可能です。
リターンの内容が事業と無関係で経費に算入できないケースでも、個人の確定申告で寄附金控除の制度を利用できる可能性があります。
4. 法人がクラウドファンディングを支援した場合
法人が出資した支援金は、「販売費及び一般管理費」の適切な勘定科目か、「寄附金」を利用して、経費の計上ができます。
両者の相違点は、支援の目的です。
自社の営業活動としてクラウドファンディングの支援をしたときは、販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」に算入できます。
一方で、親交のある団体との付き合いで支援をしたようなケースでは、寄附金への算入が適切です。
法人が出費した寄附金は、損金算入の範囲が限られます。詳細は後述します。
寄附型クラウドファンディングの会計処理
続いて、寄附型クラウドファンディングにおける支援金の会計処理を紹介します。
購入型と同様に、こちらも実行者や支援者が個人か法人かで変わります。
しかしリターンが存在しないため、購入型とは異なる処理方法です。
先ほどと同様にケースごとに分けて、費用処理方法を解説します。
1. 個人がクラウドファンディングを実行した場合
個人が寄附型クラウドファンディングで資金を調達したときは、2種類の会計処理が存在します。
支援者が法人であるか、個人であるかに応じて処理方法が異なります。
法人から支援を受けたときは、「寄附金収入」での会計処理が可能です。
寄附金収入は一時所得にあたり、発生した経費も計上できます。
個人から受けた支援金は贈与に該当し、贈与税が発生します。
ただし、贈与税には110万円の控除があるため、総額が100万円以下の支援金は課税の対象外です。
2. 法人がクラウドファンディングを実行した場合
法人が寄附型クラウドファンディングで得た支援金は収入に計上し、法人税の課税対象として扱います。
利用する勘定科目は、「雑収入」や「受贈益」、「寄附金収入」です。
実施に要した費用は、経費に算入できます。以下の仕訳例を参考にしてください。
<法人が10万円の支援金を受けたときの仕訳例>

<1万円のプラットフォーム利用料を支払ったときの仕訳例>

なお、寄附型クラウドファンディングで受け取った支援金は、消費税が非課税です。
消費税は、対価が発生する取引に課税されます。
そのため寄附金には対価性がなく、無償で金銭を得るため、消費税の課税対象から外れます。
参考:国税庁「消費税のしくみ」
3. 個人がクラウドファンディングを支援した場合
個人が寄附型クラウドファンディングを支援するケースでは、確定申告で寄附金控除を受けられる可能性があります。
寄附金控除の可否は、クラウドファンディング実行者の形態に応じて変わります。
控除を受けられる主な支援先は、国・地方公共団体・特定公益増進法人(公益社団法人や公益財団法人)です。
参考:国税庁「No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算」
以下は、寄附金の仕訳例です。
<個人が5万円の支援金を寄附したときの仕訳例>

4. 法人がクラウドファンディングを支援した場合
法人が寄附型クラウドファンディングで支援するときは、「寄附金」として処理します。
仕訳例は以下のとおりです。
<法人が5万円の支援をしたときの仕訳例>

ただし、法人の寄附金では損金算入の限度額が変化します。
国または地方公共団体に対する寄附金は、全額の損金算入が可能です。
特定公益増進法人に寄附をしたときは、特別損金算入限度額の計算式に基づいた金額を上限として、損金に算入できます。
参考:国税庁「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金」
株式投資型クラウドファンディングの会計処理
最後に、株式投資型クラウドファンディングの実行者、支援者における会計処理の方法を紹介します。
個人事業主を含む個人が株式投資型クラウドファンディングを行うケースはほぼないため、以下のケースについて解説します。その下の仕訳例とあわせて確認しましょう。

<受取時(5万円の支援を受けたとき)>

<支援時(5万円の株式を取得して支援したとき)>

<配当(500円の配当金が確定し、後日入金されたとき)>

<売却(5万円で取得した株式を6万円で売却したとき)>

クラウドファンディングの会計処理にかかわる他の質問
クラウドファンディングの会計処理について、前述の内容とは別の疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、よくある質問2つを解説します。質問内で登場する立場に該当する方は、参考にしてください。
購入型クラウドファンディングの支援は交際費や広告宣伝費になりますか?
結論として、個人事業主が自身の事業を宣伝する目的で購入型クラウドファンディングを支援したとき、事業と直接的な関連があれば、交際費や広告宣伝費への経費計上は可能です。
その他、購入した商品を事業のために利用するのであれば経費にできる事があります。
任意団体で寄附型クラウドファンディングを実施した場合はどのように会計処理をするべきでしょうか?
協会や自治会など、法人格を持たない諸団体のことを任意団体と呼びます。
収益事業に取り組んでいる任意団体では、一般の企業と同様に法人税が課されます。
そのため、「寄附金収入」や「受贈益」の計上と、必要に応じて経費を計上する会計処理が適切です。
経費に関する書類はいつまで保管しなければなりませんか?
クラウドファンディングに限らず、経費に関する書類は法人は7年。青色申告を行っている個人事業主は7年、白色申告を行っている個人事業主は5年とされています。
保管場所がないときは、一定の要件を満たせば電子データでの保存が許可されています。
クラウドファンディングサービスの事業者に支払う手数料は経費になりますか?
サービスの事業者に支払う手数料は、経費として処理できます。勘定科目は「支払手数料」です。
なお、ForGoodでは、実行者の手数料は0円、支援者側でシステム手数料が税別220円、クレジットカードの決済手数料が税別5%となっています。
まとめ
今回は、クラウドファンディングの会計処理について解説しました。
購入型・寄附型・株式投資型それぞれの特徴に応じて会計処理の方法が変わる点を把握しましょう。
また、支援者と実行者の立場でも、適切な会計処理が異なります。
リターンの有無や個人事業との関連など、論点を整理したうえでの正しい会計処理が大切です。
法人税や消費税を適切に納付するには、会計の正確性が求められます。
クラウドファンディングを実施した方、支援した方は、この記事を参考に会計処理をしましょう。
ForGoodでは、クラウドファンディングにかかわる相談を無料で相談中!
税金や細かな費用面の相談もぜひお気軽にお問い合わせください。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!