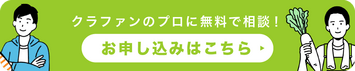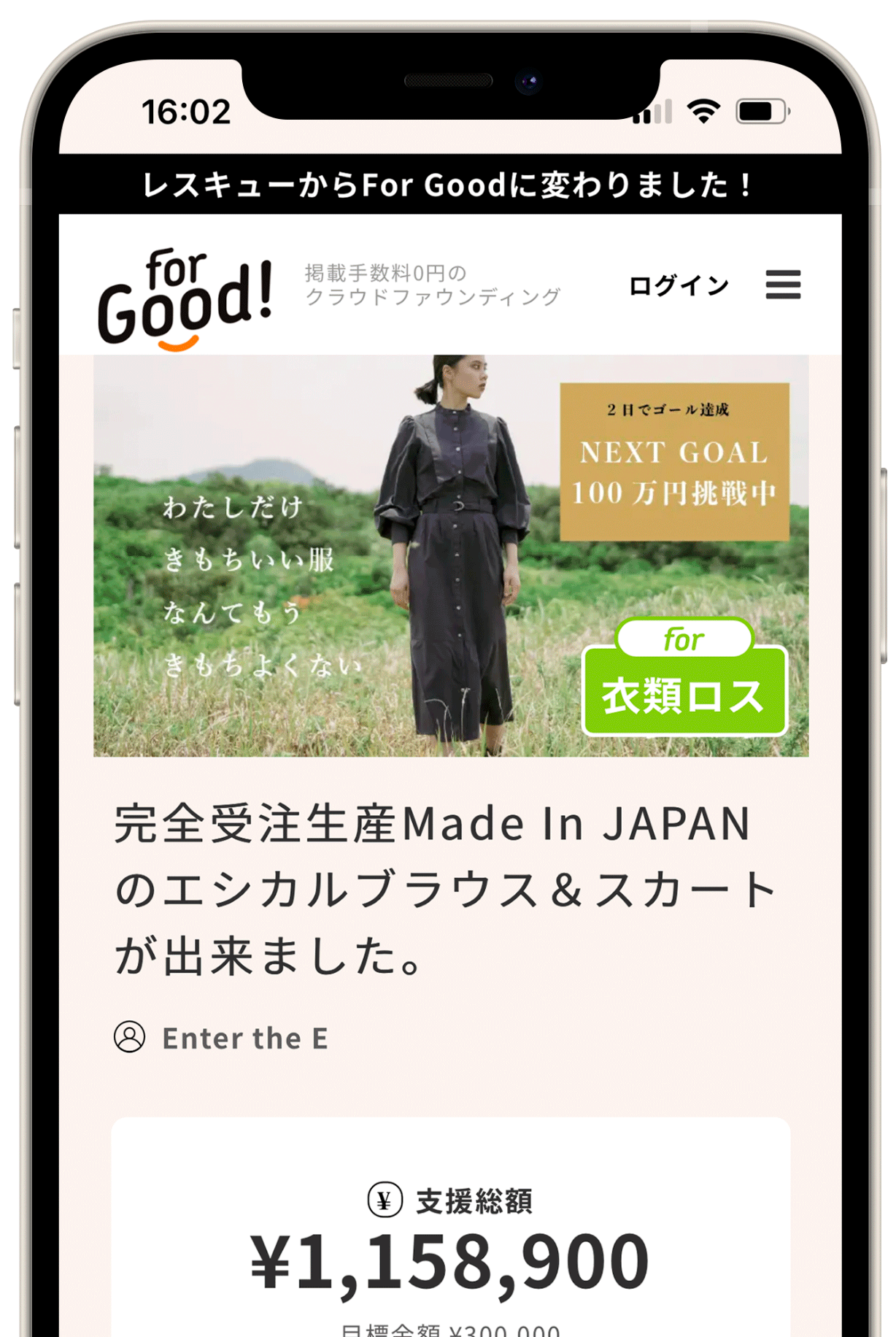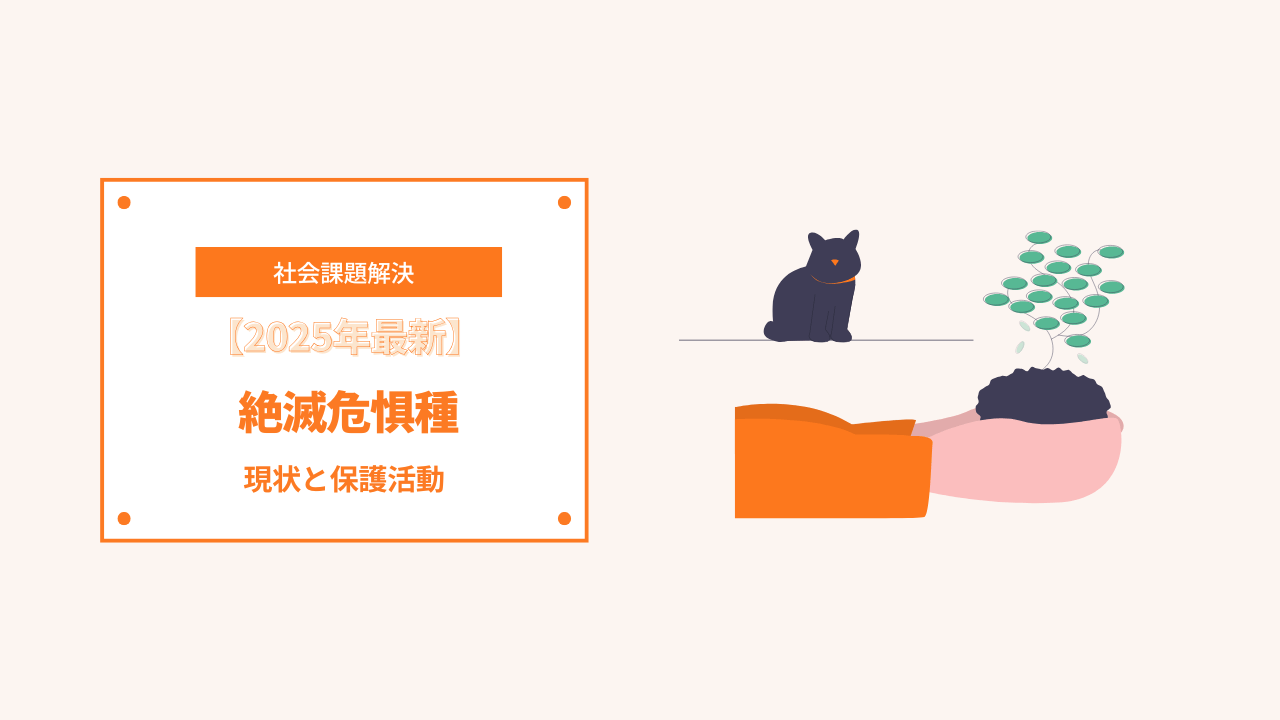
【2025年最新】絶滅危惧種の現状と保護活動
私たちの身近な自然の中で、ひっそりと数を減らしている生き物たちがいます。
どんな動物や植物が絶滅の危機にあるのか、日本や世界の現状を知っていますか?
そこで本記事では、最新のデータをもとに下記内容を解説していきます。
・日本と世界の絶滅危惧種一覧
・絶滅危惧種が減少する原因
・絶滅危惧種が減少する原因
未来の成功を掴むためのヒントをぜひチェックしてください!
- 日本の絶滅危惧種一覧
- Extinct in the Wild(EW)|野生絶滅
- Critically Endangered(CR)|深刻な危機(絶滅寸前)
- Endangered(EN)|絶滅の危機が高い種
- Vulnerable(VU)|危急種(絶滅のリスクあり)
- 世界・エリア別!絶滅危惧種の一覧
- Extinct in the Wild(EW)|野生絶滅
- Critically Endangered(CR)|深刻な危機(絶滅寸前)
- Endangered(EN)|絶滅の危機が高い種
- Vulnerable(VU)|危急種(絶滅のリスクあり)
- 絶滅危惧種が減少する主な原因
- 環境破壊|生息地の喪失と劣化
- 乱獲|密猟と過剰な捕獲
- 気候変動|生態系への深刻な影響
- 絶滅危惧種を守るための国際的・国内の取り組み
- 世界の絶滅危惧種保護活動|IUCN・ワシントン条約とは?
- 日本の絶滅危惧種保護政策|レッドリスト・種の保存法
- 絶滅危惧種保護活動の成功事例
- オランウータンを守るバター石けんづくりの取り組み
- 植林をして森林破壊を抑制する取り組み
- アフリカゾウの保護活動を実現する取り組み
- まとめ|私たちにできることから始めよう
日本の絶滅危惧種一覧

日本には固有の動植物が多く存在しますが、環境の変化や人間の活動によって、多くの種が絶滅の危機に瀕しています。
本章では、日本で確認されている絶滅危惧種を、IUCN(国際自然保護連合)の分類に基づいて紹介します。
どのような生き物が危機にあるのかを知ることが、保護活動の第一歩となります。
|
分類 |
絶滅危惧種の例 |
主な原因 |
|
野生絶滅(EW) |
トキ、キタタキ |
野生では絶滅し、飼育下のみで生存 |
|
絶滅寸前(CR) |
イリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギ、ニホンウナギ |
生息地の破壊、乱獲 |
|
絶滅危機(EN) |
ヤンバルクイナ、アホウドリ、オガサワラオオコウモリ |
生息環境の悪化 |
|
絶滅危機(EN) |
オオサンショウウオ、タンチョウ、ムラサキサギ |
気候変動、外来種の影響 |
Extinct in the Wild(EW)|野生絶滅
野生ではすでに絶滅し、動物園や植物園などの管理下でのみ生存している種が該当します。日本では以下のような生き物が含まれます。
・トキ(Nipponia nippon):かつて日本各地に生息していたが、乱獲や環境破壊で絶滅。現在は人工繁殖により野生復帰が試みられている。
・キタタキ(カワリシロチョウゲンボウ):日本では飼育個体のみ確認されており、野生では絶滅したとされる。
Critically Endangered(CR)|深刻な危機(絶滅寸前)
絶滅のリスクが極めて高い種で、すぐにでも対策を講じなければ絶滅する可能性があります。日本の代表的なCR指定種は以下の通りです。
・イリオモテヤマネコ(Prionailurus bengalensis iriomotensis):
沖縄県西表島のみに生息する固有種。生息地の開発により個体数は減少し、推定100頭程度とされる。
・アマミノクロウサギ(Pentalagus furnessi):
奄美大島・徳之島のみに生息する原始的なウサギ。森林伐採や外来種の影響で個体数が減少。
・ニホンウナギ(Anguilla japonica):
かつては一般的だったが、乱獲や生息環境の悪化により個体数が激減。
Endangered(EN)|絶滅の危機が高い種
比較的多くの個体が残るものの、生息環境の悪化などにより近い将来に絶滅の可能性がある種が分類されます。
・ヤンバルクイナ(Gallirallus okinawae):
沖縄本島北部のみに生息する飛べない鳥。交通事故や野生動物による捕食で個体数が減少。
・アホウドリ(Phoebastria albatrus):
羽毛目的の乱獲により激減。現在は保護活動が進み、個体数は回復傾向。
・オガサワラオオコウモリ(Pteropus pselaphon):
小笠原諸島に生息する大型のコウモリ。森林伐採や天敵の影響で個体数が減少。
Vulnerable(VU)|危急種(絶滅のリスクあり)
個体数は一定数いるものの、生息環境の悪化などで将来的に絶滅の危険がある種が含まれます。
・オオサンショウウオ(Andrias japonicus):
日本固有の両生類で、河川の開発により生息環境が縮小。
・タンチョウ(Grus japonensis):
北海道に生息する美しい鳥。かつて乱獲により激減したが、保護活動により個体数は回復しつつある。
・ムラサキサギ(Ardea purpurea):
日本では一部の湿地帯でのみ確認される。開発による生息地の減少が課題。
日本の絶滅危惧種の現状を知ることは、これらの生き物を守るために私たちができることを考えるきっかけになります。次に、世界に目を向け、各地域でどのような生き物が絶滅の危機に瀕しているのかを見ていきましょう。
世界・エリア別!絶滅危惧種の一覧

地球上では、さまざまな生態系に属する動植物が絶滅の危機に瀕しています。
生息地域によって環境問題や人間活動の影響が異なるため、絶滅危惧種の種類や危機の度合いも変わります。
本章では、IUCN(国際自然保護連合)の分類に基づき、世界各地の絶滅危惧種を紹介します。
どの地域でどんな生物が危機に瀕しているのかを知ることは、保護活動を考えるうえで重要な一歩となります。
Extinct in the Wild(EW)|野生絶滅
野生ではすでに絶滅し、動物園や植物園などの管理下でのみ生存している種が該当します。
・ピンタゾウガメ(Chelonoidis abingdonii)|ガラパゴス諸島
「ロンサム・ジョージ」の名で知られる最後の個体が2012年に死亡し、事実上絶滅。人工繁殖による復活が模索されている。
・スキミアナ・パンダナス(Pandanus skimmianus)|モーリシャス
かつてモーリシャス島の森林に生息していたが、開発や外来種の影響で野生では絶滅。
・チャイニーズリバー・ドルフィン(Lipotes vexillifer)|中国・長江
長江に生息していた淡水イルカ。環境汚染や乱獲により2006年に野生絶滅と認定された。
Critically Endangered(CR)|深刻な危機(絶滅寸前)
すぐにでも保護対策を講じなければ、近い将来に絶滅するリスクが極めて高い種が該当します。
・スマトラトラ(Panthera tigris sumatrae)|インドネシア・スマトラ島
伐採による森林破壊と密猟により、野生個体はわずか400頭以下と推定される。
・アムールヒョウ(Panthera pardus orientalis)|ロシア・中国国境地域
世界に100頭以下しか生息せず、森林伐採や密猟が主な脅威。保護区の拡大が進められている。
・ヤンバルテナガコガネ(Cheirotonus jambar)|沖縄・やんばる地域
世界最大級の甲虫の一種で、日本の固有種。森林開発や気候変動の影響を受け、個体数が激減。
Endangered(EN)|絶滅の危機が高い種
比較的多くの個体が残るものの、生息環境の悪化などで絶滅の可能性が高い種が含まれます。
・マウンテンゴリラ(Gorilla beringei beringei)|アフリカ・コンゴ盆地
密猟や森林伐採により生息地が減少。保護活動の成果で個体数は増加傾向にあるが、依然として脅威に直面している。
・アジアゾウ(Elephas maximus)|東南アジア
生息地の縮小と象牙目的の密猟が原因で、個体数が減少。特にスマトラやボルネオでは深刻。
・ボルネオオランウータン(Pongo pygmaeus)|インドネシア・ボルネオ島
森林伐採とパーム油の生産による環境破壊により、過去100年間で個体数が半減。
Vulnerable(VU)|危急種(絶滅のリスクあり)
現在の個体数は一定数いるものの、将来的に絶滅の危険がある種です。
・ホッキョクグマ(Ursus maritimus)|北極圏
気候変動による海氷の減少で狩りが困難になり、個体数が減少。
・アフリカライオン(Panthera leo)|サハラ以南アフリカ
人間との衝突や生息地の縮小により、個体数が減少。特に西アフリカでは深刻な状況。
・ジンベエザメ(Rhincodon typus)|熱帯・温帯の海域
乱獲と生息環境の悪化により、世界的に個体数が減少。
このように、世界中で多くの動植物が絶滅の危機に直面しています。
それでは、なぜこれほど多くの生物が減少しているのか、次にその主な原因を詳しく見ていきましょう。
絶滅危惧種が減少する主な原因

世界中で多くの動植物が絶滅の危機に瀕している背景には、いくつかの主要な原因があります。
環境の変化や人間の活動が生態系に大きな影響を与え、特定の種の生存を脅かしているのです。
本章では、絶滅危惧種が減少する主な要因について解説します。
|
主な原因 |
具体例 |
影響を受ける種 |
|
環境破壊 |
森林伐採、湿地の開発 |
オランウータン、アホウドリ |
|
乱獲 |
密猟、違法取引 |
アフリカゾウ、スマトラトラ |
|
気候変動 |
海氷の減少、海洋温暖化 |
ホッキョクグマ、ジンベエザメ |
環境破壊|生息地の喪失と劣化
開発や農地拡大による森林伐採、都市化、工業化などにより、多くの生物の生息地が急速に失われています。
・熱帯雨林の消失:
アマゾンや東南アジアでは、農業やパーム油生産のために森林が大規模に伐採され、オランウータンやトラの生息地が減少しています。
・湿地の埋め立て:
日本国内でも、都市開発や河川改修によって湿地帯が減少し、水鳥や淡水魚の生息環境が失われています。
・海洋環境の悪化:
プラスチックごみや海洋汚染によって、ウミガメやクジラなどの海洋生物が危険にさらされています。
乱獲|密猟と過剰な捕獲
人間による過剰な捕獲や密猟も、絶滅危惧種の減少を加速させる大きな要因です。
・象牙や毛皮の密猟:
アフリカゾウやトラは、象牙や毛皮を目的とした違法な狩猟により個体数が激減しています。
・食用・薬用目的の捕獲:
ウナギやサメなどは食材として乱獲され、個体数が減少。アジアでは伝統医薬品の原料として珍しい動物が狩猟されるケースも。
・ペット・観賞用の違法取引:
珍しい鳥類や爬虫類がペット市場で高値で取引され、野生から持ち出されることが多くなっています。
気候変動|生態系への深刻な影響
地球温暖化は、生物の生息環境を大きく変化させ、多くの種の存続を脅かしています。
・気温上昇と氷の減少:
ホッキョクグマは、氷の上で狩りをするため、温暖化による海氷の減少が生存を直接的に脅かしています。
・海水温の上昇と酸性化:
サンゴ礁の白化現象は、海水温の上昇やCO₂濃度の上昇が原因で、多くの海洋生物の生態系が崩れています。
・異常気象の増加:
台風や干ばつの頻発が、生態系に大きな影響を与え、森林や湿地の動植物の生存を難しくしています。
こうした原因により、多くの生き物が絶滅の危機に直面しています。
しかし、世界各国では絶滅危惧種を守るための保護活動が行われています。
次の章では、国際的な取り組みや日本国内の政策について詳しく解説します。
絶滅危惧種を守るための国際的・国内の取り組み

多くの動植物が絶滅の危機に瀕している中、世界各国ではその保護と回復を目指したさまざまな取り組みが進められています。
国際条約の制定や各国の法律の整備、さらには企業や市民による保護活動など、幅広い対策が講じられています。
本章では、絶滅危惧種を守るための国際的な枠組みと、日本国内の取り組みについて解説します。
|
取り組み |
主な内容 |
対象種 |
|
IUCNレッドリスト |
世界の絶滅危惧種を分類し、保護の指針を示す |
すべての絶滅危惧種 |
|
ワシントン条約(CITES) |
絶滅危惧種の国際取引を規制 |
アフリカゾウ、トラ、ウナギ |
|
種の保存法(日本) |
日本の絶滅危惧種を指定し、保護を強化 |
トキ、イリオモテヤマネコ |
|
国立公園の保全 |
生息地を守るための保護区を設定 |
ヤンバルクイナ、タンチョウ |
世界の絶滅危惧種保護活動|IUCN・ワシントン条約とは?
◆ IUCN(国際自然保護連合)
IUCNは、絶滅危惧種の評価を行い、「レッドリスト」として分類する国際組織です。世界中の動植物の保護状況を評価し、各国政府や研究機関に指針を提供しています。
◆ ワシントン条約(CITES)
ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約)は、希少な動植物の国際取引を規制する条約です。
象牙やトラの毛皮、ウナギやサンゴなど、絶滅の危機にある種の商取引を制限し、保護を進めています。
◆ ユネスコ生物圏保存地域(ユネスコMABプログラム)
ユネスコ(国連教育科学文化機関)が指定する「生物圏保存地域」は、自然保護と地域社会の持続可能な発展を両立させるモデル地域です。
日本でも白山や屋久島などが指定され、環境保護と観光・経済活動の共存を目指しています。
日本の絶滅危惧種保護政策|レッドリスト・種の保存法
◆ 環境省レッドリスト
環境省は、IUCNの基準をもとに、日本国内の絶滅危惧種をリスト化した「レッドリスト」を作成しています。
定期的に更新され、種ごとの危険度や保護の必要性を評価しています。
◆ 種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
1992年に施行されたこの法律では、国内外の希少な動植物を指定し、保護区の設定や商取引の規制を行っています。
具体的には、トキの野生復帰プロジェクトやアマミノクロウサギの保護活動が進められています。
◆ 国立公園や自然保護区の整備
日本では、絶滅危惧種が生息する地域を国立公園や特別保護区に指定し、生態系の保全を進めています。
屋久島、知床、奄美大島などは、世界自然遺産としても認定され、保護活動が強化されています。
国際的・国内の取り組みにより、絶滅危惧種の保護は進められていますが、それでも多くの種が危機に瀕しています。
次の章では、実際に成功した保護活動の事例を紹介し、効果的な取り組みについて詳しく解説します。
絶滅危惧種保護活動の成功事例

絶滅危惧種の保護活動は、世界各地で進められており、実際に成功した事例も数多くあります。
適切な環境保全や生息地の復元、地域住民の協力によって、個体数を回復させた種も存在します。本章では、具体的な成功事例を紹介し、どのような取り組みが効果を上げているのかを見ていきます。
オランウータンを守るバター石けんづくりの取り組み
◇ 対象種:ボルネオオランウータン(Pongo pygmaeus)
◇ 活動地域:インドネシア・ボルネオ島
◇ 課題:パーム油の大規模生産による森林破壊で生息地が減少

〈プロジェクトの詳細〉
■日本初!オランウータンなどの絶滅危惧種を守るバター石けんを作りたい!
■達成金額 ¥924,000
■目標金額 ¥924,000
■支援者数 202人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/trn_project/34825
ボルネオ島のオランウータンは、森林伐採とプランテーション開発により、生息地を失い続けています。
この課題に対し、持続可能な方法で生産されたシアバターを活用した石けん作りが行われています。
これにより、パーム油の消費を減らし、オランウータンの生息地保全につなげる活動が進められています。
植林をして森林破壊を抑制する取り組み
◇ 対象種:スマトラトラ(Panthera tigris sumatrae)、ボルネオオランウータン
◇ 活動地域:インドネシア・東南アジアの熱帯雨林
◇ 課題:森林伐採による生息地の消失

〈プロジェクトの詳細〉
■森林破壊が止まないボルネオ島に植林し、オランウータンに森を返したい!
■達成金額 ¥439,000
■目標金額 ¥439,000
■支援者数 80人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/trn_project/29979
違法伐採やプランテーション開発による森林破壊を食い止めるため、地域住民と協力して植林活動が行われています。
特に、在来種の樹木を植えることで、森林の生態系を再生し、トラやオランウータンが生息できる環境を取り戻すことを目指しています。
アフリカゾウの保護活動を実現する取り組み
◇ 対象種:アフリカゾウ(Loxodonta africana)
◇ 活動地域:アフリカ大陸各地
◇ 課題:象牙目的の密猟と生息地の減少

〈プロジェクトの詳細〉
■アフリカゾウと地域住民に命の危機が…自然との共生を目指して保護活動を実現したい!
■達成金額 ¥3,266,000
■目標金額 ¥1,100,000
■支援者数 266人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/trn_project/59461
アフリカゾウは、象牙の違法取引や生息地の縮小によって深刻な危機にあります。
この問題に対し、現地の保護団体がパトロールや地域住民との協力を強化し、密猟対策を進めています。
また、エコツーリズムを促進することで、ゾウを守りながら地域経済の発展にもつなげる取り組みが行われています。
これらの事例からわかるように、絶滅危惧種を守るためには、 環境保全・地域との連携・持続可能な活動 が重要な要素となります。
私たちにできることから始めよう

絶滅危惧種の現状を知ることで、私たちは自然とのつながりを改めて考えることができます。
野生動物の生息地を守る活動や、持続可能な消費を意識するだけでも、絶滅の危機にある生き物たちを支える一歩になります。
各国の保護活動が成果を上げているように、個人の小さな行動も未来を変える力になります。
今日からできることを考え、自然と共に生きる選択をしてみませんか?あなたの意識が、絶滅危惧種を救う大きな力になります。
クラウドファンディングに興味がある方は、
ぜひ「For Good」で一緒に取り組みましょう!