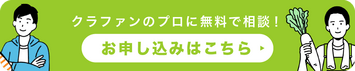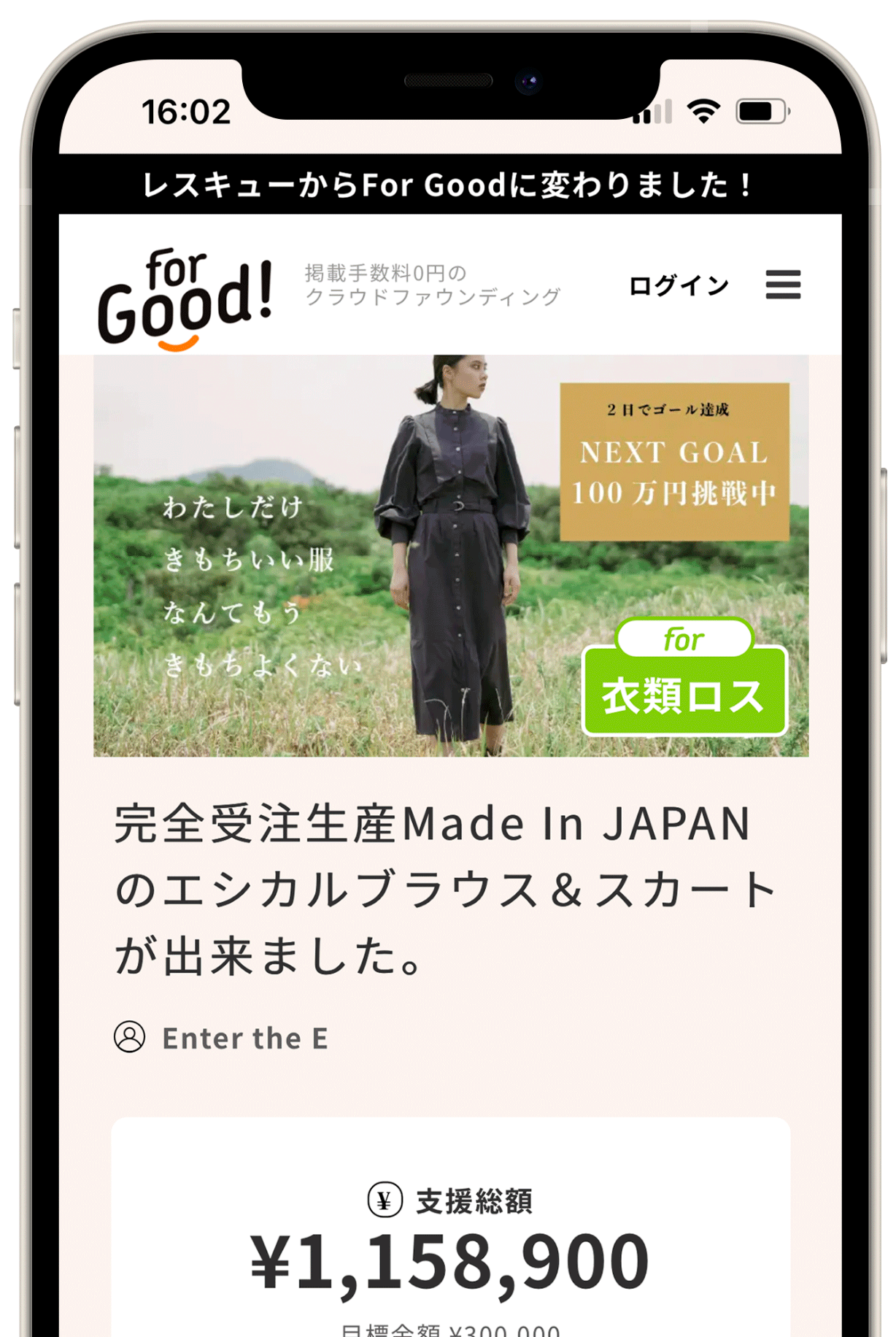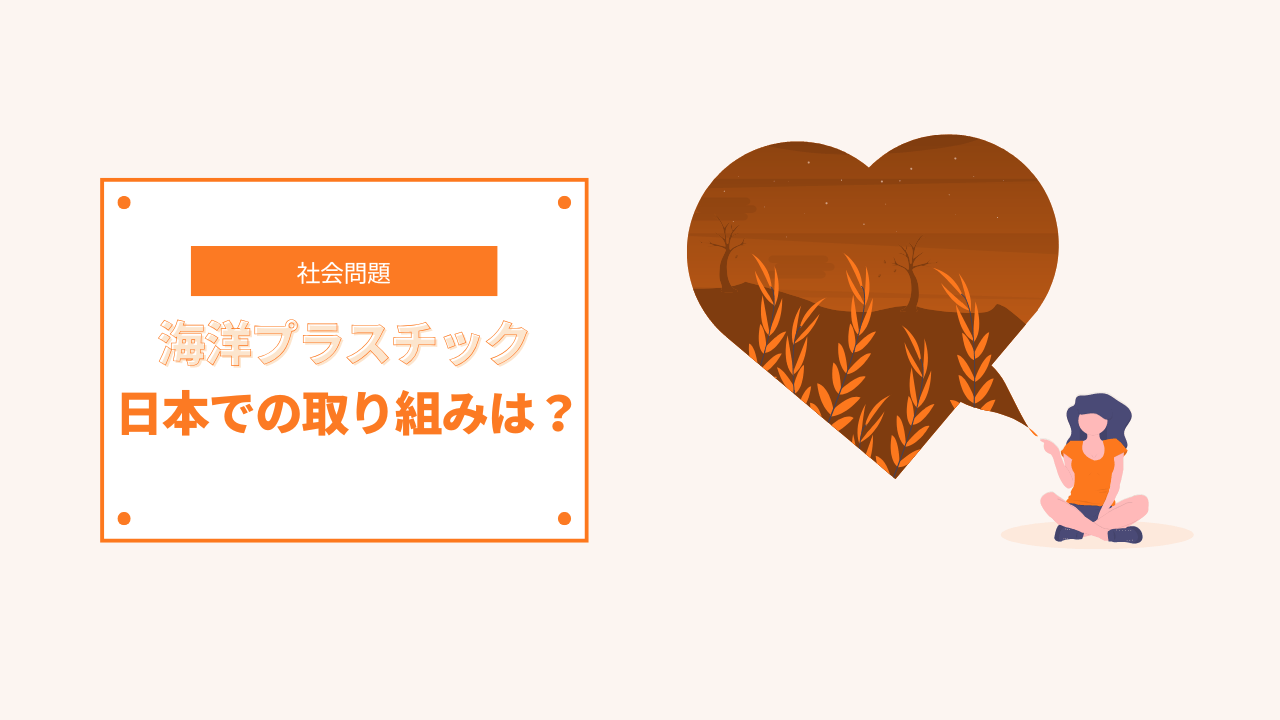
海洋プラスチック問題の日本の取り組み|個人・企業・自治体ができる対策を解説
海洋プラスチック問題は、地球規模で深刻化している環境課題の一つです。
日本でも、政府・企業・自治体がさまざまな対策を進めており、私たち個人の行動も求められています。
そこで本記事では、下記内容をわかりやすく解説していきます。
- 日本の海洋プラスチック対策
- 企業・自治体の具体的施策
- 個人ができる実践方法
今すぐできる身近な取り組みから、社会全体で進む施策まで、海を守るための第一歩を一緒に考えていきましょう。
- 1. 政府の取り組み
- プラスチック資源循環促進法の推進
- 使い捨てプラスチック削減施策の実施
- プラスチックリサイクル強化の推進
- 2. 企業の取り組み
- 事例1|日本コカ・コーラ株式会社
- 事例2|パイロットコーポレーション
- 事例3|花王株式会社
- 事例4|スターバックスコーヒージャパン株式会社
- 3. 自治体の取り組み
- 神奈川県鎌倉市「かまくらプラごみゼロ宣言」
- 京都府亀岡市「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」
- 福岡県「プラスチック資源循環促進事業」
- 4.個人の取り組み事例
- マイバッグ・マイボトルの活用
- 使い捨てプラスチックの代替品の選択
- スーパーやコンビニで「過剰包装」を避ける
- ごみの分別を正しく行い、プラスチックリサイクルの意識
- 地域の清掃活動やビーチクリーンへの参加
- 環境NPO・団体の活動への支援
- 環境問題についてSNSなどを通じた周囲への啓発活動
- 学校・教育機関での環境教育の強化
- 5.データで見る海洋プラスチック問題と日本の現状
- 海洋プラスチック問題とは?
- 日本のプラスチックごみの現状
- 影響と課題
- 未来のために「わたしたちができること」
1. 政府の取り組み

海洋プラスチック問題の解決には、政府の主導による制度整備や政策が欠かせません。
日本では、プラスチックごみの削減や資源循環を促進するため、法律の整備や施策の導入が進められています。
プラスチック資源循環促進法の推進
2022年に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」は、プラスチックごみの排出抑制と資源循環を強化するために制定されました。
この法律は、製造・販売・消費・廃棄の各段階での環境負荷低減を促すものです。
■主なポイント
・製品設計の環境配慮:リサイクルしやすい素材の使用を推奨
・事業者の責任強化:プラスチック製品の回収・再資源化の義務化
・自治体との連携強化:ごみの分別・リサイクル推進
この法律により、企業は環境負荷の少ない製品設計を求められ、消費者もリサイクルの重要性を再認識するきっかけとなっています。
使い捨てプラスチック削減施策の実施
プラスチックごみの発生を抑えるため、日本政府は使い捨てプラスチック製品の削減を推進しています。
特に、コンビニ・飲食店・ホテルなどで提供されるプラスチック製のスプーン・フォーク・ストローの使用を減らす施策が進められています。
■具体的な対策
・2022年4月から、特定の使い捨てプラスチック製品(カトラリー類・ハンガーなど)の提供削減が事業者に義務化
・企業による有料化や、バイオプラスチック・紙製品などの代替素材の活用を奨励
・消費者への意識啓発として、マイボトル・マイカトラリーの普及促進
これにより、事業者はプラスチックの使用量を削減する努力を求められ、消費者も環境に配慮した選択をする機会が増えています。
プラスチックリサイクル強化の推進
プラスチックごみの適切な処理と再利用を促進するため、日本政府はリサイクル体制の強化を進めています。
従来の焼却処理に依存せず、より資源としての再利用を促す取り組みが進んでいます。
■主な施策
・自治体と連携したリサイクル強化:分別回収の徹底とリサイクル施設の整備
・拡大生産者責任(EPR)の導入:企業が製品のリサイクルまで責任を持つ制度の強化
・ケミカルリサイクルの推進:プラスチックを分解し、再び原料として活用する技術の発展
これらの施策により、プラスチックの資源循環率を高め、廃棄物の削減を目指しています。
2. 企業の取り組み

事例1|日本コカ・コーラ株式会社
日本コカ・コーラは、プラスチックボトルのリサイクル推進に積極的に取り組んでいます。
・100%リサイクルPETボトルの導入:一部製品で完全リサイクルボトルを採用し、新たな石油由来プラスチックの使用削減
・ラベルレス製品の拡大:ペットボトル製品のラベルを省き、資源削減とリサイクルの効率化を推進
・ボトルtoボトルリサイクル:使用済みペットボトルを回収し、新たなペットボトルへと再生する取り組みを強化
これにより、プラスチックごみの排出を減らし、循環型社会の実現を目指しています。
事例2|パイロットコーポレーション
文房具メーカーのパイロットコーポレーションは、海洋プラスチックを活用した製品開発を行っています。
・リサイクル材を使用した環境にやさしい製品:製品を使い捨てにせず、廃棄物を削減する製品の開発を促進
・リサイクル可能な筆記具の開発:カートリッジ式の製品を増やし、使い捨てのプラスチック削減に貢献
これらの施策を通じて、身近な文房具から環境負荷を減らす取り組みを進めています。
事例3|花王株式会社
花王は、日用品メーカーとしてプラスチック包装の削減や環境配慮型製品の開発を進めています。
・つめかえ・エコパックの普及:ボトル容器の再利用を促進し、使い捨てプラスチック削減
・植物由来の生分解性プラスチック開発:洗剤やスキンケア製品のパッケージを環境に優しい素材へ移行
・マイクロプラスチックビーズの廃止:スクラブ入り洗顔料などに使われていたプラスチック粒子を天然成分に置き換え
これらの取り組みにより、日常生活におけるプラスチック削減を進めています。
事例4|スターバックスコーヒージャパン株式会社
スターバックスは、飲食業界でのプラスチック削減に積極的に取り組んでいます。
・プラスチックストローの廃止:紙製ストローやリユーザブルカップの導入
・リユーザブルカップの普及促進:マイカップ利用時の割引制度を実施
・店内飲食用カップの再利用強化:プラスチックの使い捨てを減らし、リサイクルの促進
スターバックスは、顧客の意識改革を促しながら、業界全体に影響を与える取り組みを進めています。
3. 自治体の取り組み

自治体ごとの環境施策は、その地域の特性や課題に応じた対策が取られ、市民の行動を変える大きな役割を果たしています。
本章では、プラスチックごみの削減に向けた先進的な自治体の取り組みとして、神奈川県鎌倉市、京都府亀岡市、福岡県の事例を紹介します。
神奈川県鎌倉市「かまくらプラごみゼロ宣言」
鎌倉市は2018年に「かまくらプラごみゼロ宣言」を発表し、市全体でプラスチックごみの削減に取り組んでいます。
観光地として多くの人が訪れる鎌倉では、ごみの発生量が多く、市民と観光客が協力して環境負荷を減らすことが重要視されています
■主な施策
・公共施設でのペットボトル販売の廃止:市庁舎や公立学校などでペットボトル飲料の販売を中止し、代わりに給水スポットを設置
・飲食店でのプラスチック製ストロー・カトラリーの削減:市内の店舗と協力し、紙製ストローや木製カトラリーの導入を推進
・市民、観光客向けの啓発活動:マイボトルやエコバッグの使用促進キャンペーンを展開
鎌倉市の取り組みは、市民だけでなく観光客にも環境配慮を促す点が特徴的です。
京都府亀岡市「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」
京都府亀岡市は、2018年に「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を発表し、使い捨てプラスチックごみの削減に積極的に取り組んでいます。
特に、自治体として全国初となるレジ袋の全面禁止条例を施行し、大きな注目を集めました。
■主な施策
・レジ袋の提供禁止(2020年施行):市内の全ての事業者に対し、プラスチック製レジ袋の配布を禁止
・エコバッグの推奨とマイボトル文化の普及:市独自のデザインのエコバッグや、給水スポットの設置を推進
・地域の環境教育の強化:学校や地域イベントでプラスチックごみ削減に関するワークショップを開催
亀岡市の取り組みは、条例制定により市全体で意識を変え、持続可能な行動を促す点が特徴です。
福岡県「プラスチック資源循環促進事業」
福岡県は、海洋プラスチックごみの流出を防ぐため、「プラスチック資源循環促進事業」を実施し、県全体でのごみ削減と資源循環を推進しています。
■主な施策
・「ふくおかプラごみ削減応援サイト」の開設:県民や事業者向けにプラスチックごみ削減の情報を発信
・企業・自治体連携のリサイクル促進:リサイクル可能なプラスチックごみの分別強化と回収体制の整備
・啓発イベントやワークショップの開催:県内の学校や企業と連携し、プラスチック削減の意識向上を図る
福岡県の取り組みは、情報発信と地域の連携によって、広範囲での意識変革を促している点が特徴です。
4.個人の取り組み事例

海洋プラスチック問題の解決には、政府や企業の取り組みだけでなく、個人レベルでの意識と行動が不可欠です。
日々の生活の中で少しの工夫をするだけで、プラスチックごみの削減につながります。
本章では、個人が実践できる具体的な取り組みを紹介します。
マイバッグ・マイボトルの活用
レジ袋やペットボトルは、使い捨てプラスチックごみの大きな原因となります。マイバッグやマイボトルを持ち歩くことで、不要なプラスチックを削減できます。
・レジ袋を使わない習慣:コンパクトに折りたためるエコバッグを持ち歩く
・ペットボトル飲料を減らす:マイボトルを活用し、給水スポットを利用する
・マイカトラリーの導入:外食やテイクアウト時に、プラスチック製スプーン・フォークを使わず、持参する

〈プロジェクトの詳細〉
■社会を変えていく「3.5%」の人たちが持つマイボトルをつくりたい
■達成金額 ¥300,500
■目標金額 ¥300,000
■支援者数 89人
➡ 詳細を見るhttps://for-good.net/trn_project/69966
使い捨てプラスチックの代替品の選択
プラスチック製品の代わりに、環境に優しい代替品を選ぶことも重要です。
・紙製ストロー・竹製カトラリーを利用
・リユース可能な食品容器を活用(シリコン製保存容器、蜜蝋ラップなど)
・洗剤やシャンプーの詰め替え製品を選ぶ
企業も代替素材の開発を進めており、消費者が積極的に選択することで市場全体の変化につながります。
スーパーやコンビニで「過剰包装」を避ける
食品や日用品の多くがプラスチック包装されています。
消費者の選択によって、無駄なプラスチックごみを削減できます。
・野菜や果物はなるべく裸売りの商品を選ぶ
・個包装が少ない商品を選ぶ(例えば、大袋のスナック菓子を選ぶなど)
・簡易包装の商品を扱う店舗を利用する(ゼロウェイストショップの活用)
ごみの分別を正しく行い、プラスチックリサイクルの意識
日本のプラスチックごみの多くは焼却処分されますが、正しい分別でリサイクル率を向上させることが可能です。
・各自治体のルールに沿った分別を徹底する
・リサイクルマークのある製品は回収ボックスへ
・ペットボトルはラベルとキャップを外し、正しく処理する
正しくリサイクルを行うことで、プラスチックが資源として活用されやすくなります。
地域の清掃活動やビーチクリーンへの参加
海洋プラスチックごみの多くは、陸地から流れ出たものです。
定期的な清掃活動に参加することで、直接的なごみ削減に貢献できます。
・地域で開催される清掃イベントに参加
・ビーチクリーンや河川清掃に協力
・自分の住む街の環境を守る意識を持つ
一人での活動も可能ですが、ボランティア団体や自治体と連携すると、より効果的な取り組みができます。

〈プロジェクトの詳細〉
■離島の海ごみ問題解決のために社会的ムーブメントを起こしたい!
■達成金額 ¥1,068,500
■目標金額 ¥1,000,000
■支援者数 157人
➡ 詳細を見るhttps://for-good.net/project/1001343
環境NPO・団体の活動への支援
海洋プラスチック問題に取り組むNPOや団体を支援することも、重要なアクションの一つです。
・募金やクラウドファンディングで支援
・NPOのイベントやワークショップに参加
・プラスチック削減に取り組む企業の商品を積極的に購入
環境活動を行う団体の存在を知り、自分ができる範囲でサポートすることが社会全体の意識向上につながります。
環境問題についてSNSなどを通じた周囲への啓発活動
SNSやブログなどを活用し、海洋プラスチック問題への関心を広めることも有効です。
・自分が実践しているプラスチック削減の方法を発信
・環境問題について学んだことをシェア
・企業や自治体の取り組みを紹介し、賛同者を増やす
個人の発信が、周囲の人々の行動変容につながる可能性があります。

〈プロジェクトの詳細〉
■【環境問題をもっと身近に!】地球もみんなも元気になるキッチンカー事業を始めたい!
■達成金額 ¥2,419,500
■目標金額 ¥1,200,000
■支援者数 345人
➡ 詳細を見るhttps://for-good.net/trn_project/59512
学校・教育機関で環境教育の強化
未来世代の環境意識を高めるためには、学校での環境教育も不可欠です。
・授業でSDGsや海洋ごみ問題を扱う
・体験型の学習(清掃活動やリサイクル工場見学)を取り入れる
・学生同士で話し合い、行動を促す機会を設ける
学校教育を通じて、より多くの子どもたちが環境問題への関心を持ち、将来的な社会変革につながる可能性があります。

〈プロジェクトの詳細〉
■「かわいい」を通して鹿児島の子どもたちに海洋プラスチック問題について知ってもらいたい!
■達成金額 ¥151,600
■目標金額 ¥100,000
■支援者数 79人
➡ 詳細を見るhttps://for-good.net/trn_project/27168
5.データで見る海洋プラスチック問題と日本の現状

海洋プラスチック問題を理解し、効果的な対策を考えるには、現状のデータを正しく知ることが重要です。
本章では、海洋プラスチック問題の概要、日本のプラスチックごみの現状、そしてそれがもたらす影響と課題について詳しく解説します。
海洋プラスチック問題とは?
海洋プラスチック問題とは、プラスチック製品が適切に処理されずに海洋に流出し、環境や生態系に悪影響を及ぼす現象を指します。
プラスチックは自然分解されにくく、海洋に蓄積されると長期間残存します。
特に、微細なプラスチック粒子であるマイクロプラスチックは、生物の体内に取り込まれ、生態系全体に影響を及ぼすことが懸念されています。
■主な発生源
・陸上からの流出(河川・雨水を通じて海に流入)
・漁業や海洋活動で発生するごみ(漁網、プラスチック容器など)
・観光地や海岸でのポイ捨て
日本のプラスチックごみの現状
日本は、プラスチック製品の大量生産・大量消費社会として知られています。
その結果、プラスチックごみの排出量も多く、海洋汚染の一因となっています。
環境省の報告によれば、日本の海岸には大量のプラスチックごみが漂着しており、その多くが使い捨てプラスチック製品です。
影響と課題
海洋プラスチックごみは、生態系や人間社会に多大な影響を及ぼします。
海洋生物がプラスチックごみを誤食したり、絡まったりすることで、死亡するケースが報告されています。
また、プラスチックに含まれる有害物質が生物濃縮され、人間の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
さらに、観光業や漁業への経済的損失も無視できません。これらの課題に対処するためには、プラスチックごみの削減、適切な廃棄物管理、そしてリサイクルの推進が必要です。
① 生態系への影響
・ウミガメや海鳥の誤飲・絡まり
・魚介類へのマイクロプラスチックの蓄積
・サンゴ礁の劣化(プラスチックが付着し、病気を引き起こす)
② 人体への影響
・魚や貝を介してマイクロプラスチックを摂取
・プラスチックに含まれる有害物質が体内に蓄積する可能性
③ 経済への影響
漁業被害:プラスチックごみによる網の破損、魚の汚染
観光業への打撃:ごみが漂着することで観光地の景観悪化
未来のために「わたしたちができること」

海洋プラスチック問題の解決には、私たち一人ひとりの行動が欠かせません。
「使わない」「選ぶ」「広める」「行動する」 という4つの視点を意識するだけで、日常から環境負荷を減らすことができます。
マイバッグやマイボトルの活用、使い捨てプラスチックの削減、リサイクルの徹底、清掃活動への参加など、小さな一歩が未来の環境を守る力になります。
また、環境に配慮した企業の商品を選んだり、SNSで発信したりすることも、社会全体の意識を変える大切なアクションです。
「誰かがやる」ではなく、「私たちみんなでやる」 という意識を持ち、できることから始めてみましょう。
私たちの小さな選択が、次世代に美しい海を残す大きな一歩になります。
クラウドファンディングに興味がある方は、
ぜひ「For Good」で一緒に取り組みましょう!