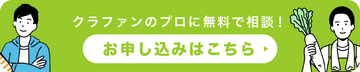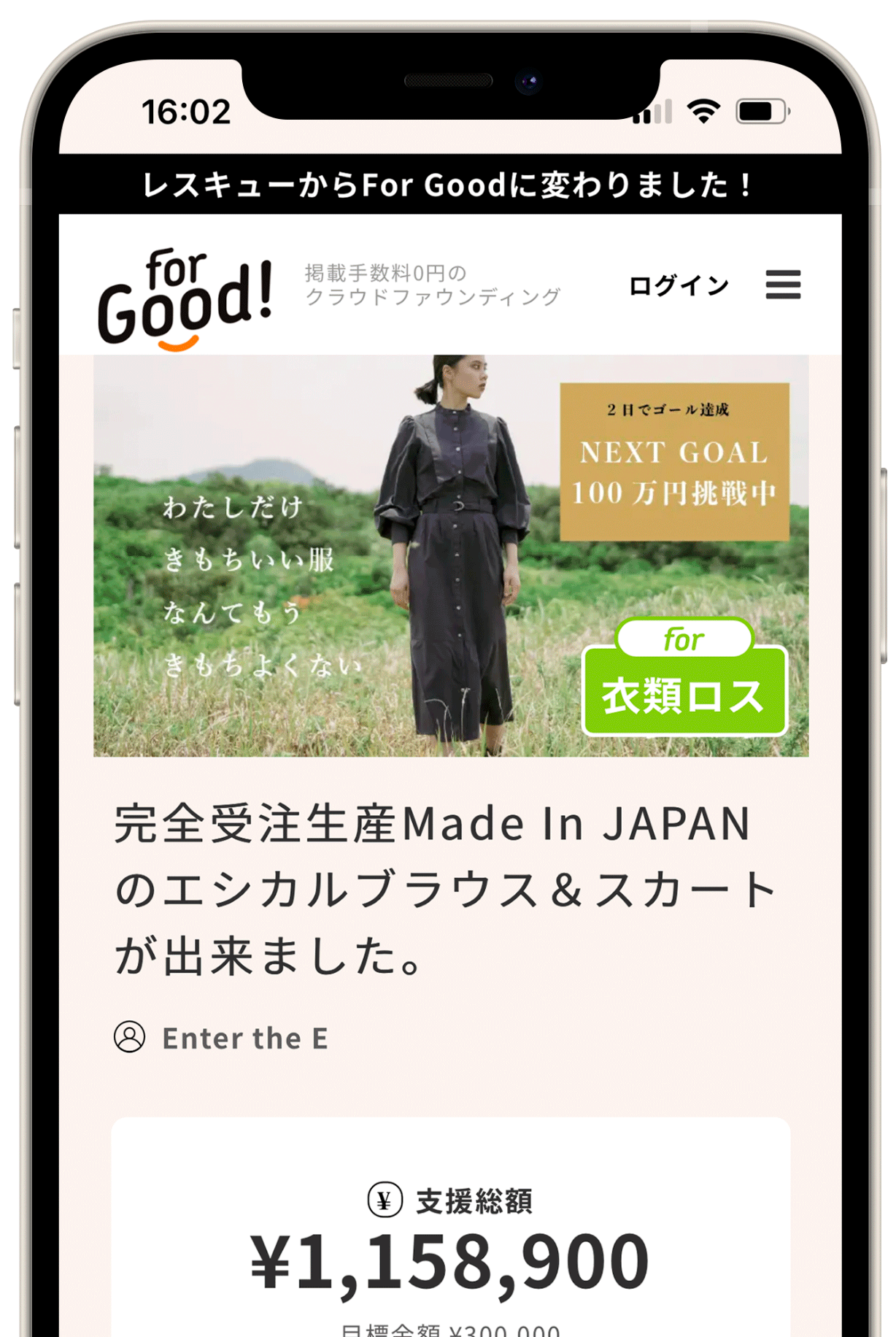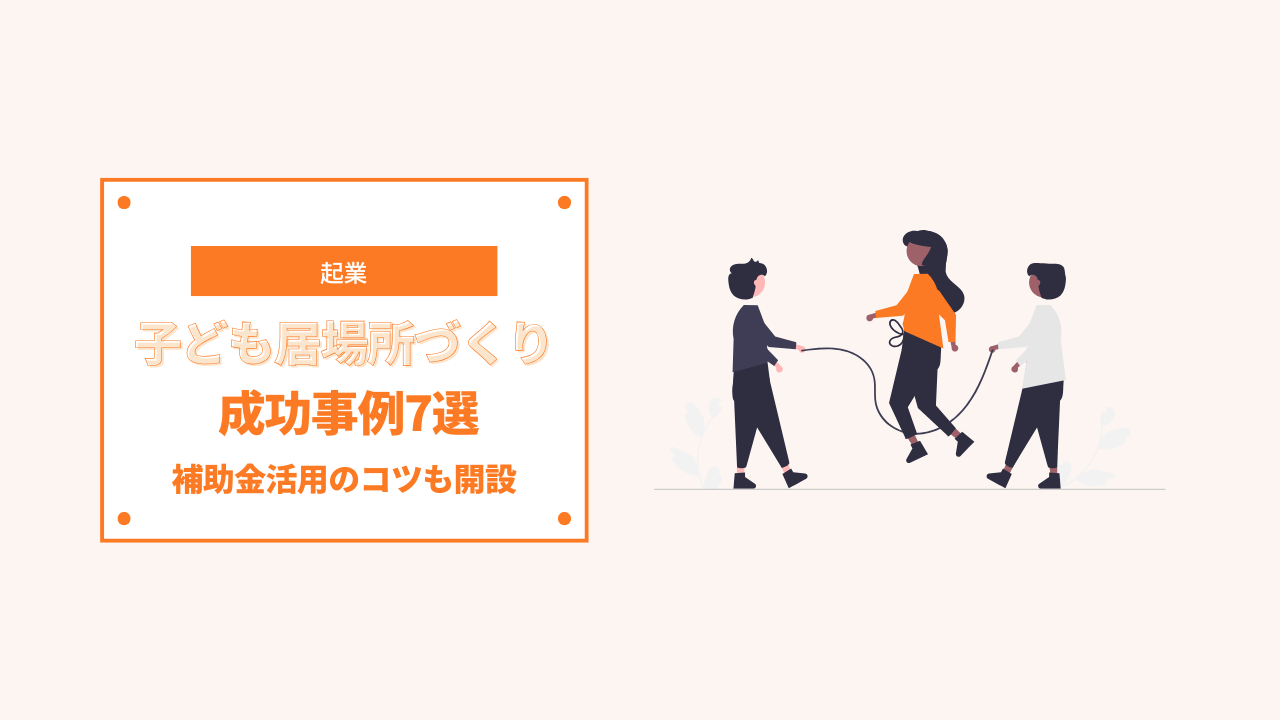
【成功事例から学ぶ】子どもの居場所づくり完全ガイド|補助金活用のコツも解説
子どもたちが安心して過ごせる「居場所」は、成長を支える重要な役割を果たします。しかし、効果的な居場所をつくるには何から始めればいいのか、どのような支援制度を活用できるのか、多くの人が悩むところです。
そこで本記事では、下記内容を解説していきます。
・居場所づくりの成功事例紹介
・補助金・助成金の活用法解説
・運営ノウハウと注意点の共有
子どもたちの未来を共に支えるための第一歩を、この完全ガイドで踏み出してみませんか?
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
- 【当社事例】子どもの居場所づくりの成功事例
- 清流沿いの廃校で遊べる・泊まれる学校を作った事例
- 空き物件を子どもの居場所に再生した事例
- 被災した子どもたちに移動式あそび場を作った事例
- 不登校に悩む生徒とママに集いの場を作った事例
- 多様な子どもたちがのびのび過ごせる場所を作った事例
- 多様な学び場・居場所マップを作った事例
- 子どもたちに第3の居場所を提供した事例
- 居場所づくりに活用できる補助金・助成金
- 国の補助金・助成金
- 地方自治体の補助金・助成金
- 民間団体の助成金
- クラウドファンディングの活用
- 申請のコツ
- 具体的な居場所づくりの手順
- ニーズの把握
- 目的の設定
- 計画の立案
- 場所の確保
- 運営開始
- 効果検証と改善
- 運営上の注意点と課題への対応策
- まとめ:子どもたちの未来のために
- よくある質問
【当社事例】子どもの居場所づくりの成功事例
清流沿いの廃校で遊べる・泊まれる学校を作った事例

〈プロジェクトの詳細〉
■【子どもに自然の豊さを】浜松の清流沿いの廃校で遊べる・泊まれる学校をつくりたい!
■達成金額
¥5,538,000
■目標金額
¥3,000,000
■支援者数
95人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000463
このプロジェクト「atago feels」は、子どもたちが自然の中でのびのびと遊び、心身の成長を促す居場所を提供することを目的としています。浜松市天竜区の廃校を活用し、自然体験を通じて子どもたちが地域とつながる環境を整備します。
日常から離れ、自然の中で自由に過ごせる場を提供することで、子どもたちの成長と安心感を支える新しい居場所づくりを進めています。
空き物件を子どもの居場所に再生した事例

〈プロジェクトの詳細〉
■【伊豆下田発】空き物件を『交流・共創・挑戦の場』『こどもの居場所』に再生させる!
■達成金額
¥2,685,500
■目標金額
¥2,000,000
■支援者数
188人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000632
「風まち下田」は、伊豆下田の空き物件を活用し、地域内外の人々が集う交流・共創・挑戦の場、そして子どもたちの居場所を提供するプロジェクトです。
この施設では、コミュニティスペースやプレイルーム、デッキなどを備え、地域の子どもたちが学びや遊びを通じて成長できる環境を整えています。
また、シェアカフェや宿泊施設も併設し、地域外からの訪問者との交流を促進することで、地域活性化と関係人口の増加を目指しています。
被災した子どもたちに移動式あそび場を作った事例

〈プロジェクトの詳細〉
■能登半島地震で被災した子どもたちを移動式あそび場「プレイカー」で笑顔にしたい!
■達成金額
¥2,579,000
■目標金額
¥2,000,000
■支援者数
258人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000580
「移動式あそび場全国ネットワーク」は、2024年1月1日に発生した能登半島地震で被災した子どもたちのため、移動式あそび場「プレイカー」を活用して笑顔を取り戻すプロジェクトを実施しました。
この取り組みでは、専門の人材が子どもたちのニーズに合わせた遊びの支援とコミュニティの構築を行い、地域の活動団体や行政機関と連携して効果的な支援体制を整えました。
クラウドファンディングを通じて目標金額を達成し、被災地の子どもたちに安心して遊べる場を提供することで、心のケアと地域の復興に貢献しました。
不登校に悩む生徒とママに集いの場を作った事例

〈プロジェクトの詳細〉
■不登校で悩む生徒とママが家庭円満!笑顔広がるフリースクールと集いの場を作りたい!
■達成金額
¥1,150,000
■目標金額
¥1,000,000
■支援者数
5人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1001015
「miniひまわり」は、神奈川県茅ヶ崎市のJR相模線香川駅近くに位置するフリースクールと集いの場です。不登校で悩む生徒とその保護者を支援することを目的とし、心理カウンセラーである女性が運営しています。
この施設では、就業体験を通じて子どもたちの自立を促し、保護者同士の交流やカウンセリングを提供することで、家庭全体の円満と笑顔の広がりを目指しています。
多様な子どもたちがのびのび過ごせる場所を作った事例

〈プロジェクトの詳細〉
■新潟県湯沢町で、多様な子どもたちが違いを楽しみ、のびのび過ごせる居場所をつくる!
■達成金額
¥605,500
■目標金額
¥335,000
■支援者数
80人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/trn_project/4847
こちらは、新潟県湯沢町で、多様な子どもたちが違いを楽しみ、のびのび過ごせる居場所をつくるプロジェクトです。
この取り組みでは、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供する施設「ここいろスペース」を開設し、発達障害やグレーゾーンの子どもたちが安心して学び、成長できる環境を整えています。
クラウドファンディングを通じて目標金額を達成し、施設の改修やICT機器の導入を進め、子どもたちの自尊心を高める支援を行っています。
多様な学び場・居場所マップを作った事例

〈プロジェクトの詳細〉
■困難を抱える子ども達のために、「栃木県多様な学び場・居場所マップ」を作成したい!
■達成金額
¥592,000
■目標金額
¥550,000
■支援者数
89人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/trn_project/11327
「学校以外の場を共につくる・とちぎネットワーク」は、栃木県内の不登校の子どもたちが安心して学べる居場所を提供するため、支援団体の情報を集約した「栃木県多様な学び場・居場所マップ」を作成しました。
このマップは、フリースクールや親の会、夜間中学など約30の団体情報を掲載し、子どもや保護者が適切な支援先を迅速に見つけられるよう支援しています。
クラウドファンディングを通じて目標金額を達成し、マップの作成・配布を実現しました。
子どもたちに第3の居場所を提供した事例

〈プロジェクトの詳細〉
■枚方市に子どもたちの居場所を作りたい!
■達成金額
¥567,000
■目標金額
¥150,000
■支援者数
55人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/trn_project/61821
NPO団体amoの代表の女性は、枚方市に子どもたちのための居場所を提供するプロジェクトを立ち上げました。
この取り組みは、家庭環境や経済的な理由で孤立しがちな子どもたちに、学校や家庭以外の「第3の居場所」を提供することを目的としています。
具体的には、子ども食堂や移動子ども食堂を通じて、子どもたちが安心して過ごせる場を提供し、地域全体で子どもたちを見守り支える環境を構築することを目指しています。
居場所づくりに活用できる補助金・助成金

居場所づくりを進める際、資金確保は避けて通れない課題です。ここでは、国や地方自治体、民間団体が提供する補助金・助成金の特徴と、さらにクラウドファンディングの活用方法についてご紹介します。
国の補助金・助成金
国の補助金は、地域の子ども支援を目的とした大規模なプロジェクト向けのものが多いのが特徴です。例えば、文部科学省や厚生労働省が提供する「地域子ども応援プロジェクト」では、子どもの居場所づくりや成長支援に対して継続的な資金を得ることができます。
地方自治体の補助金・助成金
地方自治体の補助金は、地域密着型の支援に特化しています。自治体ごとに制度が異なりますが、地域の課題に応じた柔軟な支援を受けることが可能です。申請の際には、自治体が提供する情報をこまめにチェックしましょう。
民間団体の助成金
NPOや企業の助成金は、特定のテーマや対象にフォーカスしているものが多く、地域限定や小規模プロジェクトにも適しています。たとえば「子どもの未来応援基金」は、子どもの教育や福祉支援を目的とした事業を幅広くサポートしています。
クラウドファンディングの活用
補助金や助成金と並行して、クラウドファンディングの活用もおすすめです。居場所づくりへの共感を広く募ることで、地域住民や支援者から直接資金を集めることができます。
資金面のサポートだけでなく、プロジェクトの認知度向上や支援者ネットワークの構築にも役立ちます。For Goodのようなプラットフォームを活用すれば、初めてのプロジェクトでも安心してスタートできます。
申請のコツ
補助金や助成金の申請を成功させるためには、申請書の書き方が重要です。以下のポイントを押さえましょう。
・事業計画の具体性:具体的な数値や目標を盛り込む
・必要性の明確化:地域や子どもの課題を具体的に示す
・期待効果の強調:事業がもたらす成果を明確に記述
・審査員視点を意識:簡潔で説得力のある表現を心がける
💡クラウドファンディングで資金調達する方法を解説!
具体的な居場所づくりの手順

子どもの居場所を成功させるには、明確な手順を踏むことが重要です。以下では、各ステップで押さえておくべきポイントを具体的に解説します。
1. ニーズの把握
まずは、地域の子どもたちがどのような課題を抱えているのかを把握することが出発点です。適切なニーズを把握することで、より効果的な居場所づくりが可能になります。
2. 目的の設定
居場所の目的を明確にすることは、活動内容や方向性を決定するうえで欠かせません。以下のように、目的に応じて提供する場の性質が異なります。
・安全・安心の場:子どもたちが心穏やかに過ごせる環境
・学びの場:学習支援や自己表現の機会を提供
・交流の場:他者との関わりを深める空間
しっかりとした目的設定が、プロジェクトの成功につながります。
3. 計画の立案
具体的な活動計画を立てることは、プロジェクトの骨組みを形成する重要なプロセスです。運営体制や資金計画も含めた包括的な計画が、スムーズな進行を支えます。

資金計画では、補助金やクラウドファンディングを有効活用することが成功の鍵です。
4. 場所の確保
活動場所は、子どもたちが安心して集える環境であることが重要です。以下のようなポイントを押さえて、適切な場所を選びましょう。
・安全性:事故やトラブルを防ぐ環境
・アクセス:子どもや保護者が通いやすい立地
・設備:必要な設備(机、椅子、トイレ等)が整っていること
活動場所が適切であることが、子どもたちの参加意欲を高める要因になります。
5. 運営開始
計画が整ったら、いよいよ運営開始です。関係機関との連携や広報活動を通じて、スムーズな運営を目指しましょう。
運営時に注力すべき項目
・関係機関との連携:学校、地域団体、福祉施設
・広報活動:SNS、チラシ、地域イベントでの周知
・参加者募集:対象者への直接アプローチ
これらの活動を通じて、プロジェクトの認知度を高め、参加者を確保します。
6. 効果検証と改善
運営を続ける中で、定期的に効果を検証し、改善を図ることが不可欠です。PDCAサイクルを回すことで、プロジェクトをより良いものにしていきます。

このように、継続的な改善が居場所の質を高め、持続可能な運営を実現します。
💡クラウドファンディングの達成率は?
運営上の注意点と課題への対応策

居場所の運営が軌道に乗るとともに、さまざまな課題が見えてきます。ここでは、安全対策や関係機関との連携、人材確保と育成といった重要なポイントを解説し、それぞれの課題にどのように対応すべきかを紹介します。
安全対策:事故防止と緊急時の対応
子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供するためには、安全対策が最優先です。具体的には、以下のような取り組みが必要です。
・事故防止策:活動場所の定期的な点検、リスクのある設備の改善
・緊急時の対応:緊急連絡先の明示、スタッフの応急処置訓練
安全対策の徹底は、子どもたちだけでなく保護者の信頼を得るためにも欠かせません。
関係機関との連携:学校・家庭・地域のつながり
居場所が地域に根付くためには、学校や家庭、地域団体との連携が重要です。定期的な情報共有や連絡会の開催を通じて、各機関と良好な関係を築きましょう。
具体的な取り組み
・学校との連携:子どもの状況を共有し、適切なサポートを検討
・家庭との連携:保護者へのフィードバックや相談窓口の設置
・地域との連携:自治会や地域イベントへの参加
こうした連携が、子どもたちを取り巻く支援体制を強化します。
人材確保:ボランティアとスタッフの育成
運営を支える人材の確保と育成も大きな課題です。特にボランティアスタッフは重要な役割を担いますが、定着率を上げるための工夫が必要です。
対応策
・募集方法の多様化:SNSや地域の掲示板を活用
・研修とフォローアップ:定期的な研修やスタッフ間の交流会を開催
・モチベーション維持:感謝の気持ちを伝える場を設け、やりがいを感じてもらう
質の高い人材が揃うことで、居場所の運営がより円滑になります。
💡【実行者必見!!】クラウドファンディングが達成しなかったら?
まとめ:子どもたちの未来のために

子どもたちにとって安心できる居場所は、心身の健やかな成長を支える重要な存在です。本記事では、居場所づくりの具体的な手順や資金調達方法、運営上の課題とその対応策について詳しく解説しました。これらを活用すれば、地域のニーズに応じた居場所を効果的に設立し、運営することが可能です。
居場所を提供することで、子どもたちは新たな可能性を見つけ、安心して未来に向かって歩む力を育むことができます。また、地域全体で子どもたちを支える仕組みを構築することで、社会全体の健全な発展にも寄与します。
これから居場所づくりに挑戦する方々にとって、本記事が一助となれば幸いです。
よくある質問
なぜ「子どもの居場所づくり」が必要なのか?
現代社会では、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、多様な課題が生じています。ここでは、居場所づくりがなぜ重要なのか、よくある疑問にお答えします。
(1) 現代社会における子どもの課題
現代の子どもたちは、家庭や学校での人間関係の悩み、孤独感、学力格差、貧困など、さまざまな問題に直面しています。特に、核家族化や地域コミュニティの希薄化により、家庭や地域での支援が不足しがちです。その結果、心の拠り所を見つけられない子どもが増えています。
(2) 居場所が子どもにもたらす効果
安心できる居場所は、子どもたちに以下のような効果をもたらします。
・心理的安定:自分を受け入れてもらえる環境で、心の負担が軽減される
・社会性の向上:他者との交流を通じて、コミュニケーション能力が育まれる
・学びと成長の機会:新しいことに挑戦し、自信をつける場となる
居場所づくりは、子どもたちの将来に向けた大切な土台を築くことに直結します。このように、社会全体で子どもを支えるために居場所の存在は欠かせません。
他にも具体的な疑問や不安がある場合は、ぜひお問い合わせください。
あなたの熱い気持ちを世界に発信しませんか。
無料相談も受け付けておりますので、「まだクラウドファンディングは考えていないが、一度話を聞いてみたい」という方でもぜひご相談ください。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!