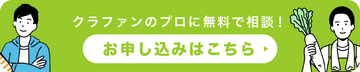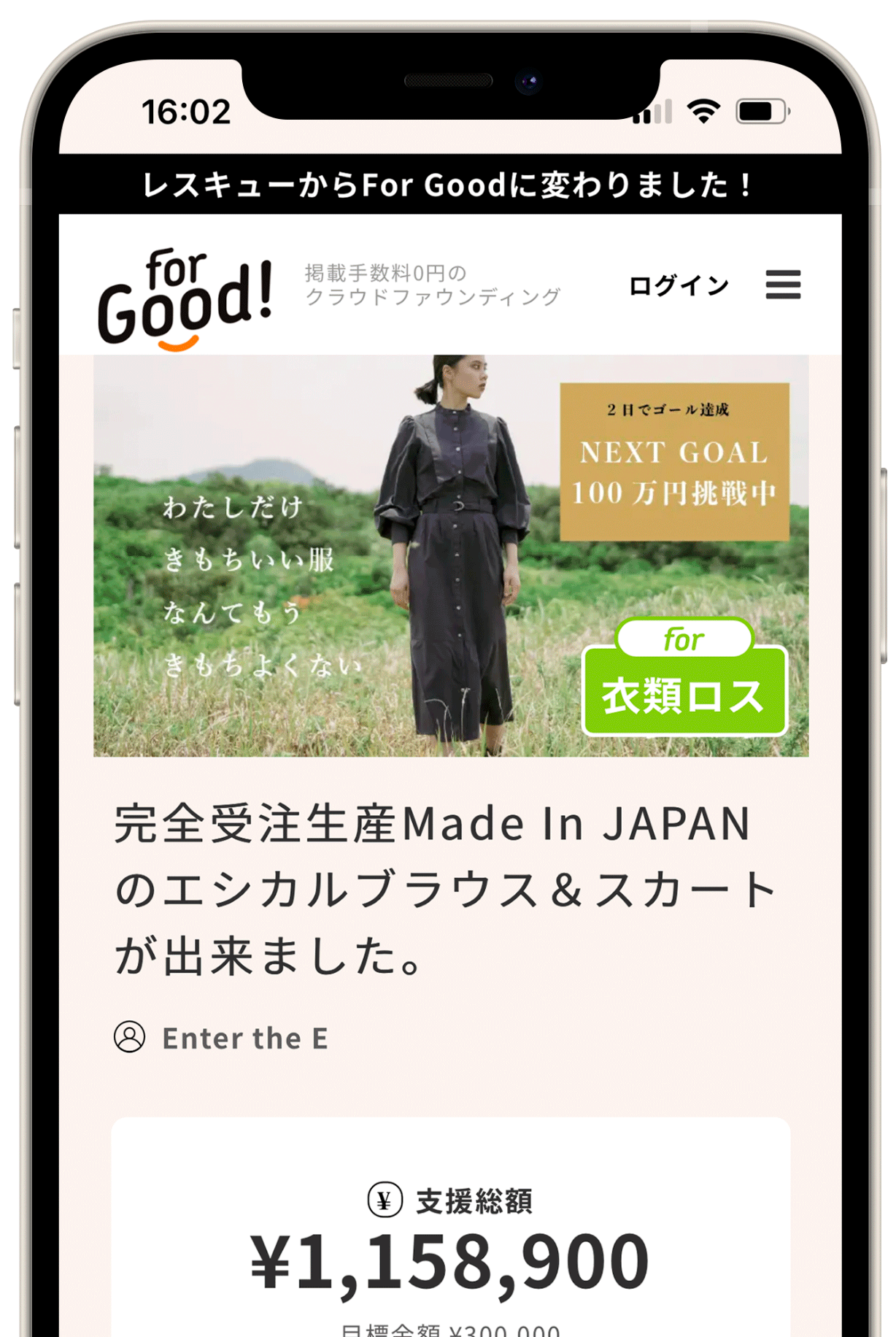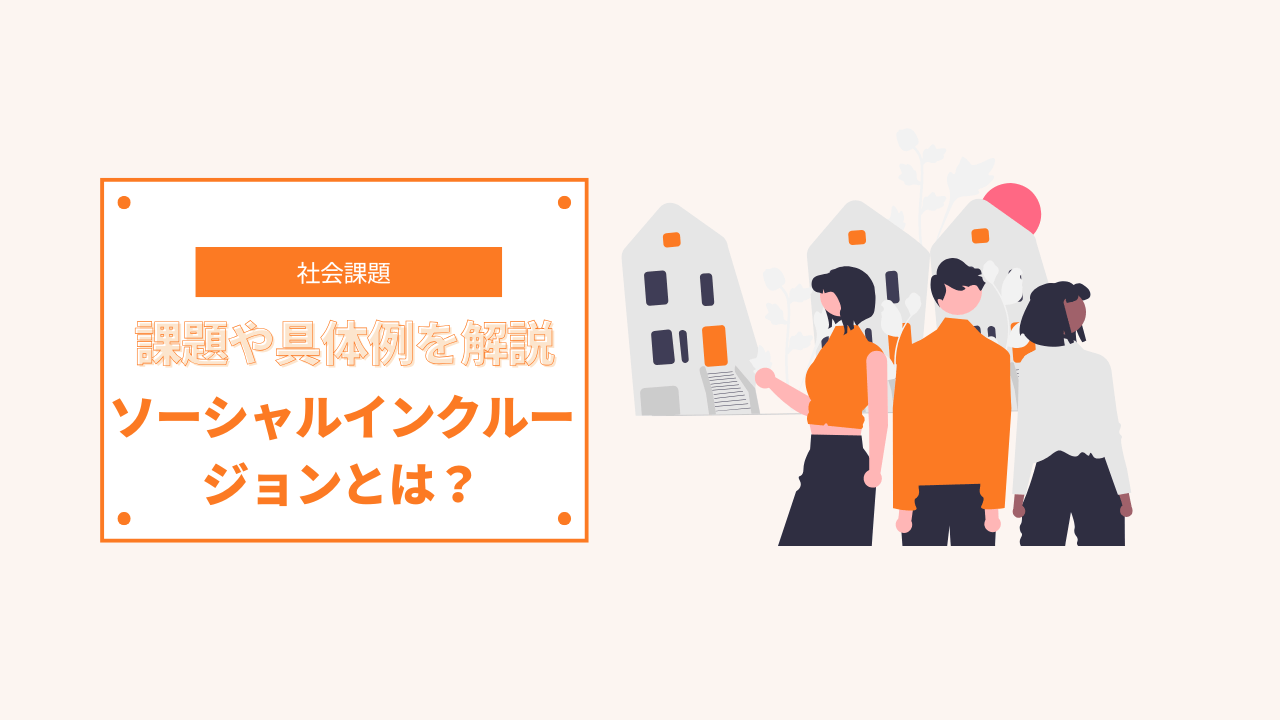
ソーシャルインクルージョンとは?課題や具体例を解説
「ソーシャルインクルージョン」とは、誰一人取り残さない社会を目指す理念です。この考え方は、私たちの身近な課題とも深く関係しています。
そこで本記事では、下記内容を解説していきます。
・ソーシャルインクルージョンの基本を解説
・日本の課題と政府の対応
・企業・団体の実践例紹介
今すぐ知って、一歩を踏み出してみませんか?
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
- 1. ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)とは
- 2.日本におけるソーシャルインクルージョンの課題
- 3.ソーシャルインクルージョンにおける日本政府の取り組み
- 4.ソーシャルインクルージョンにおける企業・団体の取り組み例
- カンボジアの子どもたちが取り残されないよう支える教室を運営
- 猫と人が幸せに共生できる社会を目指した保護猫シェルターを運営
- ビル一棟で起業家の孤独問題を解決
- 紛争地域での自立支援
- 5.まとめ:ソーシャルインクルージョンは単なる理想論ではない
ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)とは

ソーシャルインクルージョンは、社会の中であらゆる人々が排除されることなく、平等に参加できる状態を目指す理念です。その背景には、経済的、文化的、身体的なハンデを抱える人々が「取り残されない社会」を作るという強い意志があります。
以下では、その発祥や日本への広がり、関連する概念との違いを解説します。
発祥はフランス。社会学者ルネが提唱
ソーシャルインクルージョンという考え方は、1970年代にフランスの社会学者ルネ・レノアによって提唱されました。当初は、貧困層や社会から排除されがちな人々を支援する政策の一環として議論され、徐々に欧州全体で重要な社会政策として受け入れられるようになりました。
2000年に厚労省が提唱。日本にも広がる
日本では、2000年に厚生労働省が「社会的包摂」という言葉を使用し、この概念を政策に取り入れる動きが始まりました。以降、高齢者支援や障がい者雇用、地域コミュニティの再生など、多様な分野でソーシャルインクルージョンを基盤とした取り組みが広がっています。
この理念は、日本社会の課題を解決するための重要な指針となっています。
ノーマライゼーションとの違い
ソーシャルインクルージョンと似た概念に「ノーマライゼーション」がありますが、両者には違いがあります。ノーマライゼーションは、障がいを持つ人々が特別扱いされることなく、普通の生活を送る権利を保障する考え方です。一方、ソーシャルインクルージョンは、それに加えて、経済的、社会的なあらゆる要因で排除される可能性のある人々を包括的に支援する広い視点を持っています。
ソーシャルインクルージョンは、単なる理念にとどまらず、具体的な政策や取り組みとして形を成しています。
次に、日本政府がどのような施策を通じてこの理念を実現しようとしているのかを見ていきましょう。
日本におけるソーシャルインクルージョンの課題

日本社会でも、ソーシャルインクルージョンの実現に向けた取り組みが進む一方で、さまざまな課題が残っています。
震災や文化的障壁、雇用環境の不均衡など、具体的な課題について解説します。
震災による社会的排除
東日本大震災やその他の災害では、被災地の住民が孤立するケースが見られました。特に、高齢者や障がいを持つ人々は避難生活や地域復興の中で排除されやすく、支援が行き届かない状況が課題となっています。
災害時の支援体制を見直し、全ての人が必要な支援を受けられる環境を整えることが求められています。
文化面でのバリアフリー
日本では、障がい者や外国人が文化活動に参加しにくい環境が依然として存在します。劇場や博物館の設備、情報の多言語化の遅れなどが例に挙げられます。文化のバリアフリーを進めることで、多様な人々が社会的なつながりを持ちやすくなることが期待されています。
中小企業での障がい者雇用
大企業に比べ、中小企業では障がい者の雇用が進みにくい現状があります。理由としては、制度の理解不足や設備投資の負担が挙げられます。
特に、法定雇用率を満たしていない企業も多く、雇用の場を増やす取り組みが急務です。
制度の狭間にいる人たち
現行の福祉制度では、高齢者、障がい者、生活困窮者などを支援する枠組みが整備されていますが、その制度に該当しない「狭間」にいる人々が支援を受けられないケースもあります。このような人々への柔軟な支援策が必要とされています。
隠れ失業
失業率が表面的には低くても、非正規雇用や短時間労働を強いられ、生活が不安定な「隠れ失業」の状態にある人々が増えています。特に若年層や女性に多く、こうした人々が社会的排除に陥らないための支援が重要です。
これらの課題に対して、政府や企業、NPOがどのように取り組んでいるのかを知ることで、私たちにもできることが見えてきます。次に、日本政府が実施している具体的な取り組みを見ていきましょう。
ソーシャルインクルージョンにおける日本政府の取り組み

日本政府は、ソーシャルインクルージョンの理念を実現するため、さまざまな政策を進めています。ここでは、障がい者雇用の促進と年金制度改革という2つの重要な取り組みを紹介します。
改正障害者雇用促進法
日本では、障がい者の雇用促進を目的に「障害者雇用促進法」が改正され、2021年に施行されました。この改正では、雇用率の対象となる障がい者の範囲を広げ、企業に対してより多様な雇用機会の提供を求めています。
また、精神障がい者の雇用義務化も進み、働く場が増えるだけでなく、企業内の意識改革も促進されています。この取り組みは、障がい者が職場での活躍を通じて社会とのつながりを築くための重要な一歩です。
年金支給開始年齢の引き上げ
年金支給開始年齢の引き上げは、高齢者が社会に長く関わり続ける仕組みづくりの一環です。日本では、少子高齢化に伴い、65歳以上の雇用機会が拡大しています。この政策は、定年後も働きたいという意欲のある高齢者が、社会の一員として活躍し続けられる環境を整えることを目的としています。同時に、社会保障制度の持続可能性を確保する役割も果たしています。
これらの取り組みは、日本社会全体でソーシャルインクルージョンを推進するための重要な基盤です。
次に、企業や団体がどのようにこの理念を実現するための活動を行っているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
ソーシャルインクルージョンにおける企業・団体の取り組み例
カンボジアの子どもたちが取り残されないよう支える教室を運営

NPO法人SALASUSUは、カンボジアで貧困の連鎖を断ち切るため、「誰も取り残さない教室」を設立するプロジェクトを進めています。2008年から女性の就労支援やライフスキル教育を提供してきた経験を活かし、全ての子どもたちに質の高い教育機会を提供することを目指しています。
〈プロジェクトの詳細〉
■貧困の連鎖を止める「誰も取り残さない教室」をカンボジアにつくりたい!
■達成金額 ¥4,181,500
■目標金額 ¥4,000,000
■支援者数 209人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1000135
猫と人が幸せに共生できる社会を目指した保護猫シェルターを運営

ネコリパブリックは、東京の保護猫シェルターの移転に伴い、中古一軒家を購入・改装するプロジェクトを進めています。現施設の閉鎖により、約40匹の猫たちの新たな居場所を確保し、安定した運営を目指しています。
〈プロジェクトの詳細〉
■ネコリパ東京シェルター存続の危機!都内に中古一軒家を購入改装し猫助けを加速したい
■達成金額 ¥39,166,468
■目標金額 ¥30,000,000
■支援者数 1,835人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1001107
ビル一棟で起業家の孤独問題を解決

北九州市門司港で、ビル一棟を改装し、コミュニティ型共同住宅「POSTO&Co.」を創設するプロジェクトが進行中です。この施設は、孤独の解消と経済活動の両立を目指し、住民や地域の人々が交流できるスペースを提供します。
〈プロジェクトの詳細〉
■孤独のない社会を創る!ビル一棟を心の拠り所となる居場所に再生
■達成金額 ¥5,493,500
■目標金額 ¥3,000,000
■支援者数 306人
➡ 詳細を見る https://rescuex.jp/trn_project/66270
紛争地域での自立支援

認定NPO法人テラ・ルネッサンスは、紛争や災害の被害者の尊厳を守り、平和な社会を構築することを目指しています。活動は、カンボジアの地雷被害者やアフリカの元子ども兵への自立支援、ウクライナ難民への緊急支援など、多岐にわたります。
〈プロジェクトの詳細〉
■紛争や災害の被害にあった人々の命と暮らし尊厳を守り、平和な社会をつくりたい。
■達成金額 ¥10,475,000
■支援者数 499人
➡ 詳細を見る https://rescuex.jp/trn_project/96002
まとめ:ソーシャルインクルージョンは単なる理想論ではない
ソーシャルインクルージョンは、誰もが社会に参加できる環境を目指す現実的な目標です。行政や企業、NPOの取り組みに加え、私たち一人ひとりの行動もその実現に繋がります。
寄付やボランティアなど、小さな一歩から始めて、誰もが取り残されない社会づくりに貢献してみませんか?
あなたの熱い気持ちを世界に発信しませんか。
無料相談も受け付けておりますので、「まだクラウドファンディングは考えていないが、一度話を聞いてみたい」という方でもぜひご相談ください。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!