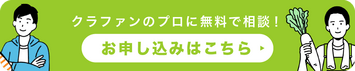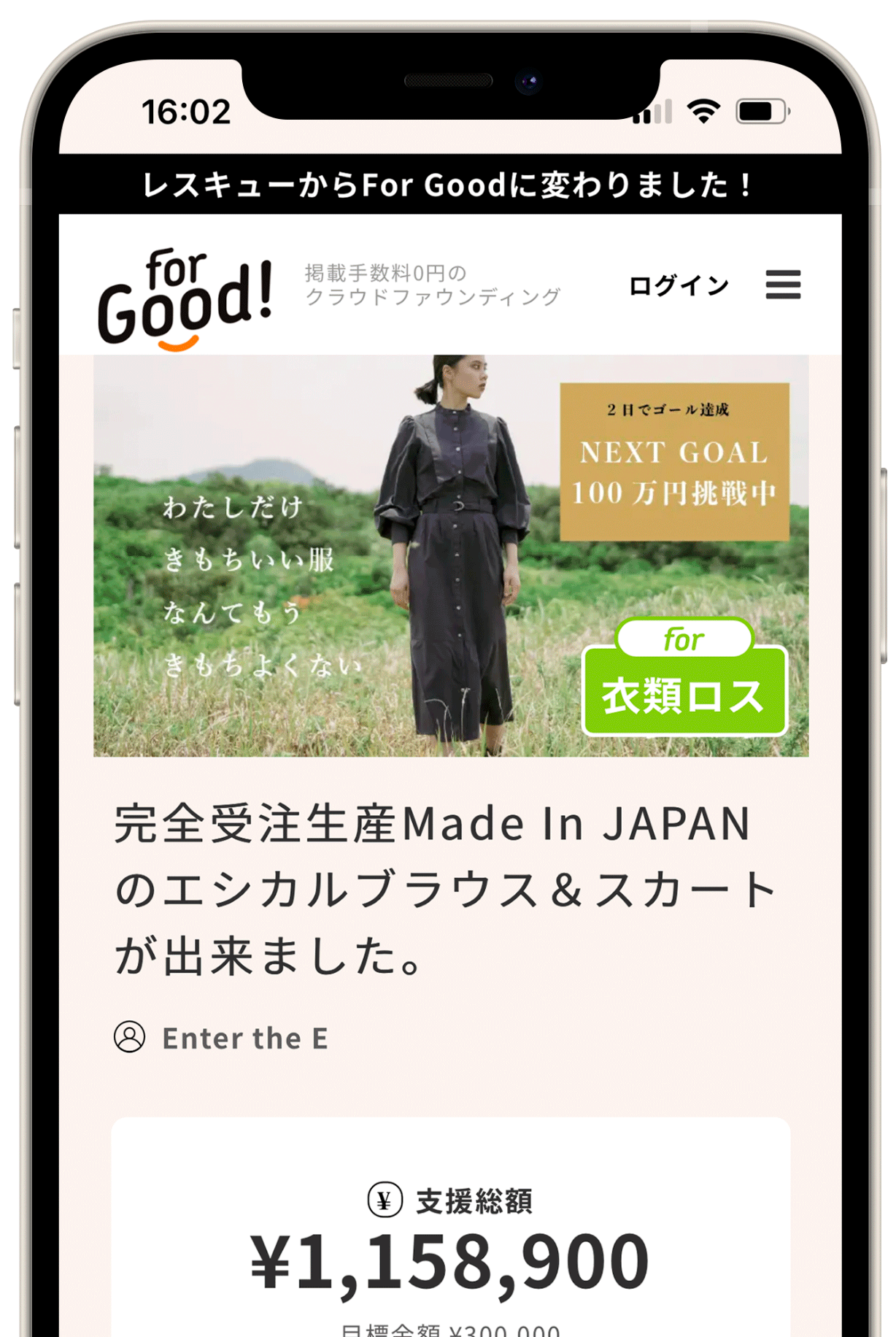補助金とクラウドファンディングは併用できる?事例や注意点を徹底解説
やりたいことはあるけれど、資金が足りない。
そんなときに頼れるのが補助金やクラウドファンディングといった資金調達方法です。
でも、この2つって併用できるのでしょうか?
そこで本記事では、下記内容を解説していきます。
・補助金とクラファンの併用可否
・成功事例と使える補助金例
・併用時の注意点と対策
未来の成功を掴むためのヒントをぜひチェックしてください!
クラウドファンディングと補助金は併用可能?
クラウドファンディングと補助金・助成金は、基本的に併用可能なケースも多く、上手に活用すれば資金調達の幅を広げることができます。
たとえば、補助金でカバーできない経費をクラファンでまかないながら、プロジェクトのPRやファン獲得にもつなげるといった方法です。
ただし、すべての補助金制度で併用が認められているわけではありません。制度ごとに「他の資金との併用」に関するルールや制限が設けられているため、事前の確認が重要です。
次の章では、クラウドファンディングとの併用が禁止されるケースや、注意すべき例外について詳しく見ていきましょう。
クラウドファンディングと補助金の併用が禁止されるケース
クラウドファンディングと補助金・助成金は併用できる場合もありますが、制度や申請内容によっては禁止されるケースもあるため、注意が必要です。
【よくある併用NGのケース】
・補助金の公募要領に「他の助成金・収益との併用を禁止」する記載がある場合
→ 特に「同一経費への重複支援」が明確に禁止されていることがあります。
・クラウドファンディングで得た資金が「自己資金」とみなされない場合
→ 補助金の要件で「自己資金割合」が必要な場合、クラファン収益が対象外と判断されることもあります。
・クラウドファンディングの活用について要綱に明記されていない場合
→ 明記がない場合でもグレーゾーンになり、審査時に減点や対象外になるリスクがあります。
これらを避けるためには、以下の点が大切です。
・公募要領の「補助対象経費」や「他制度との併用可否」欄を確認する
・不明点は、事務局や自治体の窓口に事前に問い合わせる
クラウドファンディングは自由度が高い分、補助金制度との相性や扱いにばらつきがあります。
とはいえ、しっかり制度を見極めて組み合わせたことで、実際に成功している事例も多くあります。
次の章では、クラウドファンディングと補助金の併用によって資金調達に成功した実例を見てみましょう。
クラウドファンディングと補助金を併用して資金調達を成功させた事例
クラウドファンディングと補助金をうまく組み合わせて、資金調達と事業の推進を実現した事例が実際に存在します。
ここでは、社会課題の解決に挑むプロジェクトの中から、補助金との併用に成功した具体的な例をご紹介します。
制度の活用方法や資金使途の分け方など、これから併用を検討する方にとって参考になるポイントが詰まっています。
事例① 地域資源を活かした宿泊施設作り
沖縄・大宜味村の廃校を宿泊施設として再生するため、補助金と融資で4,000万円を準備し、インフラ整備などの基盤を整えました。
しかし、建築基準法に基づく用途変更に伴い、想定外の改修費が発生。
クラウドファンディングでは、補助対象外となった浄化槽設置や防災設備など追加の必須経費をカバーするための資金を募りました。
〈プロジェクトの詳細〉
■PJタイトル名:127年続いて廃校になった旧 喜如嘉小学校に、宿泊施設をオープンさせたい
■達成金額 ¥15,468,500
■目標金額 ¥5,000,000
■支援者数 671人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1001855
事例② 環境に良いテーマパークの拡大
耕作放棄地を再生し、ソーラーシェアリングで電力と農作物の両方を生み出す「食とエネルギーのテーマパーク」を創出。
補助金や交付金を活用して農業設備などの一部を整備しつつ、クラウドファンディングでは非FIT発電所建設の初期費用や自己資金不足分をカバーしました。
地域共生型の仕組みを支える財源として、多様な資金源を柔軟に組み合わせた好事例です。
〈プロジェクトの詳細〉
■PJタイトル名:『食とエネルギーのテーマパーク』を、ソーラーシェアリングでつくりたい
■達成金額 ¥7,006,000
■目標金額 ¥3,000,000
■支援者数 351人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1001111
事例③ アフリカの若者の雇用創出
クラウドファンディングで集めた資金と、融資・助成金などの外部資金約700万円を組み合わせ、アフリカ・ルワンダでIT人材育成と就労支援の拠点を整備。
教育・品質管理・ジョブマッチングを統合したシステム「LEAP」と、地方にも設置されるPC・インターネット環境「Ready to Bloom Hub」の整備を通じて、1000名規模の雇用創出を目指しました。
クラウドファンディングの成功が、外部資金獲得の後押しとなり、大規模な社会的インパクトに繋がっています。
〈プロジェクトの詳細〉
■PJタイトル名:大卒若者失業率70%のアフリカで、1000万人へ学びの機会と雇用を作る!
■達成金額:¥3,022,500
■目標金額:¥1,000,000
■支援者数:154人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1001333
このように、クラウドファンディングと補助金をうまく併用することで、より大きなインパクトを生むプロジェクトが可能になります。
では、具体的にどのような補助金制度がクラウドファンディングと併用しやすいのでしょうか?
次の章では、併用が可能な代表的な補助金制度をご紹介します。
クラウドファンディングとの併用が可能な補助金例
クラウドファンディングと補助金・助成金の併用を成功させるためには、併用が認められている補助制度を知ることが第一歩です。
ここでは、実際にクラウドファンディングと組み合わせて活用しやすい代表的な補助金を紹介します。
創業支援の補助金
これから起業・開業を目指す人に向けた補助金は、クラウドファンディングとの相性がよく、多くの実例があります。
新規事業を立ち上げるにあたって、初期費用の一部をクラファンで先に調達し、補助金で設備費や広告費をカバーするなどの併用が可能です。
代表的な補助金例:
・小規模事業者持続化補助金(創業枠・通常枠)
・地域創生起業支援金(都道府県や自治体主導)
・各自治体の創業促進事業(例:東京都創業助成金)
ポイント:
・一部補助金では「自己資金の準備」が条件になるため、クラファン資金の扱いを事前に確認しましょう。
・創業前後のタイミングでも申請できる制度が多く、計画次第で柔軟な活用が可能です。
ものづくりに関わる補助金
製品開発・製造・システム導入といったものづくり事業においても、クラウドファンディングとの併用が効果的です。
クラファンを通じてマーケットの反応を確認しながら、技術的な課題や設備投資を補助金で支援してもらう形が一般的です。
代表的な補助金例:
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・IT導入補助金(ECサイト・予約システムなども対象)
・先端設備等導入計画(自治体申請型)
ポイント:
・クラファンで集まった資金を“プロトタイプ制作”に充て、その後の量産や広報に補助金を使う流れが王道です。
・技術性や革新性を問われる補助金では、クラファンでの反響や共感がプラス材料になることもあります。
地域活性化・NPO向けの補助金
まちづくり、子ども・高齢者支援、環境保全などの社会的プロジェクトには、NPO法人や任意団体も申請可能な補助金が多数あります。
クラウドファンディングによって活動への共感者や協力者を広げながら、補助金で運営基盤を整えるという流れが有効です。
代表的な補助金例:
・地域づくり支援制度(内閣府・総務省系)
・地方自治体の地域活動支援補助金(市区町村ごとに内容が異なる)
・民間財団の助成金(トヨタ財団、中央共同募金会など)
ポイント:
・任意団体でも申請できる制度があり、クラファン実績が「地域ニーズに即した活動」として評価される場合も。
・運営費・人件費が対象にならない補助金も多いため、クラファンで補完するとバランスが取りやすくなります。
クラウドファンディングと補助金を併用するメリット
補助金とクラウドファンディングを上手に組み合わせることで、単独では得られない資金や効果を引き出すことが可能になります。
この章では、実際に併用することで得られる3つの代表的なメリットをご紹介します。
「どうせなら賢く、支援も仲間も集めたい」そんな方にこそ、クラウドファンディングの併用はおすすめです。
補助対象外の費用もクラファンでカバーできる
補助金には、「補助対象経費」が明確に定められており、広告費や人件費、運転資金などは対象外とされることが多くあります。
そこで役立つのがクラウドファンディングです。
併用のポイント:
・補助金で対象外となる経費(例:リターン制作費、活動準備費など)をクラファンでまかなえる
・「補助金+クラファン」で、実質的にプロジェクト全体をカバーできる資金計画が可能に
ファン獲得・PR効果が高まり、事業の認知も広がる
クラウドファンディングは単なる資金調達手段ではなく、共感を広げる“広報ツール”としても非常に有効です。
得られる効果:
・支援者が“応援者”や“初期ユーザー”としてプロジェクトの輪を広げてくれる
・SNSやメディアに取り上げられることで、補助金では得られない社会的認知や信頼を獲得できる
・地域や関係者との関係性づくりに役立つ
クラファン実績が補助金審査時の信頼材料になることも
クラウドファンディングの実施実績は、「すでに応援してくれる人がいる」「事業に社会的意義がある」ことの証明として、補助金の審査時にも好印象となる場合があります。
期待される効果:
・支援者数や目標達成率が「事業の実現可能性」の裏付けになる
・「市民や地域からのニーズがある」と見なされ、加点対象となる補助金もある(例:地域活性化系)
このように、クラウドファンディングと補助金の併用は、単なる資金の足し算にとどまらず、事業の信頼性・広がり・実行力を高める手段にもなります。
ただし、良いことばかりではありません。次の章では、併用する際に直面しやすいデメリットや注意点についても解説していきます。
クラウドファンディングと補助金を併用するデメリット
補助金とクラウドファンディングの併用には多くのメリットがある一方で、スケジュールや管理の複雑さ、制度上のリスクなど、注意が必要な点もあります。
この章では、実際に併用を検討する際に直面しやすいデメリットを紹介します。
事前に理解しておくことで、トラブルやロスを防ぎ、安心してプロジェクトを進めることができます。
申請・実行・報告の事務負担が増える
補助金とクラファンは、それぞれ必要な書類や進行管理のルールが異なります。両方を活用する場合、事務作業や準備の負担が大きくなる点には注意が必要です。
主な負担の内容:
・補助金用の事業計画書・報告書類の作成
・クラファンページ制作、リターン管理、支援者対応などの運営業務
・両方のスケジュールを並行管理する必要がある
使途やタイミングのミスで補助金対象外になるリスクがある
補助金は「交付決定前の支出は対象外」「対象経費が限定されている」など、厳格なルールが存在します。クラファンと組み合わせる際には、タイミングや費目のズレに注意しなければなりません。
よくある失敗例:
・クラファン開始を急いでしまい、補助金の交付決定前に経費を使ってしまった
・同じ費用をクラファンと補助金の両方でカバーしようとして“重複支出”と判断された
・補助金では対象外のリターン費用を誤って経費として申請してしまった
クラファンの収益が補助金審査に影響する可能性も
補助金によっては、クラウドファンディングの収益を“自己資金”と認めない、または“収益性の高い事業”と見なされることがあります。
注意したい点:
・「自己資金要件」のある補助金では、クラファンの扱いが不明確な場合がある
・非営利型の補助金で、クラファン収益が“営利活動”と判断され減点になることも
・リターンの設計や価格設定により、収益構造に誤解が生じやすい
このように、併用には慎重な設計とスケジュール管理が不可欠です。
次の章では、これらのデメリットを避けるために役立つ注意点とチェックリストをご紹介します。失敗を防ぎ、スムーズに併用するための実践的なヒントをまとめています。
併用にあたっての注意点とチェックリスト
補助金とクラウドファンディングをうまく併用するには、制度ごとのルールを理解し、事前の準備を丁寧に行うことが鍵です。
ここでは、実際に併用する前に押さえておきたい重要なポイントを、3つの視点から解説します。
クラファンの実施タイミングと申請スケジュールを整理する
クラウドファンディングと補助金の申請・審査・実行のスケジュールが計画とずれたり重複してしまうと、予期せぬトラブルや資金ショートにつながります。
意識すべきタイムライン:
・補助金の申請時期、交付決定日、報告期限
・クラウドファンディングの開始日・終了日、入金日、リターン発送時期
・それぞれのタイミングが重複しないよう、月単位でスケジューリングするのが理想
「対象経費の重複」や「収益の扱い」に注意する
補助金とクラファンの併用では、同じ費用を両方でカバーする“二重支出”や、クラファンの収益の扱い方にも注意が必要です。
注意点の例:
・クラファンで集めた資金を「事業収益」として処理し、補助金と混同しない
・同じ領収書を両制度に使わない(例:リターン制作費をクラファンでまかない、別の経費を補助金で)
・収益が出る事業であれば、その使い道や収支計画も明確にしておく
専門家に事前相談する
補助金やクラウドファンディングの併用は、制度ごとの細かい違いや判断基準も多いため、ひとりで進めるのはリスクが高くなります。
不安な場合は、早めに専門家に相談するのが賢明です。
相談先の例:
・商工会議所や地域の創業支援センター
・補助金申請に詳しい中小企業診断士
・クラファンプラットフォーム
For Goodはクラファンに関する無料相談をLINE・オンラインMTGで受け付けています。
|
チェック項目 |
内容 |
チェック欄 |
|
補助金制度の要項を確認したか |
他制度との併用可否や補助対象経費の規定を読んだか |
□ |
|
クラファン資金が「自己資金」として扱われるか確認したか |
補助金の自己資金要件に該当するか自治体・事務局に確認済みか |
□ |
|
補助金の「交付決定前」に支出しない計画になっているか |
クラファン開始時期や経費発生のタイミングが補助対象内に収まっているか |
□ |
|
同じ経費を重複して申請していないか |
補助金・クラファンで対象とする経費を明確に分けているか |
□ |
|
クラファンと補助金のスケジュールが整理されているか |
申請・実行・報告のタイミングを月単位で管理しているか |
□ |
|
専門家や支援機関に相談したか |
商工会議所、中小企業診断士、支援プラットフォーム等に事前確認したか |
□ |
これらの注意点を押さえれば、補助金とクラウドファンディングの併用を、より安全かつ効果的に活用できるようになります。
次の章では、クラファン自体の取り組みに対して助成が行われる「クラウドファンディング活用助成金」についてご紹介します。
クラファンを始めたい方にとって、心強い選択肢のひとつです。
クラウドファンディング活用助成金とは?
これまで紹介してきた補助金は、あくまで事業そのものの活動に対する支援が中心でした。
一方で、近年ではクラウドファンディング自体の実施に対して助成を行う制度も各地で増えています。
「クラファンに挑戦したいけど、広報費や動画制作費のハードルが高い…」そんな人にとっては、非常に心強い支援制度です。
クラファン自体の実施に対して支給される
クラウドファンディング活用助成金とは、クラファンの立ち上げや運営にかかる経費(例:ページ制作、動画撮影、PR費など)に対して助成される制度です。
対象経費は自治体や制度によって異なりますが、次のような支援内容が一般的です。
対象になりやすい経費例:
・プロジェクトページ作成費用
・広報用の写真・動画撮影費
・SNS広告やポスターなどのPRツール制作費
・クラウドファンディング実施に関わる専門家への依頼料
東京都での導入例
特に東京都をはじめとする一部自治体では、地域資源の活用や創業支援、NPOの活動促進を目的として、クラウドファンディング活用助成を導入しています。
例:東京都クラウドファンディング活用支援事業(過去実施例)
・対象:都内で創業・地域活性化を目指す事業者やNPO等
・条件:クラファン実施を前提に、事前申請・審査あり
・支援内容:クラファン立ち上げ費用の1/2を補助(上限30万円)
このような制度は、初めてクラウドファンディングに挑戦する人にとって、費用的にも心理的にも大きな後押しになります。
気になる方は、お住まいの自治体や地域の創業支援窓口のサイトをチェックしてみるとよいでしょう。
まとめ|クラウドファンディングと補助金・助成金を併用して効果的な資金調達を実現しよう
クラウドファンディングと補助金・助成金は、それぞれに強みがあり、うまく併用することで資金面・PR面の両方を補える強力な組み合わせになります。
とはいえ、制度ごとにルールが異なるため、「何に使えるのか」「いつから使っていいのか」などをしっかり確認し、スケジュールと資金の使い分けを丁寧に設計することが成功のカギとなります。
今回ご紹介したチェックリストや事例を参考に、
・対象となる補助金の選定
・クラウドファンディングとの費用・役割の切り分け
・計画的な実施タイミングの調整
を意識することで、リスクを抑えつつ、より実現性の高い資金調達が可能になります。
「地域の課題を解決したい」「新しい挑戦を形にしたい」――そんな想いがある方にこそ、この併用という選択肢が力になります。
まずは、身近な補助金制度とクラウドファンディングのサポート体制を調べるところから、第一歩を踏み出してみてください。
クラウドファンディングに興味がある方は、
ぜひ「For Good」で一緒に取り組みましょう!