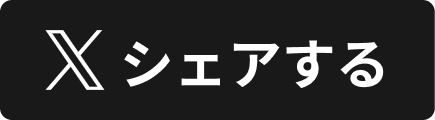ルワンダ貧困改善
ルワンダのシングルマザー20世帯にお腹いっぱい食べられる生活を!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/7/1 15:38
10年越しのソーシャルビジネスへの想い

クラウドファンディングプロジェクト「ルワンダのシングルマザー20世帯にお腹いっぱい食べられる生活を!」を実施して半年ほど経ちました。
先日2回目の食糧支援として、グループリーダーに70万ルワンダ・フラン(約8万円)を送金しました。現在は地域で食糧の調達や配給作業をしてもらい、その報告の写真などを待っているところです。
この取り組みをきっかけに、自分のなかでソーシャルビジネスへの想いが再燃しています。その気持ちをブログとYouTubeで語ってみたので、ご覧いただければ幸いです。
〜
社会起業家になりたい。
ソーシャルビジネスをやりたい。
でも何から始めていいかわからない。
そんな方はぜひ読んでみてください。
わたし自身が通ってきた道であり、目指している道半ばだからこそ、その危うさと希望についてお伝えします。
YouTube版はこちら(ほぼ同じ内容を語ってます)↓
ソーシャルビジネスとは
そもそもソーシャルビジネスとは何なのでしょうか。
経済産業省が2008年に発表した「ソーシャルビジネス研究会報告書(案)」によると、ソーシャルビジネスを定義する特性は、①社会性、②事業性、③革新性の3つ。
いきなりちょっと堅苦しいですが、この後はそうでもないのでちょっとだけ我慢して読んでくださいね(次の段落まで飛ばしちゃってもOK)。
①社会性:現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。
②事業性:①のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。
③革新性:新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組を開発すること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。
出典:ソーシャルビジネス研究会報告書(案)
簡単に言えば「社会的な課題を、ビジネスの手法を使って解決する、新しい取り組み」ということですね。上の図で示されているように、特に重要なのは①事業性と②社会性の2点だと考えてよいでしょう*。
*③革新性を定義に含むと、登場して10年20年経ったら新しくないから「ソーシャルビジネス」じゃなくなるのか?でも②の事業性では『継続的に』事業を進めていくことと定めているから矛盾するのでは?という疑問が生じるた。
要するに、単にお金を稼ぐだけでなく、困っている人たちを助け、社会をより良くしていくための取り組み、ということ。もちろん世の中のほとんどの仕事は誰かのお困りごとを解決するために存在しているので、広く捉えればすべてソーシャルビジネスと言えなくもなさそうですが、一般的な仕事と比べてより社会課題の解決に重きを置いている取り組み、と考えるのが良さそうです。
そしてそういったビジネスを立ち上げる人のことを「社会起業家(Social entrepreneur/ソーシャル・アントレプレナー)」と言います。
よりわかりやすくするために、ほかの組織形態と比べてみましょう。
たとえば「ソーシャル(社会性)」方向に特化しているのは、政府/地方自治体やNPO/NGO、ボランティア団体です。

一方、「ビジネス(事業性)」方向に特化しているのが民間企業ですが、いまどきの企業は社会貢献意識も高まっているので、ソーシャルビジネスと明確に違う会社と考えると「社会のことなんかまったく顧みず、自分たちの利益のためだけに事業を展開している企業」ということになります(めっちゃ悪い人がやってそう)。

「ソーシャル」だけだと収益を得られず継続的に事業をおこなっていくのが難しいですし、「ビジネス」だけだと社会的な課題の解決が難しい。これらのいいとこ取りをしているのがソーシャルビジネス、というわけですね。
ソーシャルビジネスの具体例
ではソーシャルビジネスには実際どんな事例があるのでしょうか。
グラミン銀行
もっとも有名なのは、グラミン銀行でしょう。創設者のムハマド・ユヌスさんは、この取り組みによってノーベル平和賞を受賞しています。グラミン銀行は、バングラデシュで1983年に設立されたマイクロファイナンス機関。貧困層、特に女性を対象に、無担保で少額の融資を行い、彼らの自立を支援することを目的としています。
認定NPO法人フローレンス
わたしが影響を受けたのは、日本の認定NPO法人フローレンスの病児保育の取り組みです。病気の子どもを家庭で預かる訪問型病児保育をいち早く開始し、共働き家庭の仕事と育児の両立を支援しています。創業者の駒崎弘樹さんの著書「「社会を変える」を仕事にする: 社会起業家という生き方」を社会人1年目のときに読んで、「社会起業家って働き方があるんだ!なんてかっこいいんだ!」と衝撃を受けました。
ボーダレス・ジャパン
いま日本でソーシャルビジネスと言えば、ボーダレス・ジャパンでしょう。「社会課題解決」と「ビジネス」を両立させることを目指す、ソーシャルビジネスに特化した会社です。社内に多様な社会課題に取り組む複数のソーシャルビジネス事業を立ち上げ、それらを子会社・事業部として展開しています。
たとえばクラウドファンディングのfor Goodは、わたしも昨年末にプロジェクトを立ち上げてお世話になりました。日本の自宅ではハチドリ電力を導入していて、電気代の一部が応援するNPO/NGOへの寄付金として活用されています。
どこの誰のどんな問題をどうやって解決するか
わたしは前述の駒崎弘樹さんの本を読んで、社会起業家という生き方に強烈にあこがれました。20代前半の頃ですね。そして当時は待機児童の問題が盛んにニュースで取り上げられていたので、「子育ての問題を解決できるソーシャルビジネスをやりたい」と思っていました。
でもいま思うのは、そのときはだれのことも見れていなかったということ。子育ての問題を解決したい、つまりは子育てに悩む親を助けたいと思っていたわけですが、その親ってどこにいる誰のことだったの?「子育てに悩む親」というのは属性でしかなく、実態のない概念でしかないんです。
もしあなたが当時のわたしのように「ソーシャルビジネスをやりたい」「社会起業家になりたい」と思っているとしたら、どこの誰のどんな問題をどうやって解決するかを考えてみてください。

わたしの失敗談
わたしは特に「どこの(WHERE)誰の(WHO)」の解像度が低かったために、つまづいてしまいました。子育ての問題に関わるソーシャルビジネスをやりたいと思いつつ、それで困っている親はテレビや本のなかにしか存在せず、自分のまわりにはひとりも実在していなかったからです。だからなにをしていいかわからなかったし、現実も見えていなかった。
逆に身近にそれで困っている人がいたのなら、何に悩んでいて、それをどうやったら解決できるか(HOW)を考えて行動する、という具体的な取り組みに移れていたかもしれません。だから大事なのは、顔と名前のわかる誰かがいて、その人のお困りごとを解決するために動くこと。
逆に言うと、その「顔と名前のわかる誰か」がいないのであれば、あえて社会起業家なんて目指さなくたっていいんです。だって困ってる人がいないんだから。火事も起きてないのに防火服着てホース持ってウロチョロしてるようなもの。それじゃただのコスプレです。隣町では火事が起きてるかもしれませんが、それはいまのあなたには知りようもないし、どうしようもないこと。
そんなふうに中身もないのにソーシャルビジネスや社会起業家という「ガワ」にだけ憧れていた15年前のわたし。そんな自分と似たようないまの10代20代を見ると、身に覚えがあるだけに恥ずかしさを覚えつつ、応援したいなとも思うのです。
ソーシャルビジネスを諦めた10年前
わたしのこの10年の話。大学卒業後、子どもに関わる仕事をしたいと思ってお菓子メーカーに入社。その間に、自分にとっての「どこのだれを」がないことに気づき3年で退社。社会問題が山積している途上国に自分も生活者として住み、「顔と名前のわかる誰か」と出会いたいと思って青年海外協力隊に参加。そこでたまたま派遣されたのが、いまも住んでいるルワンダでした。

協力隊としての2年間のボランティアで、ソーシャルビジネスの種を見つけたいと思っていましたが、気づいたのはいまの自分にできることはなにもないということでした。そこでいったん「ソーシャルビジネス」はあきらめて、自分にできることから始めよう、ただのビジネスでもいいから一番役に立てる人のために働こうと決めました。
そこで2018年に立ち上げたのが、いまも続く日本人向けのスタディツアー事業です。コロナ禍を挟んで現地のパートナーたちの協力を得ながら7年やってきました。

そして去年、ずっといっしょにホームステイプログラムをやってきたホストマザーから「助けてほしい」と初めて頼みごとをされました。それが彼女がリーダーを務める未亡人家庭20世帯の生活支援でした。そこで先述のfor Goodを使ってクラウドファンディングを実施。

プロジェクトは無事に目標達成し、その20世帯に寝具と食と教育の支援をすることができました。でもそれだけでは一時的な支援に過ぎません。これを今回だけで終わらせず、彼女たちが支援に頼らず生活を営んでいけるようにしたい。そう思って、再び「ソーシャルビジネス」と向き合うことを決めました。
10年越しのソーシャルビジネス再挑戦
わたしにとっての「どこの誰の」は、ルワンダ東部県ルワマガナ郡ムシャセクターの未亡人世帯20家族86人になりました。ここに来るまでに10年かかりました。クラファン後は、まだスタディツアーの売上の一部を彼女たちに還元することしかできていないので、とてもソーシャルビジネスと呼べるレベルではありません。
でも、そう遠くない未来に、5年くらいかな……まずはその20家族86人が自分たちで稼いで、毎日十分なご飯を食べて、子どもたちも安心して学校に通えるようにしていきたいです。
ということで、あらためてソーシャルビジネスについて勉強していきます。学んだことはおなじ志をもつみなさんにもシェアしていきたいので、今後もブログやYouTubeをアップ予定です。
ぜひいっしょに学んでもらい、ご意見や感想などもらえたらうれしいです。そしてぜひルワンダに、現場を見に来てください。あなたなりの「どこのだれを」を見つけるヒントが転がっているはずです。
ルワンダを知る、ルワンダで学ぶ
スタディツアーSTART
農村ホームステイや現地在住日本人との交流などを通して、ルワンダの歴史や文化、国際協力、ビジネスを学ぶプログラム
ルワ旅コーデ
日程や行程を自由にお決めいただけるオーダーメイドサービス
著書
『アフリカに7年住んで学んだ50のこと: ルワンダの光と影』
7年のルワンダ生活で得た学びを、50の章にまとめました。きっとあなたにも刺さる発見が、50章のなかにあるはずです。
オンライン講座
『はじめての国際協力〜アフリカ・ルワンダを事例とした現状理解〜』(Udemy)
「アフリカの奇跡」と称される経済発展を遂げているルワンダ。そのルワンダを事例にアフリカや国際協力について学ぶ講座です。
リターンを選ぶ
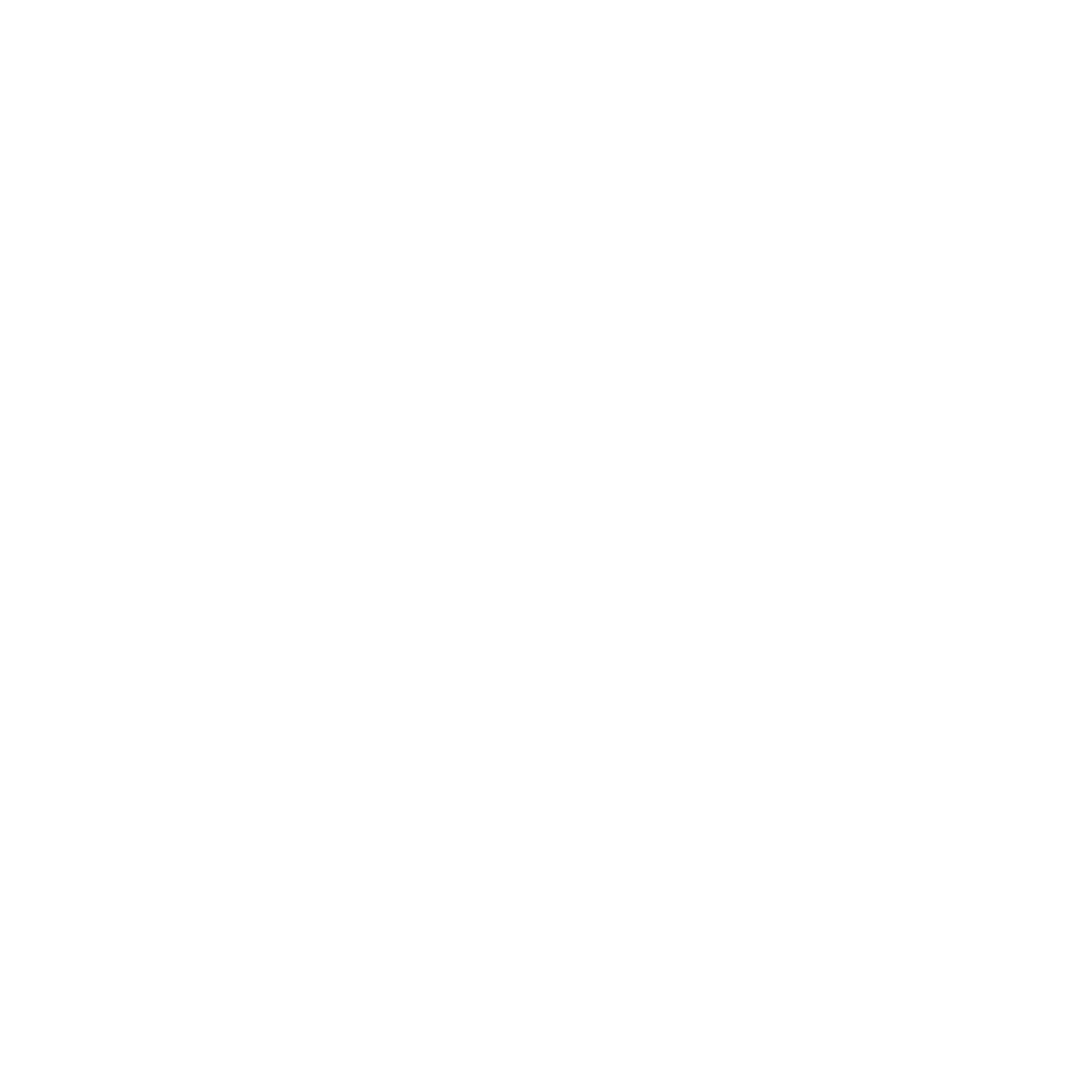
 画像処理中です...
画像処理中です...