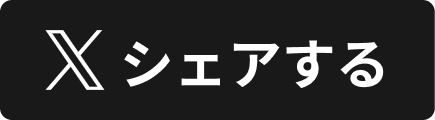創造する力
【新感覚!】スタンプ型画材-ペタロ-で『描いて創造する』喜びが、誰もの日常に!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/10/24 08:15
【応援メッセージ】 綿貫哲様より

けあデザインラボ 代表 綿貫哲様より、
応援コメントを頂きました!
本当にありがとうございます!
・・・
大坪さんとの出会いは、グロービス経営大学院の「デザイン思考と体験価値」のクラスでした。前のめりに学びを深め、楽しむ姿勢がクラス全体を明るくしてくれたことを今もよく覚えています。そんな彼女が立ち上げたNHUMAを訪ねたのは卒業式の前日。“体験”を通じて人の「本人らしさ」を引き出す取り組みに触れ、大きな感銘を受けました。
私自身もスタンプ体験をさせてもらいましたが、とても心地よく、無心でスタンプを押す時間は、時計の針に縛られた日常を忘れられる自由な時間でした。単調に見えるその作業が、むしろ自分らしさを研ぎ澄ます時間であることに気づかされました。これは、高齢者ケアにおいて大切にされるべき「らしさの回復」にもつながる体験だと思います。
老人ホームや介護施設にこの体験を届けたいという彼女の思いに強く共感します。誰もが「やらされる時間」ではなく、「創り出す時間」を持てるようになることは、生きがいの再発見につながります。そして、その時間はご本人にとっても、ご家族にとっても、かけがえのない価値になるはずです。認知症の高齢者や施設での生活リズムに縛られがちな入居者が、スタンプ体験を重ねることで、思わず「らしい」作品を生み出す瞬間には大きな希望を感じます。この挑戦を心から応援しています。どうか多くの方に届きますように。
--------------- <小話>-----------------
綿貫さんとは大学院の授業で、デザイン思考のグループワークをご一緒し、3ヶ月「ケア」をテーマに深めて課題に取り組みました。仕事の後の深夜そして早朝を使って、あーでもないこーでもないと、お互いにテーマ周りで思考と観察を深めていき、ミロで随時気づきのメモをペタペタしていきながら(あ、ここもペタペタ!)プロダクトとサービスを設計してプロモーション動画にまとめていく。おじさまおばさまがヒィヒィ言いながら頑張る、青春時間でした(笑)。

依頼ずっと、活動を応援してくれている大切な仲間です。はるばる秋田からNHUMAにきてくださりPETALOの試作も体験してくれて、色々ケアの現場の専門家として可能性、ヒントをくれました。私がご高齢の方にも喜んでいただけるツールになるかもしれないと、いろんな可能性に目が入ったのも綿貫さんのおかげです!
PETALOで描いてくださった絵も素敵で!!!本当にありがとうございます!

綿貫さんがCADL(Cultural Activities of Daily Life)理論という
ケアとケアマネジメントのイノベーションとなる「新たな概念」のもとで分析くださった「PETALO:貢献の可能性」もシェアしますね。
綿貫さんのtipsで印象的だったのが、梨の枝という「地域・土地の素材」に触れる体験そのものが地域文化への接続、「季節」「収穫」といった暮らしの記憶を呼び起こす可能性を秘めているということ。
ものづくりにおいて、素材という「言語」やプロダクトの持つ「物語」という細部へのこだわりを大切にすることの重要性、細部へのこだわりが秘める価値提供・貢献の可能性を改めて感じるtipsでした。
介護施設にお伺いするとお土地柄農家さんにお会いすることも多く、椅子に座って行う運動をご一緒させていただいたことがありますが、みなさん私より足腰が丈夫で!日々の農作業で鍛えた筋力の賜物。農家さんとしてお勤めされていた時のお話をいっぱいしてくださることを思い出したアドバイスでした。ありがとう綿貫さん!
高齢者へ受けた貢献の可能性
- オブジェクトとして「にぎる」手の運動としての期待
- 創作活動という文化芸術活動があたえる個人への尊厳への心への期待
- 脳へのアプローチ、認知症対策にむけての期待
PETALOの強みが、本人らしさ・地域性・継続性の三拍子で立ち上がるイメージです。「押して模様を作る道具」ではなく、「本人らしさを選び取り、暮らしの文化をつなぎ、日々を耕していく営み」と捉えています。
CADLの「3つのC」Creative(自分で決める)× Culture(暮らしと地域を映す)× Cultivate(小さく続けて育てる)に引き寄せると、「本人らしさの回復→役割の回復→地域の循環」に育っていく景色が見えてきます。
高齢者への貢献は静かに、確かに積み上がる印象を受けています。
1.「にぎる・手の運動」―オブジェクトとしての可能性
Creative(創造)
握り方・押し方・置き方を自分で選ぶ=小さな自己決定の連続。
片手・両手・交互・重ね押しなど“遊びのバリエーション”が自然に生まれる。
Culture(文化)
梨の枝という「地域・土地の素材」に触れる体験そのものが地域文化への接続になる。
ハンドルの形・木目・香りが「庭木」「季節」「収穫」といった暮らしの記憶を呼び起こす。
Cultivate(育む・耕す)
太径グリップ・軽重2段階 “できる感”を積み重ねる。創作を短いようで長い10〜15分の2セット、毎日ではなく週2–3回など「無理なく続く」処方に落とし込むことでの効果を促す。
2.「創作=文化芸術活動」―尊厳・心へのはたらき
Creative(創造)
形・配置・色・タイトルを本人が決める=自律的な表現主体の回復と実感。
作品は「正解」より「選んだ理由」が価値。語りが生まれる可能性。
Culture(文化)
作品を飾る・誰かに贈る・孫に教える=作業を「文化」へ。
Cultivate(育む・耕す)
落書きで止まらず、展示会やポストカードで「社会との接点」を継続的に育てる。
3.「脳へのアプローチ」―認知症予防・進行抑制への期待
Creative(創造)
失敗を感じない「創造活動」で安心して集中が続く。
Culture(文化)
季節・行事・地域などのモチーフで創造すると、記憶の回復や失った言葉が自然に立ち上がる。
梨木の触感・香り=多感覚刺激が“暮らしの時間”を呼び戻す。
Cultivate(育む・耕す)
認知領域(注意切替・実行機能・視空間・作業記憶・言語)に合わせた段階課題を「ゆるやかに継続」。
指標は「できた点数」ではなく、参加時間・自発的選択・発話回数・表情の変化などの日常指標で。
リターンを選ぶ
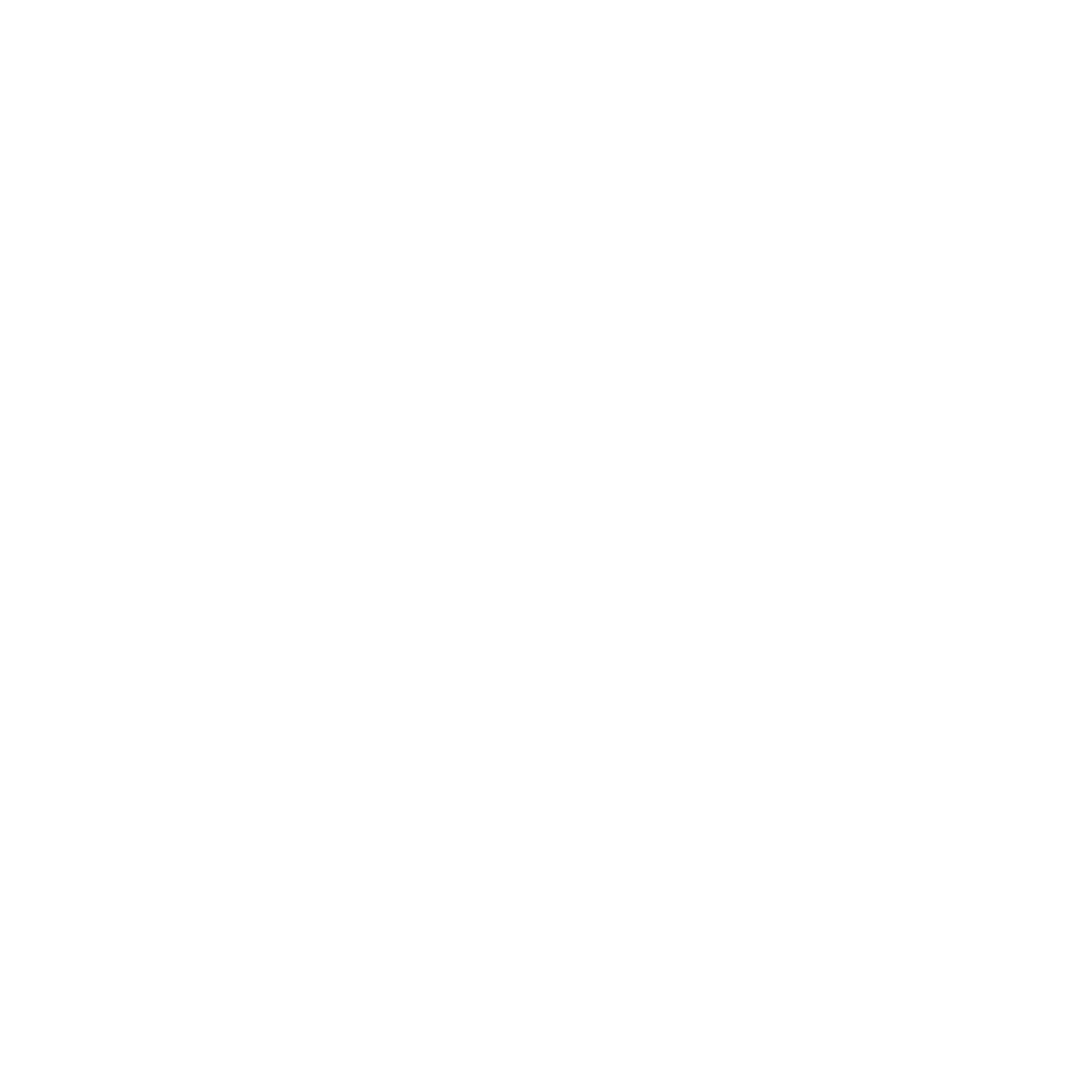
 画像処理中です...
画像処理中です...