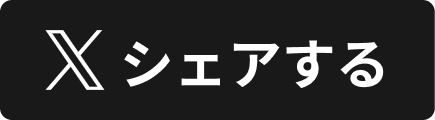住みよいまちづくり
広島県尾道発!猫の医療車「おの猫号」医療の力で人と猫の地域共生モデルを実現!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/11/25 20:00
週末からの捕獲~36匹の不妊去勢、交通事故猫の断尾手術まで

週末からの捕獲~36匹の不妊去勢手術、そして交通事故猫の断尾手術
手術現場では常に"人獣共通感染症のリスク"と背中合わせ
相談から捕獲・搬送、そして手術へ
地域アンケートを経て、町内会が動き出した現場など36匹の不妊去勢手術
手術現場では常に"感染リスクと命の重さ"の最前線
ご支援いただいている皆さまへ。
西日本アニマルアシストの箱﨑です。
週末から本日にかけて、36匹の不妊去勢手術を実施しました。
今回は、相談対応から町内会の動き、捕獲、搬送、手術、術後管理、その後の猫の管理まで、現場の流れに沿ってご報告いたします。
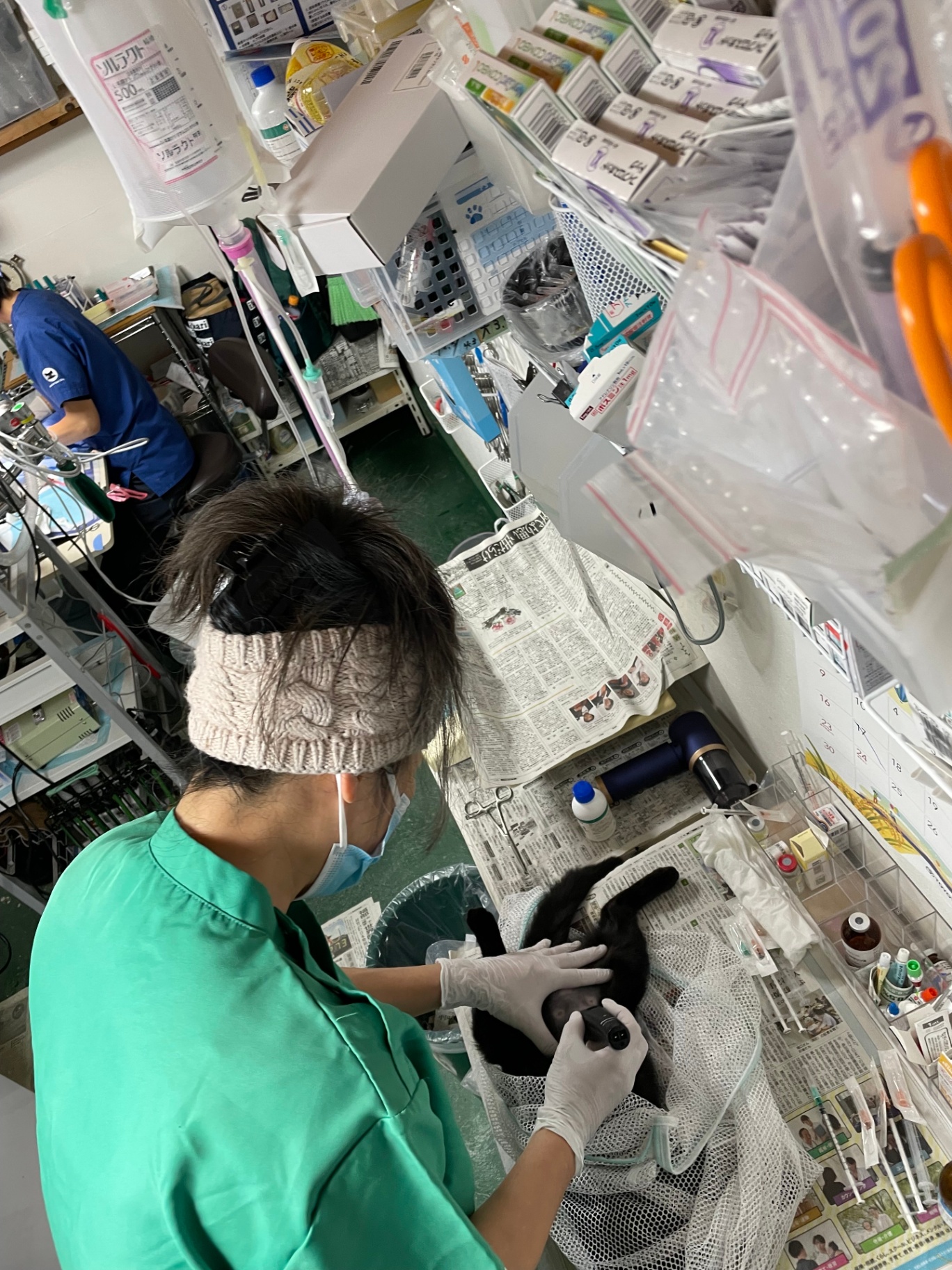
▲クリニックに収容された36匹
①【地域アンケートの実施】
私たちは今年、尾道市内の複数地域で、
「外猫(野良猫)に関するアンケート」 を町内会と協力して実施しています。
質問内容は
- 猫の頭数
- 餌やりの有無
- ふん尿・鳴き声などの被害
- 地域猫活動に対する意識
- 相談窓口の必要性
- など多岐にわたり、
- 住民の"生の声"をデータとして可視化した初の取り組みでした。
このアンケートをもとに、
「うちの町内会でもきちんと向き合おう」
と決意し、町内会として地域猫活動を行っています。
行政任せでも個人任せでもなく、
"地域が主体となって動き始めた"重要な変化 です。
②【相談対応】
今回の案件も、アンケートで問題が顕在化した地域のひとつでした。
現行クリニックから片道30分ほど離れた、島嶼部の高齢者の方から
「猫を連れて来たいけれど、自分では無理なんです」
という相談も入りました。
- 捕獲できない
- 搬送できない
- 猫は増えて困っている
- 苦情も出始めている
こうした状況は、実際には多くの地域で起きています。
③【捕獲】
高齢者は自ら捕獲できない方が多く、
出向くため捕獲には回数を要します。
●毎週土曜は仕事後に複数現場へ
●日曜早朝
●夕方〜夜の巡回捕獲
今回は 36匹 と数が多く、
2〜3地域にまたがる広い範囲での捕獲となり、
メンバーと2手に分かれ作業しました。

④【搬送】
クリニックまでは 往復1時間以上の場所も少なくありません。
頭数が多いため、
様々な場所の搬送 が必要でした。
また、高齢者からは
「年金暮らしなので安くしてほしい」
という打診もあり、
地域を支えるための経費の圧迫 という現実も突きつけられます。
⑤【手術現場は"人獣共通感染症のリスク"と隣り合わせ】
外猫の手術は非常に感染リスクが高い活動になります。
麻酔が十分に効かないまま突然噛まれることがあります。
噛傷には
- パスツレラ症
- カプノサイトファーガ感染症
- 破傷風
- SFTS(重症熱性血小板減少症候群)
- など、人獣共通感染症のリスクが常に存在します。
術者・補助者は、
感染に細心の注意を払いながら、
高度な集中状態で処置を行っています。
昨日も咬まれてしまい、抗生剤を服用中です。

● 交通事故猫の断尾手術
今回の中には、尻尾が壊死し、
断尾しなければ命が危険だった子もいました。
細い血管・皮膚を丁寧につなぐ繊細な手術となりました。
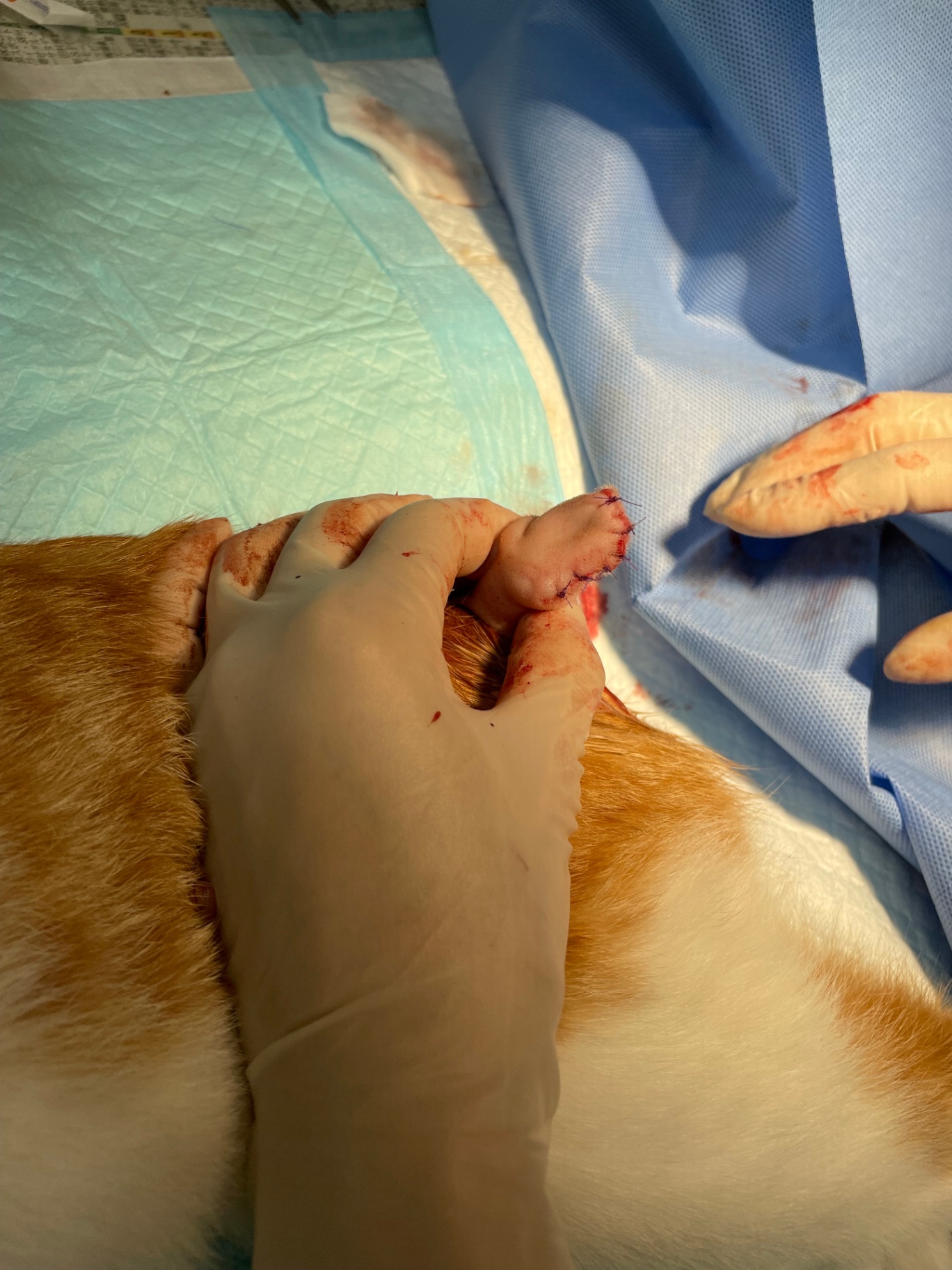
⑥【地域への効果】
36匹のTNRにより、
来年生まれるはずだった数百匹の"行き場のない命"を確実に防げます。
また、地域の悩みも軽減します。
- 発情期の夜鳴きの減少
- 糞尿・マーキングトラブルの改善
- 交通事故の減少
- 苦情・トラブルの予防
- 高齢者負担の軽減
さらに、
アンケートを経て町内会が動いたことにより、
住民全体の理解と参加が進みつつあります。
⑦【総括】
不妊去勢手術を進めていくことは、本当は"人"のためです。
人と猫が調和のとれた共生をしていくために、
欠くことのできない医療行為です。
私たちは「動物福祉を医療で提供する」団体として、
この地域に必要な"専門病院"の役割を担っています。
私は、この仕組みは本来、
各市町に1つずつ配置されるべき公共的インフラだと考えています。
皆さまのご支援が、
"命と地域の未来"の両方を支えています。
心より感謝申し上げます。
リターンを選ぶ
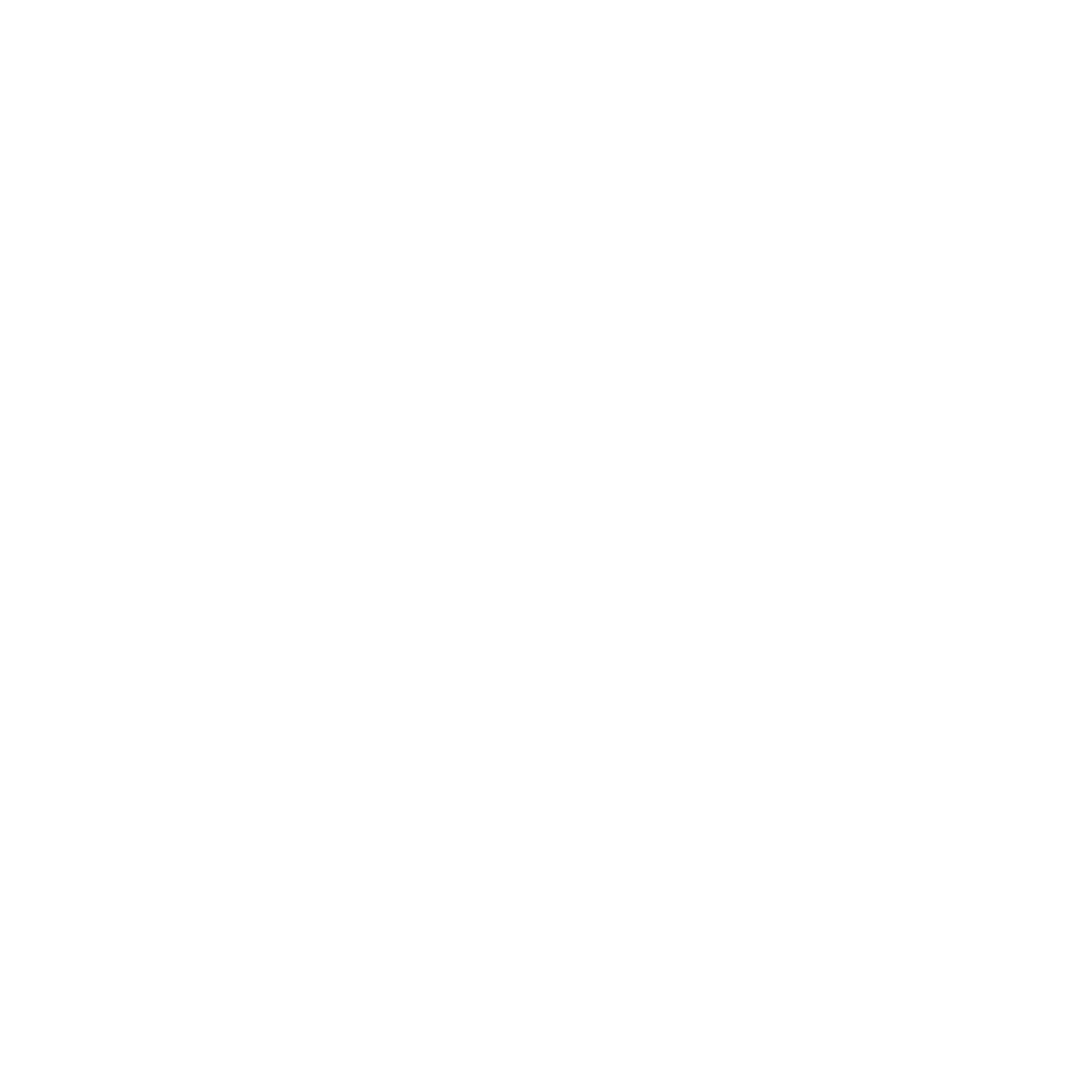
 画像処理中です...
画像処理中です...