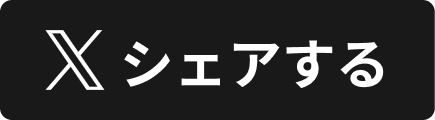住みよいまちづくり
広島県尾道発!猫の医療車「おの猫号」医療の力で人と猫の地域共生モデルを実現!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/11/23 22:00
代表理事から皆様へ『幼い頃に交わした約束』

数あるクラウドファンディングから、このプロジェクトにご賛同いただき
心より感謝いたします。
代表理事の箱﨑千鶴と申します。
まずは、ご挨拶に代えて、私がこの道を進むことになった原点からお話しします。
●幼少期に感じた「命の重み」
物心ついた頃から、私は"動くものすべて"に心を奪われていました。
犬、猫、鳥、カエル、亀…。
段ボールやみかんのコンテナに入れられて捨てられた犬や猫、
ケガをした子、弱った鳥、野良犬や野良猫。
見つけるたびに家に連れ帰りました。
父にしょっちゅう怒られました。
「お前のせいで小さな家が建つ!」
エサ代がとんでもないことになっていたからです。
今思えば、
幼い私は「かわいそう」だけで動き、
助けることだけを考えていました。
田舎の島・因島には野良犬も野良猫もたくさんいる時代でした。
ボロボロの野良犬の背中を見ては思っていました。
『この子たちは誰に頼っているのだろう?
誰もいないのだろうか?
どこで寝ているんだろう…』
気になって気になって、胸がざわついて仕方がなかった。
あの感覚は今でも同じです。
●小学生で「保護・譲渡」を始めた日々
この延長線で、私は小学生にしてすでに
"保護と譲渡"を始めていました。
自転車でフェリーに乗り、島外の譲渡先へ。
その後も心配で、放課後に"抜き打ちチェック"へ行った日も多かった。
毎日の日課は、
4畳半の犬小屋の掃除。
元は父が秋田犬を飼っていた場所で、自作の犬舎でした。
そこには私が拾ってきた犬がたくさんいました。
父に怒られるので、友達を巻き込んで掃除したこともあります。
頑張って譲渡しても、「毎年毎年、野良犬も野良猫も増えていく。」
いくら保護しても、保護しても追いつかない。
幼い私は初めてその壁に直面しました。
そして、犬や猫たちと過ごす中で、たくさんの『温もり』を感じました。
胸の奥にひとつの誓いを立てました。
「この子たちを守れる大人に必ずなる。」
●大人になり、医療の道へ進んで気づいた"根本の問題"
私は大人になり、動物の法律を学び、医療の道に入りました。
そこで知りました。
知識がなければ救えない命がある。
間違った善意は、命を傷つけてしまうことがある。
医療を学んだことで
「私のやり方には限界があった」
と痛感しました。
そして気づいたのです。
これは動物の問題ではなく、
"人側にある問題" が根本にあるのだ、と。
●人と猫が共に生きられる社会をつくる
私は、繁殖を止められない猫たちと、それに困る人々のために
繁殖をコントロールしていくことに注力しました。
『人を通じて動物福祉を実現する社会』
『人も猫もしあわせに暮らせる地域』
をつくりたい。
人が安心して暮らせれば、
動物もしあわせになります。
これは "プロジェクト" と呼ぶと難しく聞こえますが、
私にとってはただひとつ。
幼い頃に交わした約束を果たすだけ。
本当は、それだけです。
●お金という道具が社会を変える
私たちの医療×制度の構想を実現するには、
医療、相談対応、マンパワー、施設、車…。
どうしても"お金"という道具が必要です。
尾道の課題を解決するため、「おの猫号 × おの猫基金2026」 を
組み合わせた支援モデルを始動します。
医療従事者が中心となり、次の2本柱で地域猫問題にアプローチします。
1.おの猫号で交通格差を解消し、不妊去勢手術率を向上させる。
2.現場で感じた不具合を制度化し、町を住みやすくする。
本モデルは、「動物医療従事者が住民と協働して地域の仕組みを整える」という点で、
従来の支援とは大きく異なります。
医療従事者の知識とデータに基づく科学的管理を導入することで、円滑に活動を進めることが実現し、地域全体の負担を軽減します。
人にも猫にもやさしい尾道を加速させる力をください。
●最後にお願いです
あなたの1回のシェアが、
人のこころを救い、1匹の命をつなぎます。
どうか、
私たちの悲願のプロジェクトに
お 力を貸してください。
尾道の未来を変えるために。
ここにいる命を守るために。
尾道から始まるこの新モデルが、全国の地域猫問題の解決に向けたヒントとなることを願います。
リターンを選ぶ
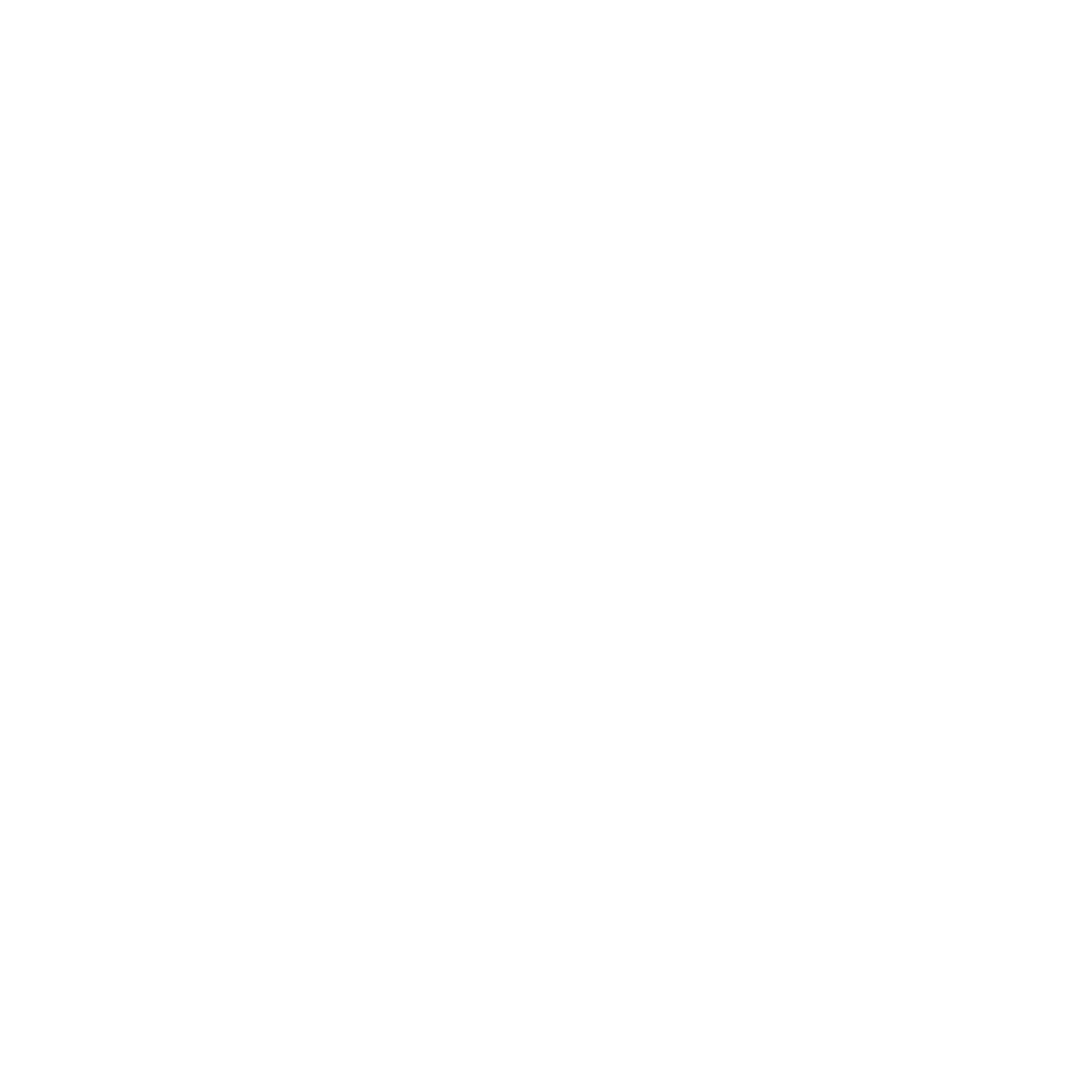
 画像処理中です...
画像処理中です...