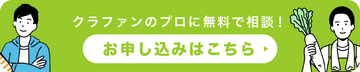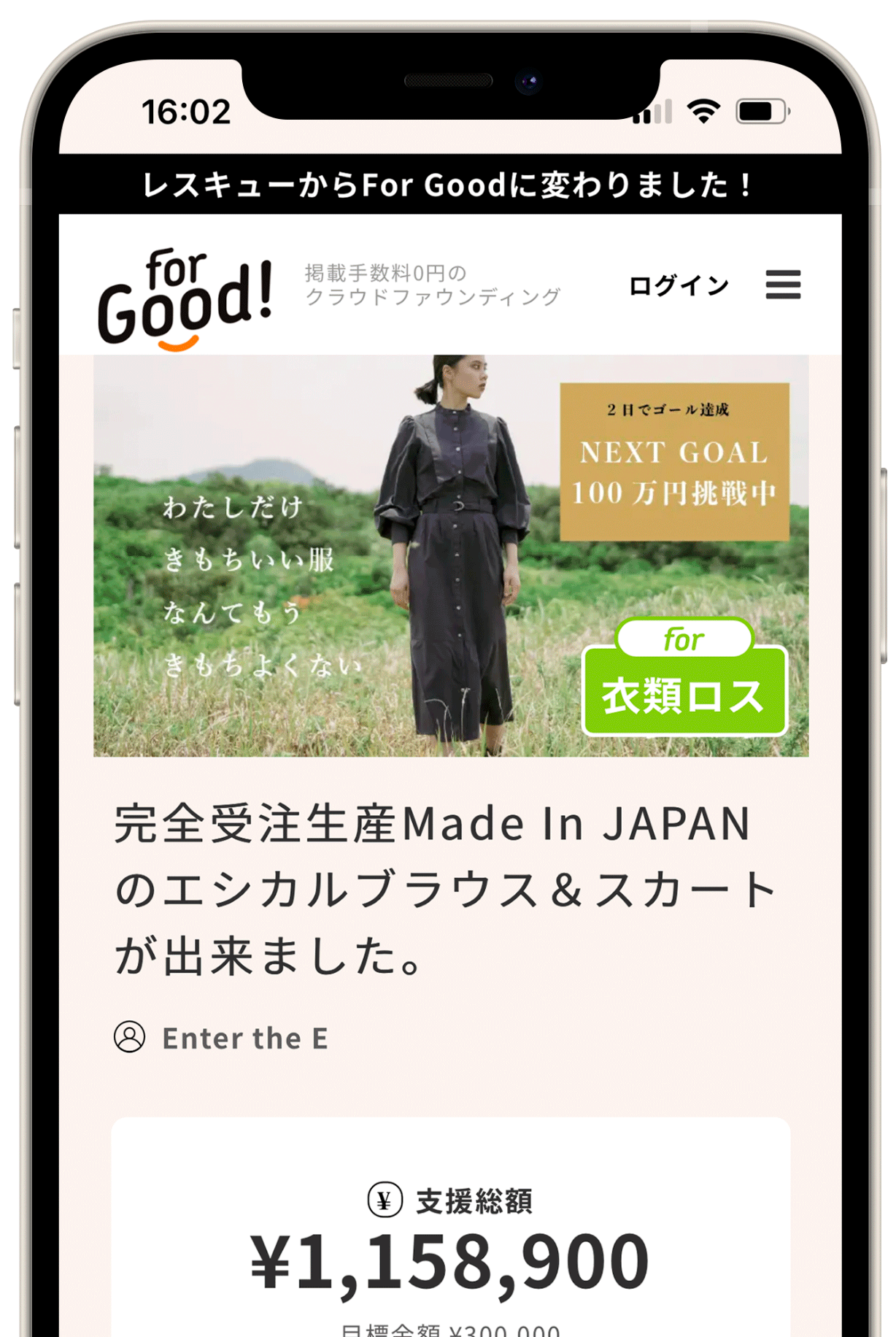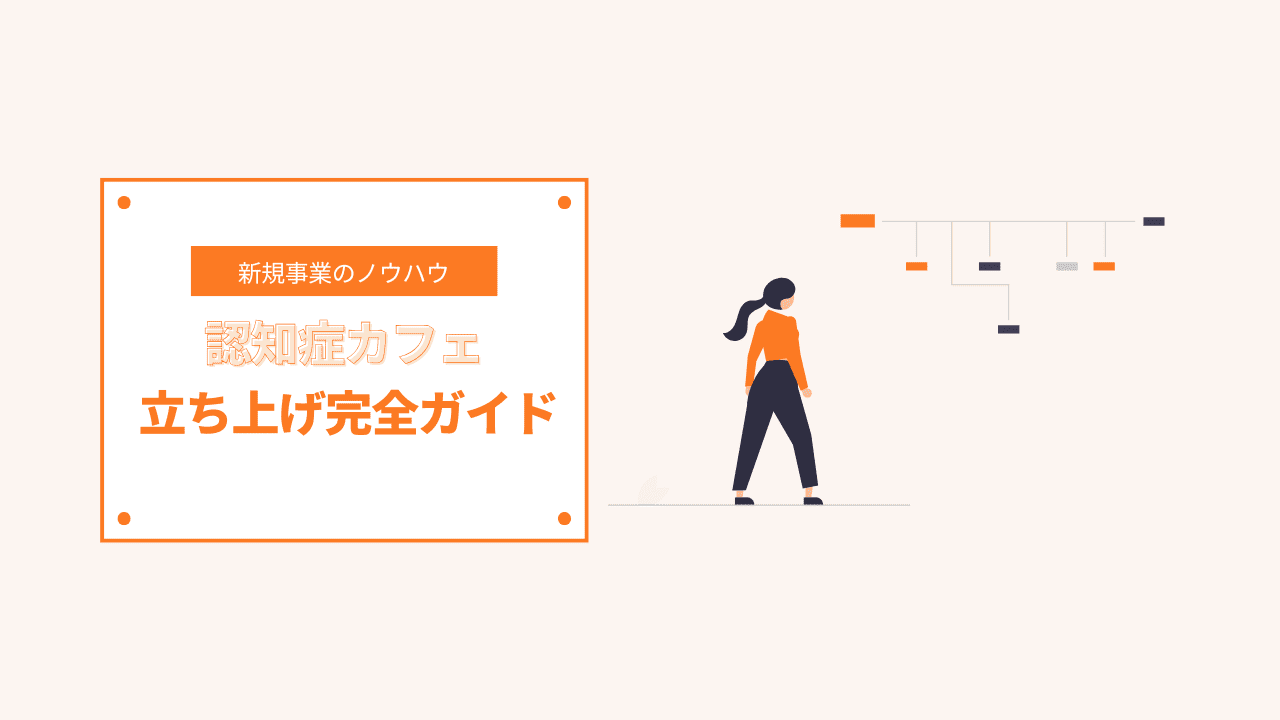
認知症カフェの立ち上げ方・成功例|必要な手続きから運営ノウハウまで解説
高齢化が進む中、認知症の方やその家族を支える「認知症カフェ」のニーズは高まっています。
認知症カフェは、当事者や家族、地域住民が安心して集い、交流を深めるための場所です。
しかし、立ち上げや運営には様々な準備とノウハウが求められます。
そこで本記事では、下記内容を解説していきます。
・認知症カフェは地域の支援拠点
・準備と運営の具体的な手順を紹介
・地域や関係機関との連携が重要
ぜひ最後までお読みいただき、認知症カフェの開設に向けた第一歩を踏み出してください。
クラウドファンディングにかかわる費用に関してはプロに直接聞くのが最も効率的。
実行者の手数料0円「For Good」のアドバイザー(キュレーター)に、無料で相談しませんか?
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
- 認知症カフェとは?
- 認知症カフェの目的・役割
- 認知症カフェの7つの基本要素
- 認知症カフェの10の特徴
- 認知症カフェの内容
- 認知症カフェ立ち上げの準備
- 認知症カフェ運営のノウハウ
- 認知症カフェ運営を成功させるために
- 認知症カフェの成功例
- 認知症にまつわるプロジェクト
- 福祉カフェのプロジェクト
- 高齢者のための運動支援プロジェクト
- まとめ
認知症カフェとは?

認知症カフェは、認知症の方やその家族が安心して過ごせる「憩いの場」です。
日々の生活において不安や孤立感を抱えやすい認知症の当事者や家族が、リラックスしながら交流し、情報を共有することで、心理的な負担を軽減する役割を果たします。
また、地域住民との橋渡しの場でもあり、認知症についての理解を深めることができる重要な場です。
地域全体で認知症の方を支える風土を築くためのきっかけとして、多くの認知症カフェが地域に根ざして運営されています。
悩み相談や世間話などができるコミュニケーションの場として、全国各地で運営されています。
オレンジカフェなど別の名称で呼ばれることもあります。
1997年にオランダで「アルツハイマーカフェ」として発祥し、2012年から日本でも推進。
2015年には新オレンジプランで全市町村への設置が目標とされました。2020年度時点で7,737カフェが運営されています。
💡カフェを開業する流れとは?
認知症カフェの目的・役割
 認知症カフェには、認知症当事者とその家族、地域住民や専門職が交流を通じて支え合える環境づくりという目的があります。
認知症カフェには、認知症当事者とその家族、地域住民や専門職が交流を通じて支え合える環境づくりという目的があります。
具体的には次のような役割が期待されています:
・認知症の方や家族が、専門職や地域の人々と安心して情報交換や意見共有ができる場を提供する
・介護を担う家族の心理的・実務的負担を軽減し、孤立を防ぐ
・認知症という病気に対する正しい知識や理解を広め、地域全体で支え合う土壌を育てる
こうした目的のもと、厚生労働省では認知症カフェのあり方として「7つの基本要素」と「10の特徴」を示しています。
認知症カフェの7つの基本要素
認知症カフェが果たすべき機能や空間のあり方を示す7つの要素は、当事者が心地よく過ごし、地域とのつながりを深めるためのヒントとなります。
これらを意識した運営は、参加者の満足度やカフェの継続にもつながります。
1. 認知症の方が病気を意識せずに自然体で過ごせる環境
2. 認知症当事者に役割や居場所があること
3. 社会とのつながりを持てる場であること
4. 自身の弱みを受け入れられる安全な空間
5. 認知症の方とその家族、そして地域の多様な人々が共に参加できる
6. それぞれのペースに合わせて関わり方を選べる柔軟性
7. 人と人とのつながりを促す仕組みが整っていること
これらは、認知症の方が「ただ利用する」のではなく、自らがその場を形作る一員として関われるような設計思想を反映しています。
認知症カフェの10の特徴
さらに、厚生労働省は認知症カフェの「具体的な姿」を示す10の特徴を挙げています。
これらは実際の運営場面で配慮すべき視点をまとめたもので、カフェを通じて地域全体に良い影響をもたらすことを目指しています。
1.認知症の方とその家族が安心できる居場所
2.気軽に相談ができる環境
3.思いや悩みを率直に話せるスペース
4.家族の生活リズムを尊重しながら利用できる
5.当事者の声が社会へ届く場となる
6.地域住民が認知症に触れるきっかけになる
7.認知症について学ぶ場としての役割
8.専門職がフラットに関わり、違った側面を理解できる場
9.スタッフにとってやりがいを実感できる場
10.将来、誰もが安心して利用できる地域資源となる
この10の視点を持つことで、認知症カフェは単なる「場」ではなく、地域に根ざした共生のプラットフォームとして育っていきます。
認知症カフェの内容
認知症カフェで行われることはさまざまで、運営団体によって異なります。ここでは、認知症カフェでよく行われている内容について解説します。
参加者同士の交流
認知症カフェの代表的な役割が、参加者同士がお茶やお菓子を楽しみながら自由に交流することです。
気軽な会話から情報交換、困りごとや相談がある場合は専門家への相談も可能です。
一般的なカフェと同じように、利用者が主体的に活動できるところが多いでしょう。
運動や趣味などのセミナーやイベント開催
認知症進行や運動機能低下を予防するプログラムとして、簡単なエクササイズや体操のイベントを開催しているカフェもあります。
また、音楽鑑賞や舞台鑑賞、カラオケ大会など趣味のイベントもよく行われ、興味のある人は自由に参加できるでしょう。
話し合いや相談会
認知症カフェでは、当事者や家族の悩みを解決する相談会もよく開催されています。
看護師や介護福祉士など専門家による勉強会や相談会も多く、適切なアドバイスが得られる機会です。
カフェでお茶を楽しみながら、気軽に相談できるでしょう。
認知症カフェ立ち上げの準備

認知症カフェの成功には、しっかりとした準備が欠かせません。
ここでは、カフェを立ち上げるために必要な基本的な準備について解説します。
1. 目的・理念の明確化
・支援対象者や提供したい場のイメージを具体化
・カフェの方向性やコンセプトを設定
2. 運営体制の構築
・ボランティアや専門スタッフの役割を決定
・安定した運営のための体制づくり
3. 資金調達
・自己資金の確保
・クラウドファンディングや助成金の活用
4. 場所の選定
・地域住民が集まりやすい場所を選ぶ
・利用者がリラックスできる環境づくり
5. スタッフの確保と研修
・認知症に関する知識を持ったスタッフの採用
・スタッフ研修でサポートスキルを向上
6. 利用可能人数の設定と開催日時の決定
・会場の広さやスタッフの配置状況に応じて、無理のない利用人数を決定
・開催日時は、地域の高齢者や家族のライフスタイルを考慮して決定
月に1回〜2回、1回2時間程度の開催が多く見られますが、平日昼間が利用されやすい傾向にあります。
7. PR活動(広報誌、回覧板、SNS、病院等との連携)
・地域の広報誌や町内会の回覧板への掲載、地域包括支援センターや病院、福祉施設との連携による紹介
・SNSやホームページを活用して、活動の様子や開催情報を発信することで、若い世代や介護に関心を持つ層にもアプローチ
認知症カフェの存在を地域に知ってもらうことが、継続的な参加者の確保につながります。
以上のように、認知症カフェの立ち上げには明確な目的の設定、運営体制の構築、資金調達、場所選び、スタッフの確保と研修が必要です。
しっかりとした準備を進めることで、地域に根ざした温かいカフェを実現することができます。
💡クラウドファンディングで資金調達する方法を解説!
認知症カフェ運営のノウハウ

認知症カフェを運営するためには、参加者が心地よく過ごせる場を提供し、効果的な集客を行うことが求められます。
ここでは、運営を円滑に進めるためのノウハウについて解説します。
1. イベント・活動内容
・認知症の方やその家族が楽しめるレクリエーションやワークショップを企画し、参加者同士の交流を促進しましょう。
2. 集客方法
・地域の掲示板やSNS、広報誌を活用し、幅広い層に情報を届ける工夫が大切です。また、地域の病院や福祉施設との連携も効果的です。
3. 参加者への配慮
・認知症の方がリラックスできる環境づくりを心がけ、家族の方の相談にも丁寧に対応することが重要です。
4. トラブル対応
・参加者の体調不良や突発的な行動に備え、スタッフ全員が基本的な対応方法を理解し、迅速に対応できる体制を整えましょう。
5. 会計処理
・参加費や寄付金など、収支の管理を透明に行い、必要に応じて専門家にアドバイスを受けることを検討しましょう。
💡【成功事例8選】福祉に関するクラウドファンディングの事例をご紹介!
認知症カフェ運営を成功させるために

認知症カフェを成功させるためには、地域や関係機関との連携を強化し、効果的なPR活動を行うことが重要です。
以下に、そのためのポイントをまとめました。
地域や関係機関との連携
・地域住民との信頼関係
認知症カフェを地域の一部として根付かせるために、地域住民との信頼関係を築くことが大切です。住民参加型の活動を取り入れ、地域全体での支援意識を高めましょう。
例: 地域住民を対象とした認知症理解講座や、ボランティア活動の導入
・行政や関係機関との協力
行政や医療・福祉関係機関と協力し、利用者への適切なサポート体制を構築しましょう。行政の支援を受けることで、資金的助成やイベント周知などのサポートが期待できます。
PR活動の重要性
・地域メディアやSNSの活用
カフェの活動内容や意義を積極的に発信し、広く認知度を高めることが重要です。定期的な情報発信によって、新たな参加者や支援者を引きつけることが可能です。
💡【成功例6選】クラウドファンディングで地域活性化を成功させた事例をご紹介!
認知症カフェの成功例
認知症カフェは各地で展開されていますが、運営がうまくいっている例には共通する工夫があります。以下はその一部です。
・地域全体を巻き込んだ運営体制:
地域包括支援センターや地元企業、大学と連携し、カフェの開催だけでなく地域全体に認知症への理解を広げている事例があります。
・テーマ性のあるプログラムの実施:
例えば「音楽療法の日」「家族ケアの日」など、毎回異なるテーマを設定し、参加者の興味関心を引き続けているカフェもあります。
・クラウドファンディングの活用:
運営資金を地域住民や企業からの支援でまかない、資金面でも共感とつながりをつくっているケースもあります。
For Goodを通じて資金を集めたカフェでは、支援者が実際にカフェを訪れ、新たな関係性が生まれました。
・定期的な振り返りと改善:
スタッフ間で毎回の振り返りを行い、小さな改善を積み重ねている点も成功要因の一つです。
成功している認知症カフェは、単なる「居場所」ではなく、地域と一体となった支援のハブとして機能している点が特徴です。
認知症にまつわるプロジェクト
〈プロジェクトの詳細〉
■沖縄版認知症予防DVDを作りたい!
■達成金額 ¥449,000
■目標金額 ¥400,000
■支援者数 84人
■詳細はこちら
https://for-good.net/trn_project/44567
福祉カフェのプロジェクト
■「福祉をひらく!」ドーナツカフェ「ちかつの窯」をとこなめにOPENします!
■達成金額 ¥1,258,000
■目標金額 ¥1,000,000
■支援者数 126人
■詳細はこちら
https://for-good.net/project/1000714
高齢者のための運動支援プロジェクト
〈プロジェクト詳細〉
■運転が困難な高齢者やアスリートを目指す子どもにジムへの送迎支援を!
■達成金額 ¥1.842.000
■目標金額 ¥2.000.000
■支援者数 84人
■詳細はこちら
https://for-good.net/project/1000972
これらのプロジェクト事例からも分かるように、認知症や福祉にまつわる取り組みが、多くの共感と支援を集めていることがうかがえます。
地域への思いや課題解決への意志が、クラウドファンディングという形を通して具体的なアクションとなり、社会に良い循環を生み出しています。
まとめ
認知症カフェは、認知症の方やその家族にとって、憩いの場でありながら、地域住民との交流の場としても重要な役割を担っています。
本記事を参考に、認知症カフェの立ち上げを具体的に検討し、地域の中で温かい支援の場を築いていく一助となれば幸いです。
ForGoodでは、クラウドファンディングにかかわる相談を無料で相談中!
税金や細かな費用面の相談もぜひお気軽にお問い合わせください。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!