FOR
水俣病研究原点の出版
水俣病研究の原点『企業の責任』〈増補・新装版〉出版、「安全確保義務」の確立を!

現在の支援総額
¥3,918,500
目標
¥2,700,000

支援者
308
人

残り
終了

みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
プロジェクトのポイント
1.水俣病研究の原点である『企業の責任』の〈増補・新装版〉を出版
2.水俣病第一次訴訟判決の理念に、いまあらためて光を当てる
3.これからの企業や行政に「安全確保義務」の倫理を定着させる
プロジェクトの詳細
支援金の使い道
さいごに
PROFILE

石風社 代表 福元満治
死者の鎮魂のために 福元満治(図書出版石風社代表)
私が学生だった頃、水俣病問題に関わりました。そのことが私のその後の人生を決定づけ、アフガニスタン で用水路を造った中村哲さんの事業にまで関わることになりました。石牟礼道子さんは、水俣病の患者さんのことを「かつて一度も歴史の面に立ちあらわれることなく、しかも人類史を網羅的に養ってきた血脈」と記しています。その血脈、つまり累々たる無名の死者の思いを背に闘われたのが、第一次水俣病訴訟だったと思います。だからこそあの裁判は、「損害賠償請求」に止まらず「人としての道義」をも問う訴訟になったのです。『企業の責任』は、利益追求を優先し、人の命や自然環境を破壊したチッソの「罪と嘘」を完膚なきまでに暴きました。本書の「安全確保義務」の法理論が企業・行政の倫理として定着することで、水俣病による死者たちの鎮魂になればと祈ります。
リターンを選ぶ
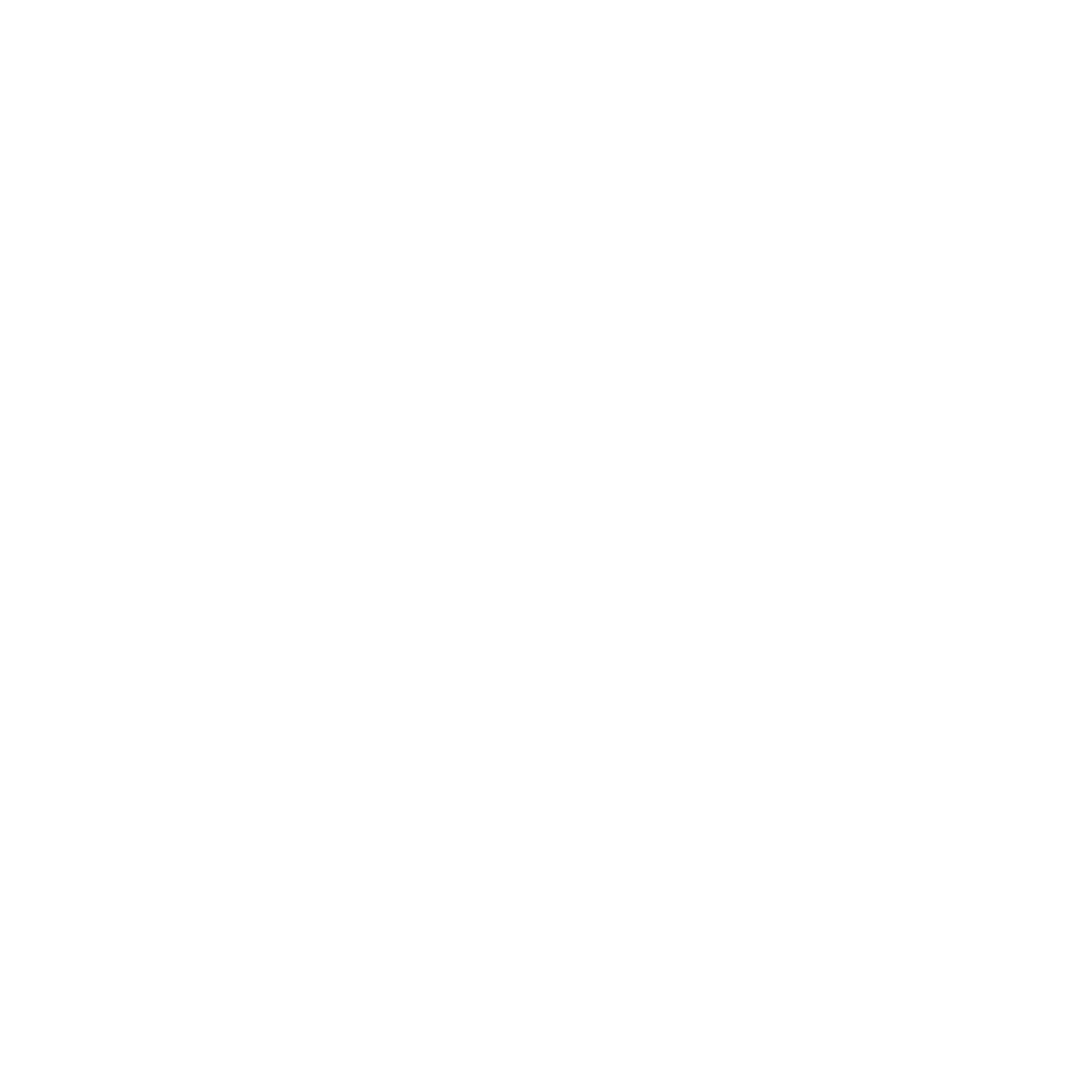
 画像処理中です...
画像処理中です...







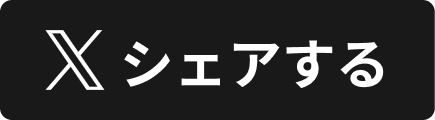








最新の活動レポート
2025.03.10
本日23時59分で終了です。応援ありがとうございました。
本日23時59分で終了です。応援ありがとうございました。1月10日にスタートした、クラウドファンディングが、本日で終了いたします。2ヶ月の長丁場でしたが、皆様の応援で第一次目標を達成し、第2次目...
2025.03.05
本日NHK(福岡・ロクいち)で放映予定。全国NHKプラスで視聴できます。
本日NHK(福岡・ロクいち)で放映(18時半過ぎ)予定です。全国NHKプラスで視聴できます。7分ほどの放映ですが、富樫貞夫先生のインタビューも出ます。ご覧いただければ幸いです。あと5日になりました。セ...
2025.03.04
リターン・熊本県下の高校に「企業の責任」と「核心・〈水俣病〉事件史」を寄贈
リターンとして、熊本県下の高校と、鹿児島県の出水、阿久根の高校図書館に、「企業の責任」と「核心・〈水俣病〉事件史」を寄贈します(計77校)。皆様の応援のおかげで、第一次目標を達成し、第2の目標であ...
みんなの応援コメント
やよい
2025年3月10日
長いこと読みたいと思っていました。応援しています!
石邨善久
2025年3月9日
門司港のグリシェンカフェさんの投稿でこちらの取り組みを知りました。はなはだ微力ではありますが応援させていただきます!
緑青
2025年3月9日
「企業の責任」〈増補・新装版〉が市販されて、現在も続く水俣病問題、あまたの患者・家族・支援者の皆さんの苦しみと闘いが、広く知られますように。応...