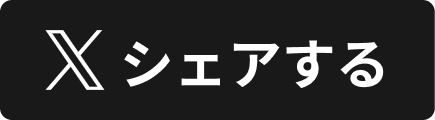熊野本宮の茶文化継承
甦りの聖地、世界遺産熊野本宮の音無茶。復活継承プロジェクト!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/10/6 16:19
「教師補」の認定をいただきました!

全国手揉み茶振興会より「教師補」の認定をいただきました😊ありがとうございます!
手揉み茶とは煎茶の原点とも言われる製法で、江戸後期(1738)に永谷宗園さんが京都、宇治田原の湯屋谷で生み出しました。この製法が現代でも受け継がれています。蒸した茶葉を焙炉(ほいろ)の上で、手作業のみで揉みながら乾燥させて作る伝統的な日本茶です。この伝統技術で作られるお茶は、針のように細長い形状と、繊細かつ力強い特別な旨味が特徴です。
資格にはランクがあり、私はまだ初段です。この先に教師、師範、茶匠とあり、茶匠となると全国で数名しかいません。まだまだ道のりは長いですが、一歩前進しました!
試験中も試験官から厳しい指導があり、手技だけでなく、手順も全て決まっているので、とても難しいです。今回受からせてもらえてほんとに有り難かったです。やっと形に残る一つの結果を出せたと感じています。
手揉み茶は国登録無形文化財にもなっており、師範、茶匠が揉んだ茶がそれに該当します。私はまだまだこれからで、順当に行っても10年先?くらいにしか師範にはなれません。
2023年の投稿にも書きましたが、本宮の茶は1854年(江戸時代)に下湯川村の掘文左衛門が宇治茶製法で製茶していたのを西谷村(現在の中辺路町)の大熊武平が伝習し、協力して製法を広めていきました。
明治3年には精選改良し、東京や神戸等で販売したそうで、当時は「熊野のハシリ茶」として大阪神戸で珍重されたそうです。(本宮町史より)
これがのちの本宮町の銘柄、音無茶になるわけです。
今では本宮町で煎茶を生産販売する者は私だけとなり、もちろん手もみ製茶が出来る者などいません。
この令和の時代に私は堀文左衛門になりたいと思っています。
一歩、一歩、堀文左衛門に近づいていきます!!!
リターンを選ぶ
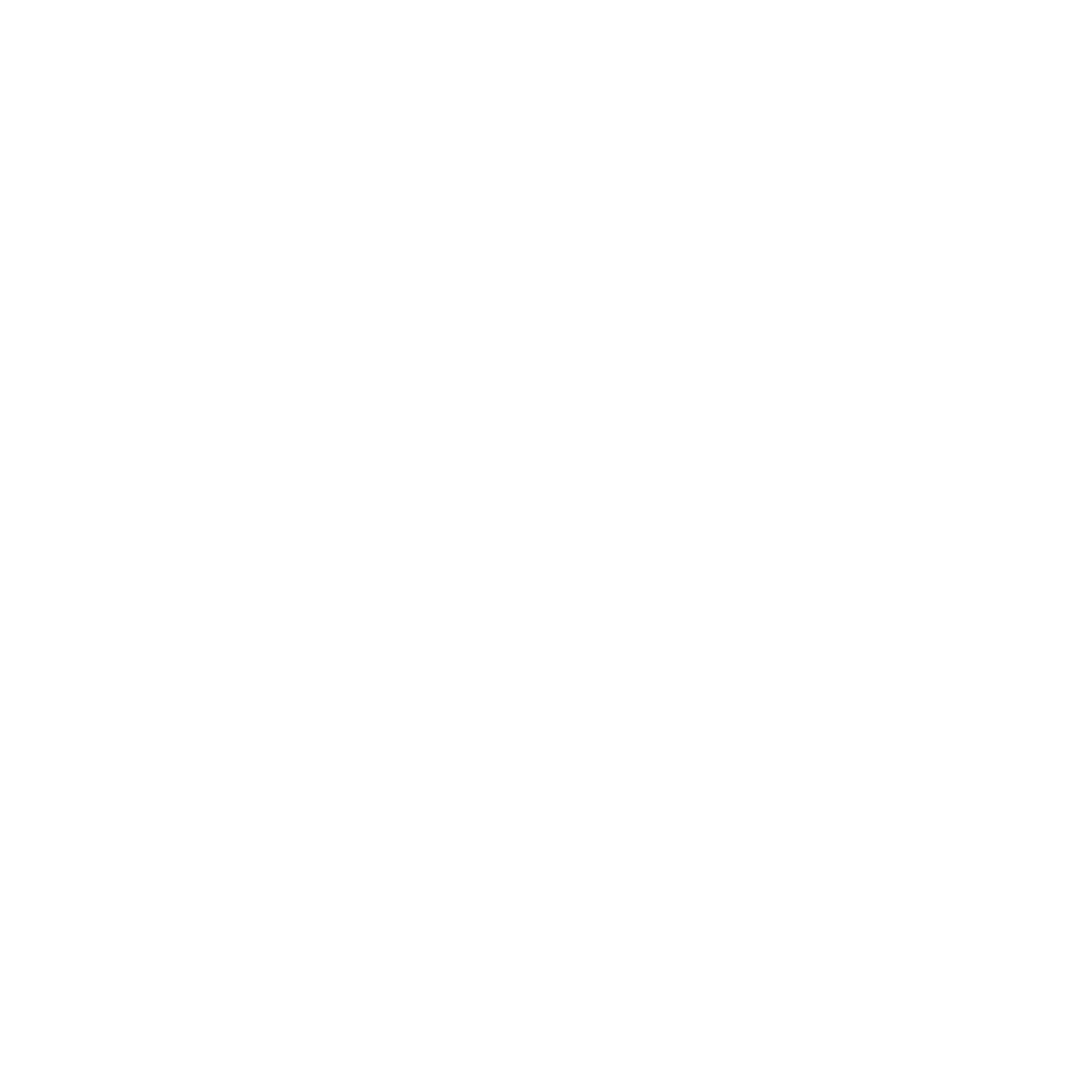
 画像処理中です...
画像処理中です...