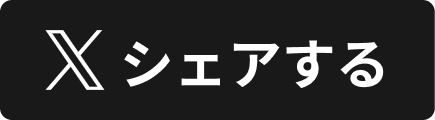傘の廃棄を減らす
静岡の伝統工芸を復活させたい!創業106年の傘屋がつくる伝統✖️革新の傘




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/10/9 20:30
創業106年の歴史。私たちが「傘づくり」を続ける理由

クラウドファンディング開始から1週間。
ご支援くださった皆さま、本当にありがとうございます。
少しずつではありますが、私たちの想いに共感いただき、応援の輪が広がっていることを心から嬉しく感じています。
今回は、本文では書ききれなかった「藤田屋の歴史」と「なぜ傘づくりを続けているのか」をご紹介します。
私たちの始まりは大正8年。
滋賀で傘づくりをしていた曾祖母・ノブが静岡に移り、曾祖父・怜司と共に創業しました。
当時の静岡は職人のまち。傘やその部材を扱う職人も多く、ものづくりの土壌が整っていたようです。

創業当初は和傘の製造と卸の仕事が中心で、一部の材料販売も行っていたそうです。
仕上げた傘を天日に干す光景は、街の風物詩でした。
黒い塀に色とりどりの傘が並ぶ――その景色を、私も見てみたかったと思います。
一方で、傘は天候に左右されやすく、「なぜそんな仕事を?」と問われることもあったようです。
それでも藤田屋は、細部まで品質と見た目の美しさにこだわり、「雨の日でも快適に出かけられる暮らし」を広めることを信条としていました。だからこそ誇りを持って、手を止めなかったのだと思います。
一方で、戦後は洋傘が主流となり、和傘職人は急速に減少しました。その中で、私たちも洋傘の技術を学びながら形を変え、時代に合わせて歩んできました。
しかし海外から安価な傘が大量に流入すると、国内生産は厳しくなり、やむを得ず一度傘づくりを休止しました。
やがて大量生産・大量廃棄が当たり前の時代に。
誇りをもった丁寧な仕事や、長く大切に使い続けることは意味が無くなってしまった。そんな風に思う時もありました。
それでも、創業100年を迎えたとき、改めて思いました。
「長く大切に使い続けられる一本をつくること」こそが、私たちの原点だと。
そこから再び、傘づくりを事業としてに復活させることを決めました。
静岡の伝統工芸と職人の技を融合させた私たちだけが作れる傘――それが『仁心 - nico -』です。

今後は再び工房を整え、若い職人を育て、静岡に傘づくりの文化を根づかせたい。
そして静岡のものづくりを世界へ広げていきたいと考えています。
これが藤田屋の歩みであり、傘づくりを続ける理由です。
これからの活動報告では、製作の裏側や職人たちの日常をお伝えしていきます。
引き続き、温かく見守っていただけたら幸いです。
リターンを選ぶ
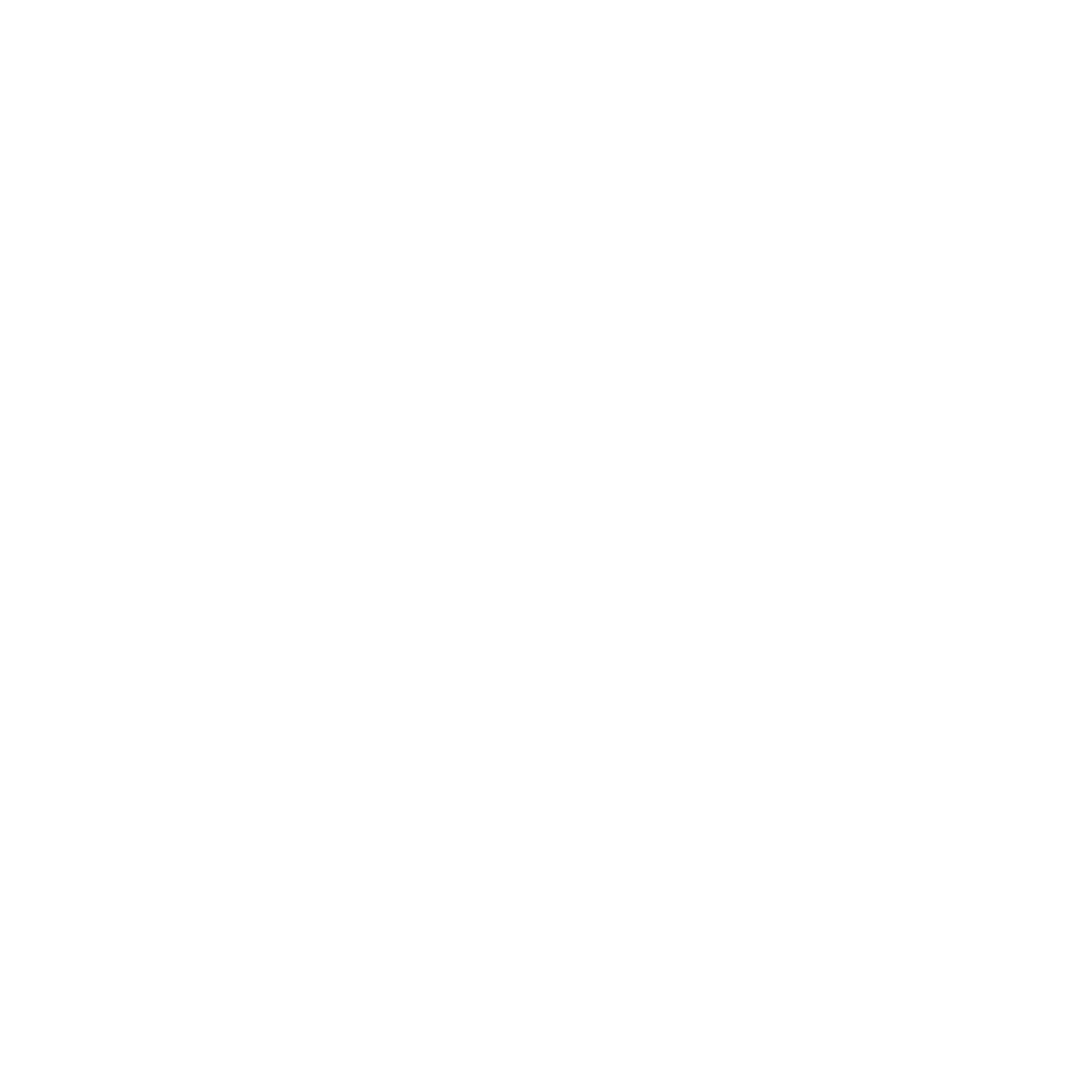
 画像処理中です...
画像処理中です...