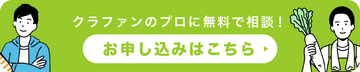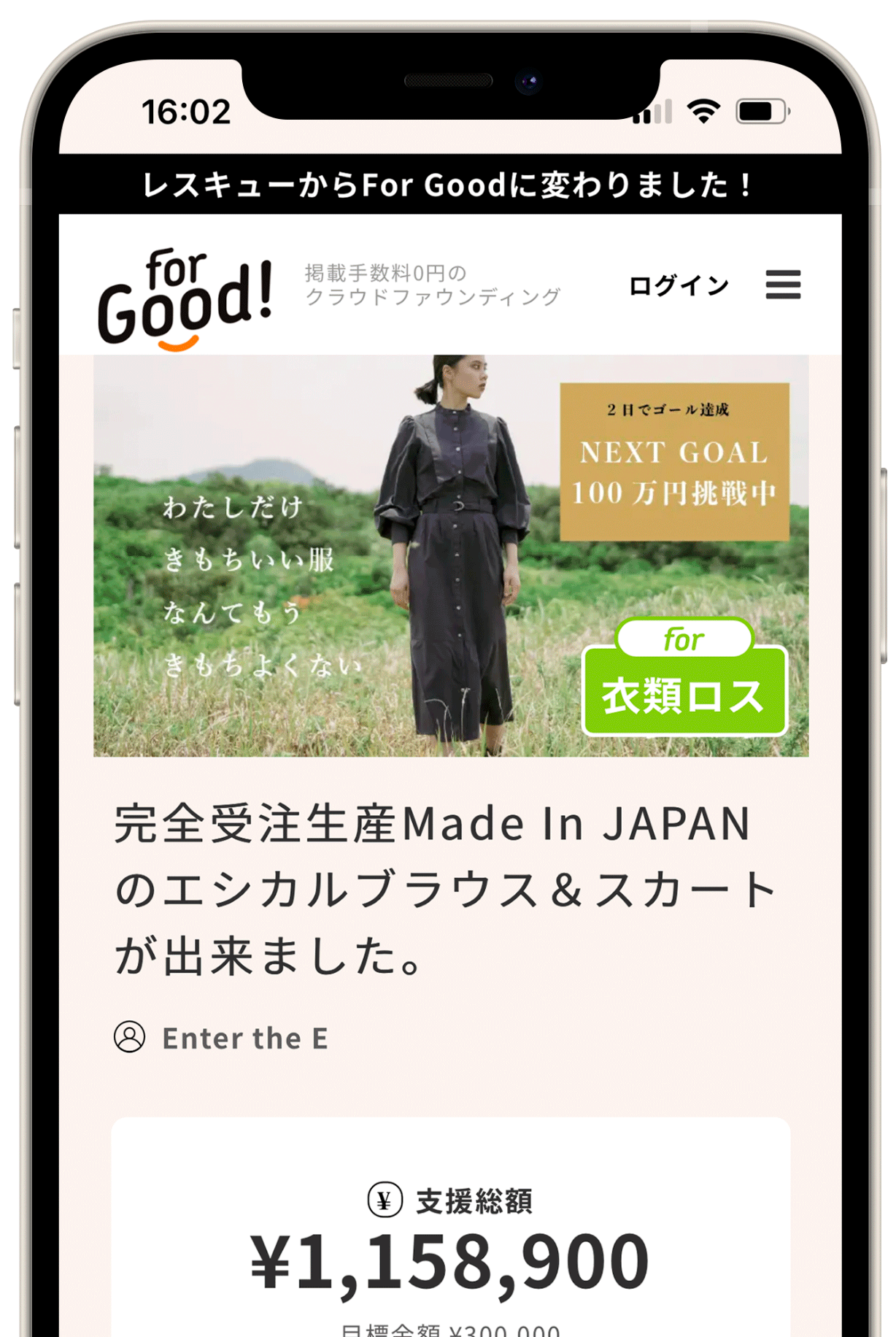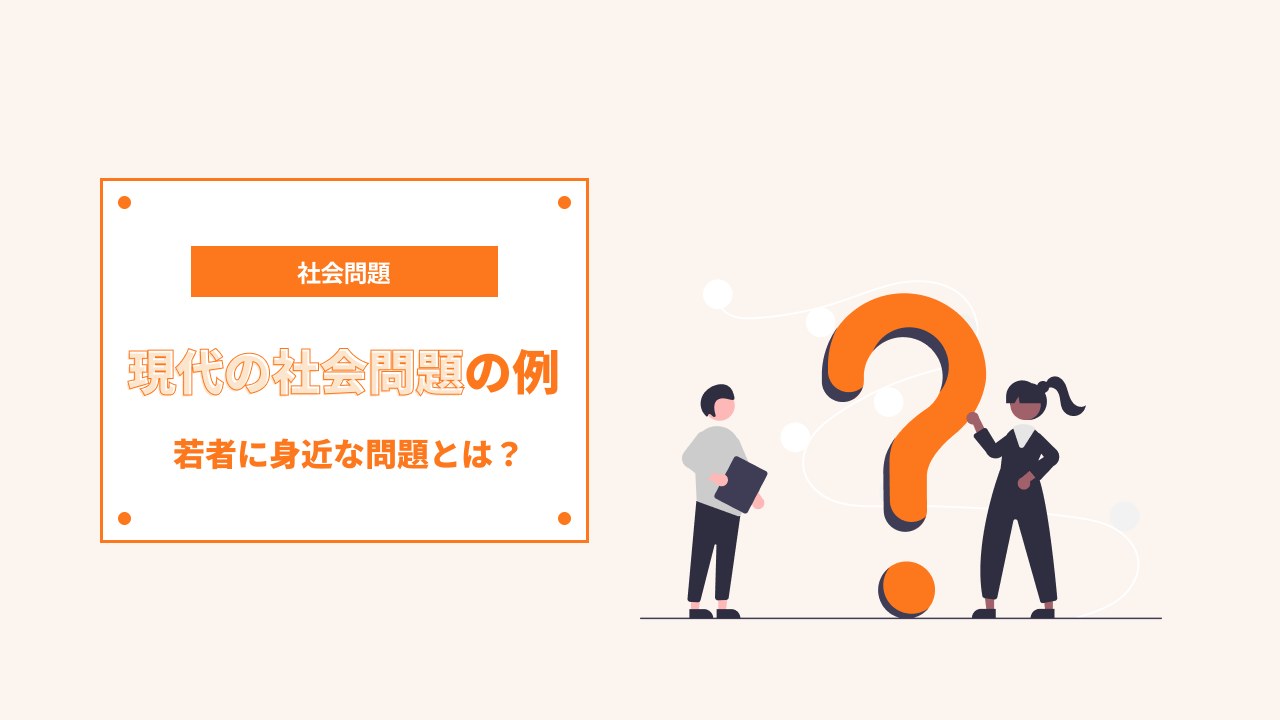
【日本版】現代の社会問題の例を紹介!若者に身近な問題とは?
日本では、社会問題が山積みであることはご存じでしょうか。一方で、いじめやジェンダー格差など、あなたの身の回りで起きている社会問題も多くあります。
ここでは、日本国内で懸念されている身近な問題について詳しく解説します。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!
目次
- 日本が直面している社会問題
- 1. 子どもの貧困問題
- 2. 地域の過疎化/都市への一極集中
- 3. 異常気象に関する問題
- 4. 労働の業務効率化・生産性に関する問題
- 5. 移民に関する問題
- 6. 環境問題
- 若者(Z世代の学生)に身近な社会問題
- 1. いじめ
- 2. 自殺問題
- 3. ジェンダー格差
- 若者(Z世代の社会人)に身近な社会問題
- 1. 過労問題
- 2. 奨学金問題
- 3. 年金問題
- 日本の社会問題に対して、私たちにできること
- クラウドファンディングで社会問題解決に取り組んでいる事例
- 【環境問題】学生向けに社会問題を解説する無料動画を100本制作
- 【エネルギー問題】ソーラーシェアリングによるテーマパーク建設
- 【教育問題】教員不足解消のため教師専門の求人サイトを運営
- 【発達児童受け入れ問題】発達児童向けデイサービス施設の設立
- 【少子化問題】新潟県上越エリアに助産院を新設
- 【貧困問題】フェアトレードによる紅茶葉の開発
- 【フードロス問題】規格外野菜を販売する無人店舗のオープン
- まとめ
日本が直面している社会問題
 私たちが住む日本において、深刻な問題は数多くあります。
私たちが住む日本において、深刻な問題は数多くあります。
ここでは日本で起きている社会問題と、それが及ぼす影響を解説します。
1. 子どもの貧困問題
日本は豊かな先進国である一方、およそ7人に1人の子どもが貧困状態であるといわれています。
日本での貧困とは、衣食住の確立が困難であり経済的に困窮している状況を指すことが一般的です。
また、貧困問題は教育格差にも影響を与えます。
塾や習い事に通えるかは親の経済力によって左右されやすく、育つ環境で教育の機会や質に差が出てしまうためです。
さらに、貧困家庭では金銭面や学習面で高校や大学への進学が厳しく、就職において不利に働く可能性があるでしょう。
そのため、子どもが将来結婚し子どもができたとしても貧困から抜け出せず、さらにその子どもも貧困から抜け出せない、という負の循環が考えられます。
2. 地域の過疎化/都市への一極集中
日本では都市部への人口流入が続く一方、地方では人口流出や出生数の低下などによって過疎化が深刻化しています。
近年の過疎化に伴い、地方で多くあげられる問題点を以下にまとめました。
・交通網の減少:人口減によって地域公共交通が衰退し車での移動が必要になったが、地方の高齢化によって高齢者運転の事故が増加している。
・空き地の増加:所有者の不在や高齢化で利用・管理されない土地が増え、治安の悪化や家屋の転倒などが懸念されている。
・山林の荒廃:人口流出によって山林の所有者が不明となり、荒廃が進行することで、野生動物の行動範囲が広がり農作物や人的被害につながるおそれがある。
3.異常気象に関する問題
日本では気候変動の影響により、異常気象や災害が深刻化しています。
猛暑や豪雨の頻発、台風の強大化、海面上昇などが主な問題です。
2024年の夏は特に猛暑で、熱中症リスクが高まりました。
農業でも、高温による米の品質低下や果実の着色不良が報告されています。
また、暖冬の影響で冬眠パターンが乱れたこと・食料源のブナやナラが凶作なことなど複合要因から、クマが餌を求めて人里に出没する事例も増加しています。
2023年には「アーバンベア」という言葉が流行語大賞になるほどです。
4.労働の業務効率化・生産性に関する問題
公益財団法人日本生産性本部の調査によると、日本の労働生産性は低迷しており、OECD加盟国中29位(34か国中)に位置しています。
主な要因は、長時間労働の常態化、デジタル化の遅れ、モチベーション低下です。
DXによる業務効率化が進められていますが、多くの企業では内向きの取り組みに留まっています。
AIやデジタルツールの活用が進む一方、レガシー企業では従来の慣行が根強く残り、情報リテラシーの格差も顕在化しています。
労働生産性向上には、プロセスの自動化、データ駆動型の意思決定、コミュニケーション改善が重要ですが、適切な評価制度の導入も課題です。
5.移民に関する問題
日本の移民政策は曖昧な状況が続いており、外国人労働者の受け入れ拡大と共に様々な課題が浮上しています。
埼玉県川口市では、クルド人コミュニティと地元住民との軋轢が深刻化し、ヘイトデモや犯罪問題が報告されています。
政府は2024年2月に技能実習制度を廃止し、新たな「育成就労」制度の創設を発表しました。
この制度は潜在的な永住者の増加を見込んでおり、日本の移民政策における転換点となる可能性があります。
一方で、外国人との共生や文化的な摩擦、労働環境の整備など、多くの課題が残されています。
6.環境問題
18世紀の産業革命以降、日本のみならず、徐々に世界規模で環境問題が悪化しており、現在では地球上に生息する生き物の存続危機や自然環境の破壊など、数々の問題が深刻化しています。
日本も例にもれず、対策が求められています。
さらに、環境問題がこのまま進行すると生物多様性の損失を引き起こし、今までの生態系が崩れてしまうといわれています。
以下に、環境問題を代表する5つの課題を表にまとめました。
| 地球温暖化 |
温室効果ガスの増加で熱の吸収量が増え、地球の平均気温が上昇すること。 |
| 海洋汚染 |
プラスチック類のポイ捨てや産業廃棄物の不法投棄、工業・家庭排出の流出など、人間が出すゴミで海水を汚すこと。 |
| 大気汚染 |
排気ガスやPM2.5、光化学オキシダントなどの発生で大気中の空気を汚すこと。 |
| 水質汚染 |
河川や湖、地下水などが地球温暖化や工業・家庭排水によって汚染されること |
| 森林破壊 |
人間の土地開発や農地への転用などによる大量の木の伐採・焼き畑農業が原因で、自然の力には元に戻れないほど森林を破壊してしまうこと。 |
身近な問題でいうと、オーバーツーリズムにおけるごみ問題が挙げられます。インバウンド需要の影響で、日本の観光地では道にゴミが散乱する事態が起きています。
ゴミ箱の設置や、看板ルールなど、行政でも取り組みはなされています。
「ゴミの持ち帰り専用紙袋で観光地のゴミのポイ捨てを無くし観光地の景観を守りたい!」というプロジェクトでは、「持ち帰る」対策に取り組んでいる方がいらっしゃいます。
若者(Z世代の学生)に身近な社会問題
 現代では、学生を中心とした社会問題が増加傾向にあり、今後の社会にとって極めて深刻な状況であるといわれています。
現代では、学生を中心とした社会問題が増加傾向にあり、今後の社会にとって極めて深刻な状況であるといわれています。
今も身近なところで起きるいじめやジェンダー格差など、ここでは現代の学生を取り巻く社会問題について詳しく解説します。
1. いじめ
現代では学生を中心にいじめが増加傾向にあり、文部科学省の調査によると、小中高等学校と特別支援学校でのいじめの認知件数は681,948件あることが分かりました。
これは前年度に比べて66,597件の増加であり、いじめの急増が深刻な社会問題に発展しているといえます。
また、日本労働組合総連合会が若者を中心に社会運動調査を行った結果、関心のある社会問題で回答した人が多かったものの一つが「いじめ」でした。
いじめのなかでも深刻化しているものは、インターネットを使った誹謗中傷です。
現代ではスマートフォンが普及し、気軽にSNSを利用する若者が増えた一方で、それを介して誹謗中傷や悪口を投稿するなどのいじめが多く見受けられます。
2. 自殺問題
日本では若者の自殺が増加しており、極めて深刻な問題です。
なかでも学校問題を原因とした10代の自殺率が増加傾向にあります。
また、文部科学省の調査によると、大学生の自殺の背景には学業不振や進路に関する悩みが多いことが分かりました。
自殺問題は学生や若者からの関心が比較的高い一方、若年層の自殺者数は年々増加しており重大な社会問題といえます。
3. ジェンダー格差
ジェンダー格差とは、男女の違いで生じる格差のことです。
日本では、男女間での雇用形態の差や役職の差など、社会的なジェンダー格差が多いといわれています。
また世界経済フォーラムによって、健康・教育・経済・政治の分野において男女差を表す「ジェンダーギャップ指数」が算出され、これらのデータを元に世界各国のジェンダー格差がどれほどか確認することができます。
2024年6月12日に発表された結果では、日本におけるジェンダーギャップ指数は146カ国中118位と、低迷していることが分かりました。
日本では教育や健康分野では男女平等である一方、男女の勤労所得の差に加え、政治分野においては大幅に男性が多く社会的な課題といえます。
若者(Z世代の社会人)に身近な社会問題

若者の社会人にも、身近な問題は多くあります。
まさに今、これから解説する社会問題に直面していたり、周りの人が悩んでいたりするケースも多いのではないでしょうか。
ここでは、社会人である若者の多くが抱えている問題を説明します。
1. 過労問題
長時間労働は、〜時間以上の労働と明確な基準はありません。
一方で、労働基準法で定められている法定労働時間「週40時間、1日8時間」を超えると時間外労働(残業)と判断されます。
一般的に、時間外労働を大幅に超えている状態を長時間労働と呼び、現在の若者から懸念・問題視されています。
現代では働き方の多様性が広がり、若者を中心にワークライフバランスが重視されるようになりました。
一方で、激務による過労死や残業文化が根付いているため過労問題が身近になり、若者にとって関心の高い社会問題の一つです。
2. 奨学金問題
現在の若者のおよそ3人に1人が、機構から奨学金を借りているといわれています。
また、奨学金のほとんどが貸与型といわれており、大学卒業後に働きながら数年〜数十年かけて返済するケースが一般的です。
利息と延滞金が膨大な負担となり、返しても元金が減らないことも少なくありません。
このため、結婚や出産などのライフプランにも大きく影響を与えており、若者を中心に社会問題となっています。
3. 年金問題
年金問題とは、公的年金の運用が悪化している状態のことを指します。
年金積立金における運用利回りの低下や、急速な少子化で財政が不安定化していることが主な原因としてあげられます。
さらに、現役世代への負担が増加している一方で、今後の年金額は目減りすると考えられるでしょう。
そのため、現在の高齢者のほうが現役世代よりも年金を多く受け取れる仕組みであり、問題視されています。
日本の社会問題に対して、私たちにできること
社会問題に気付き、現状を知ることがすべての始まりです。
1.SNSや信頼できるメディアを通じて社会課題の情報を収集する
2.正確な情報を理解し、デマを拡散しない
3.多様な視点から社会問題を学ぶ姿勢を持つ
ここまで読み進めている方はぜひForGood magazineをご覧ください。
社会課題に取り組む人たちを数多く紹介しており、「社会課題にみんなで取り組むメディア」を目指しています。
現状を知ったら、ぜひ小さな行動から始めてみてはいかがでしょうか。
1.支援団体へ寄付する
2.ボランティア活動へ参加する
3.コミュニティで課題解決へ関わる
4.SNSを通じた社会課題を発信する
クラウドファンディングで社会問題解決に取り組んでいる事例
ここからは実際に社会問題への対策を行なっている方々が、ForGoodのクラウドファンディングを利用して資金集めをされているケースについてご紹介します。
真剣に社会問題と向き合いたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
【環境問題】学生向けに社会問題を解説する無料動画を100本制作
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
【社会問題を楽しく学べる】 動画100本を無料で学生に届けたい!
■達成金額
¥5,151,100
■目標金額
¥2,500,000
■支援者数
516人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/trn_project/22952
学生向けに、環境問題を中心として社会問題を解説する動画を100本作成して無料公開しようというプロジェクトです。
目標金額であった250万円を超えて500万円以上を集め、動画を1カ所でまとめて見られるWebサイトを作成予定です。
【エネルギー問題】ソーラーシェアリングによるテーマパーク建設
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
「食とエネルギーのテーマパーク」を、ソーラーシェアリングでつくりたい
■達成金額
¥7,006,000
■目標金額
¥3,000,000
■支援者数
351人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1001111
ソーラーシェアリングとは農地に太陽光パネルを設置し、発電と農業を同時に行なう仕組みのことです。このプロジェクトはソーラーシェアリングのモデルとなる農園を作り、さらに食とエネルギーについて学ぶテーマパークを建設するものです。
1年を通じてブドウ・イチジク・レモンを栽培し、ソーラーシェアリングによる農業を学びながら体験できる場所として、2025年夏に竣工開始予定です。
【教育問題】教員不足解消のため教師専門の求人サイトを運営
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
先生の求人サイト「ミツカルセンセイ」で、全国の教員不足解決に貢献したい。
■達成金額
¥1,537,000
■目標金額
¥1,000,000
■支援者数
192人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000751
現在、教員不足が常態化し生徒にも教員にも負担がかかっています。
教師専門の求人サイトを制作し、教師を志望しながら働く場所やタイミングが見つからないいわゆる“潜在教員”に、求人情報を届ける手段を増やすことが、このプロジェクトの目的です。
情報は地域限定ではありますが、すでにこのサイトは運営が始まっており今後の活用が期待されています。
【発達児童受け入れ問題】発達児童向けデイサービス施設の設立
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
畑付き放課後等デイサービスを作りたい!@大阪・十三
■達成金額
¥1,836,000
■目標金額
¥1,200,000
■支援者数
162人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1001126
いわゆる発達障害の児童に、基礎能力の向上や社会性の取得支援を農業を通じて行なう施設の開設が、このプロジェクトの目的です。
家庭と学校以外でも子どもが抱える問題に対処できる施設として、子どもを取り巻く環境の改善を目指しています。
この施設は2025年2月にグランドオープンし、同月3日より子どもの受け入れをスタートしました。
【少子化問題】新潟県上越エリアに助産院を新設
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
あなたの幸せなお産・育児に寄り添いたい!新潟県上越エリアに助産院を!
■達成金額
¥1,011,000
■目標金額
¥500,000
■支援者数
75人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000633
お産そのものの支援ではなく、妊娠期から産後に至る時期のケアや支援をする助産院を新設するプロジェクトです。
この時期の不安を取り除く相談相手や、有機野菜や女性の健康に特化したフェムケア商品を提供しています。また、SDGsにも配慮しており地熱発電による電力の使用やリユース品の利用に力を注いでいます。
【貧困問題】フェアトレードによる紅茶葉の開発
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
【神戸紅茶✖︎神戸学院の挑戦】フェアトレードを身近にする為に紅茶を作りたい
■達成金額
¥3,118,000
■目標金額
¥3,000,000
■支援者数
288人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000932
フェアトレードで茶葉を輸入・販売し、一般的に手に入りやすい商品にするためのプロジェクトです。
フェアトレードについて学んでいる神戸学院大学の生徒さんたちが、地域企業であり日本で初めてティーバック製造機を導入した神戸紅茶とコラボレーションして商品を開発しました。
【フードロス問題】規格外野菜を販売する無人店舗のオープン
〈プロジェクトの詳細〉
■プロジェクト名
【農家を救え!】規格外野菜を販売するDX無人販売店を淡路島にオープン!!
■達成金額
¥2,025,000
■目標金額
¥2,000,000
■支援者数
30人
■プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1000639
形が不規則であったり大きさが揃わないなどの理由で廃棄されている規格外野菜を、キャッシュレス&セルフレジの無人販売する店舗をオープンするプロジェクトです。
規格外として売値がつかない野菜を販売することで農家に還元し、フードロス問題の解消に寄与する仕組み作りの一環として、店舗での販売に加えて通信販売も行われています。
まとめ
この記事では、今も日本で起きている社会的課題から、あなたの身近で起こっているあらゆる問題まで、幅広く解説しました。
社会問題解決の民主化を図る「ForGood」では、世界各国の大小さまざまな課題と向き合い、解決へ導く行動を起こすことで、よりよい社会の実現を目指しています。
あなたの支援で日本の社会・世界の未来がかわる可能性があるでしょう。
社会問題への想いをアクションに変え「For Good」とともに、課題解決を目指しませんか。
クラウドファンディングに関するご相談を受け付けています!