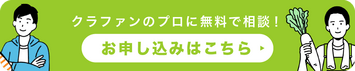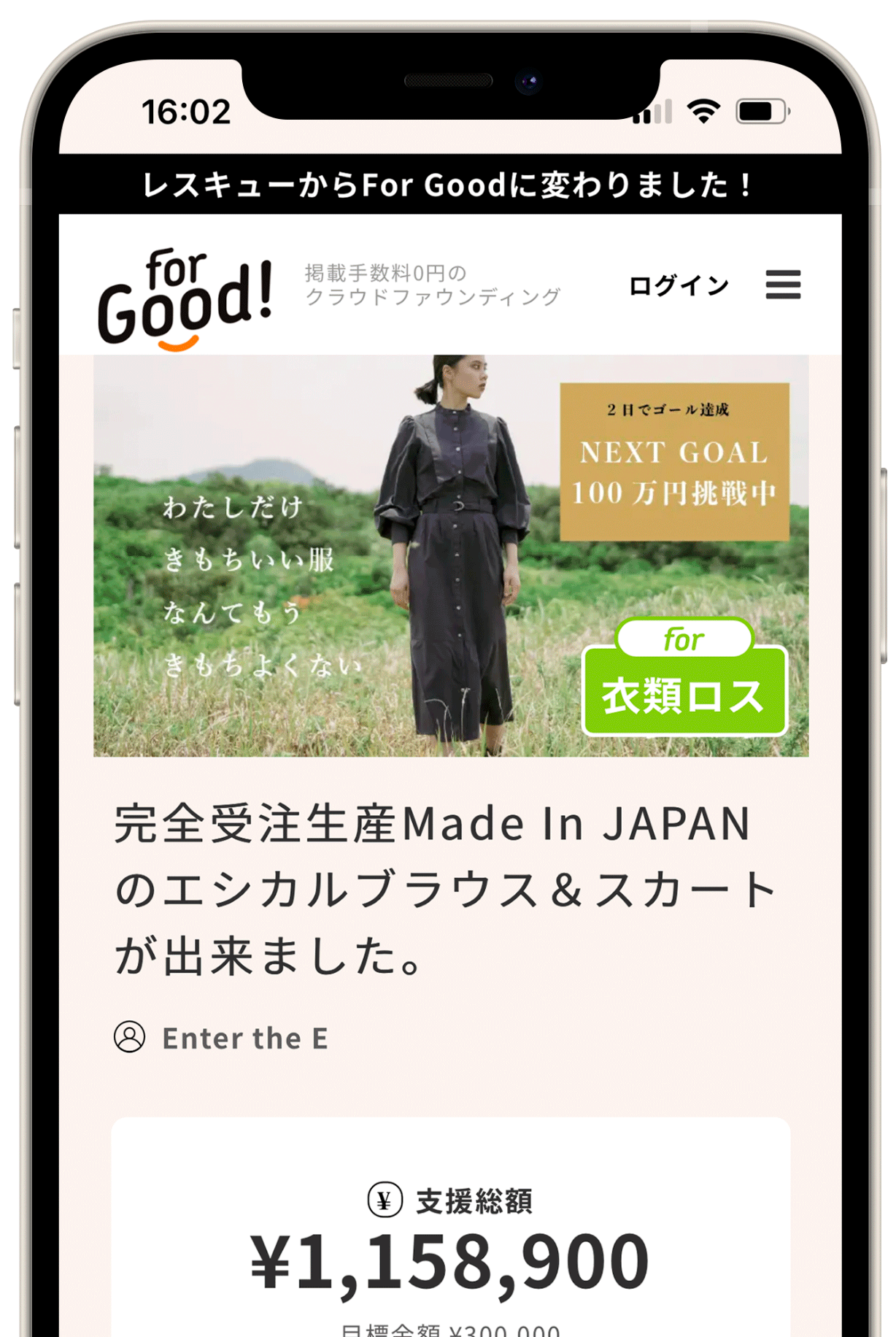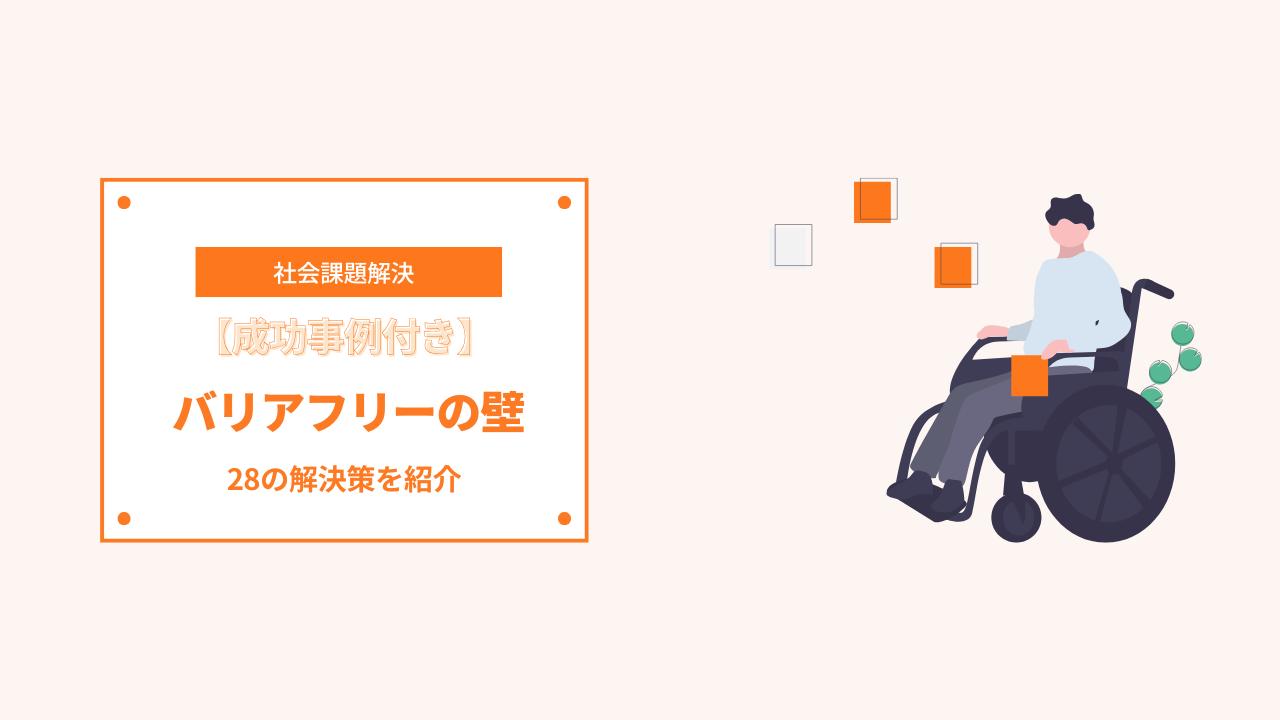
【事例付き】バリアフリーの壁を乗り越える!28の解決策を紹介
バリアフリーは、一部の人のためではなく、社会全体をより暮らしやすくするためのものです。
そこで本記事では、「物理的」「制度的」「文化・情報」「意識」の4つのバリアの観点から下記内容を解説していきます。
・4つのバリアを解消する28の事例
・成功事例と実践のためのポイント
・バリアフリーを進める具体的な方法
身近な場所で取り入れられるヒントを見つけ、 「変えられること」から一歩踏み出してみませんか?
- 物理的バリアの解消(7選)
- スロープの設置
- 自動ドアの導入
- 手すりの設置
- エレベーターの設置
- ノンステップバスの導入
- 多目的トイレの設置
- バリアフリー遊具の導入
- 物理的バリアの事例
- 歴史ある建築×自動ドアの導入
- 足こぎ車いすの認知拡大
- 制度的バリアの解消(7選)
- 助成金の活用
- バリアフリー整備計画の策定
- バリアフリー減税の適用
- バリアフリー認定制度の活用
- 障がい者割引制度の導入
- バリアフリー研修の義務化
- インクルーシブ教育の推進
- 制度的バリアの事例
- ラグビー選手を日本のリハビリ施設へ
- 農業×福祉施設の融合施設の設立
- 文化・情報のバリアの解消(7選)
- 点字メニューの導入
- 視認性向上デザインの採用
- スマート家電の活用
- 多言語対応アプリの提供
- 手話ガイドの導入
- 合理的配慮ルールの整備
- 筆談窓口の設置
- 文化・情報のバリアの事例
- 「やさしい日本語」の提供
- 意識のバリアの解消(7選)
- 接客研修の実施
- 意識改革プログラムの導入
- バリアフリー意識の啓発
- 適切な声掛けの普及
- 交流イベントの開催
- ワークショップの開催
- ダイバーシティ研修の実施
- 意識のバリアの事例
- 「見えにくい」を体験するイベント
- 障害の有無の隔たりをなくすイベント
- バリアフリーを実現するためにできること
物理的バリアの解消(7選)

物理的バリアとは、建物や交通機関などに存在する 「移動の障壁」 です。
日本では、バリアフリー新法(高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) に基づき、施設や交通機関のバリアフリー化が進められていますが、
未対応の場所も多く残っています。
ここでは、 導入しやすく、利便性を向上できる物理的バリアの解消策 を7つ紹介します。
|
施策 |
解決できる課題 |
導入のポイント |
|
スロープの設置 |
入口や施設の段差解消 |
簡易スロープや折りたたみ式を活用 |
|
自動ドアの導入 |
手動ドアが開けづらい問題を解消 |
センサー式やボタン式など環境に合わせる |
|
手すりの設置 |
転倒リスクの軽減 |
介護施設や住宅の動線確保に有効 |
|
エレベーターの設置 |
階段移動の負担軽減 |
設置が難しい場合は昇降機の導入を検討 |
|
ノンステップバスの導入 |
乗降時の段差を解消 |
地域公共交通機関と連携が重要 |
|
多目的トイレの設置 |
高齢者・障がい者が利用しやすい環境 |
オストメイト対応や十分な広さを確保 |
|
バリアフリー遊具の導入 |
すべての子どもが遊べる環境 |
視覚・聴覚に配慮した遊具も活用 |
1. スロープの設置
段差のある入口は、車椅子利用者やベビーカーを押す人にとって大きな障壁になります。
スロープを設置することで、すべての人がスムーズに出入りできる環境 を作ることが可能です。
◆ ポイント
・小規模店舗や住宅向けには 簡易スロープ も活用できる
・設置スペースが限られる場合は 折りたたみ式スロープ も選択肢
・助成金の活用 により負担を軽減できる
2. 自動ドアの導入
手動ドアは、車椅子利用者や手がふさがっている人にとって開けづらい場合があります。
自動ドアの導入により、誰でもストレスなく出入りできる環境 を実現できます。
◆ ポイント
・高齢者や子ども連れの来店客にとっても快適
・センサー式やボタン式 など設置環境に応じた選択肢がある
・補助金の対象となる場合もあるため、自治体の制度を確認
3. 手すりの設置
階段やスロープ、トイレなどに手すりを設置することで、転倒リスクを軽減し、安全性を向上させることができます。
◆ ポイント
・介護施設や公共施設では 手すりの高さや材質にも配慮 するとより効果的
・DIYで取り付けできる製品もあり、住宅でも手軽に導入可能
・段差が多い場所では、手すりと合わせてスロープを設置するとより安全
4. エレベーターの設置
階段しかない施設では、車椅子利用者や高齢者にとって移動が困難 になります。
エレベーターを導入することで、すべての人が自由に移動できる環境を整えられます。
◆ ポイント
・設置が難しい場合は、 昇降機や階段昇降機 も選択肢に
・エレベーターの点検や維持管理も重要(古い施設では改修支援制度も活用可能)
・商業施設では「バリアフリー対応エレベーター」の設置で利用者の満足度が向上
5.ノンステップバスの導入
公共交通機関において、バスの段差は大きな移動の障壁になります。
ノンステップバス(低床バス) を導入することで、車椅子利用者や足腰の弱い方もスムーズに乗車できます。
◆ ポイント
・全国的に導入が進んでいるが、地方ではまだ普及率が低い
・バス停のバリアフリー化 も併せて進めるとさらに利便性向上
・自治体と連携し、運行エリアの拡大を検討することも重要
6.多目的トイレの設置
車椅子利用者や高齢者、子ども連れの方が 安心して利用できるトイレ環境 を整えることが求められています。
◆ ポイント
・オストメイト対応トイレ の設置で、人工肛門・人工膀胱利用者の負担を軽減
・広めのスペースと手すりの設置 で、介助者と一緒に利用しやすくする
・商業施設や観光地では、バリアフリートイレの有無が来訪者の決定要因になることも
7. バリアフリー遊具の導入
公園や学校の遊具は、障がいのある子どもも一緒に遊べるものにすることが理想的 です。
◆ ポイント
・車椅子対応ブランコや傾斜の少ない滑り台 など、誰でも遊べる遊具を設置
・触覚や音を活用した遊具 で、視覚・聴覚障がいのある子どもにも配慮
・地域コミュニティが関与し、継続的に利用・維持できる仕組みが重要
これらの取り組みによって、 障がいのある方や高齢者だけでなく、誰にとっても使いやすい空間が生まれます。
さらに、バリアフリー対応が進むことで、 訪問客の増加や施設の評価向上にもつながります。
しかし、これらの施策を進める上で 費用負担の壁 があるのも事実です。
そこで、次の章では 実際に物理的バリアを解消した事例 を紹介します。
どのようにバリアフリーを実現したのか、具体的なプロジェクトを見ていきましょう。
物理的バリアの事例

物理的バリアを解消するためには、設備の改善やインフラ整備が重要ですが、 「コストがかかる」「建物の構造上、改修が難しい」 などの課題もあります。
しかし、創意工夫や支援を活用することで、既存の環境を活かしながらバリアフリーを実現した事例 も数多くあります。
ここでは、 歴史的建築物とバリアフリーの両立 や、 新たな移動手段の普及を通じたバリアの解消 に取り組んだ事例を紹介します。
歴史ある建築×自動ドアの導入
歴史的な建築物は、文化的価値が高い一方で、バリアフリー化が進みにくいという課題があります。
「段差が多く、重い扉が開けづらい」 という問題に直面する施設も少なくありません。
このプロジェクトでは、 伝統的な外観を守りながら、自動ドアを導入する取り組み を行いました。
〈プロジェクトの詳細〉
■伊香保温泉の築100年超の建物を活用して、石段街を楽しくする拠点をつくりたい!
■達成金額 ¥1,605,000
■目標金額 ¥1,200,000
■支援者数 164人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/project/1000970
足こぎ車いすの認知拡大
車いす利用者にとって、移動の自由度を高めることは生活の質を向上させる重要な要素 です。
しかし、従来の車いすは「手でこぐタイプ」が主流であり、長距離の移動が負担になることもあります。
このプロジェクトでは、 足の力を使って前進できる「足こぎ車いす」の認知拡大 に取り組みました。
足を動かせる人にとっては、より自立した移動が可能になり、リハビリ効果も期待できる という利点があります。

〈プロジェクトの詳細〉
■足こぎ車いすCOGYで歩行困難者の誰もが「挑戦できる機会」を創造する!
■達成金額 ¥724,000
■目標金額 ¥650,000
■支援者数 60人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/trn_project/44892
これらの事例は、設備の改善だけでなく、「新しい発想」や「使い方の工夫」によってバリアを解消する方法がある ことを示しています。
バリアフリー化は、大掛かりな改修だけでなく、 既存の環境に合わせた柔軟な取り組み でも十分に進めることができます。
ただし、物理的バリアの解消には、資金や制度の支援が欠かせません。
次の章では、 バリアフリーを推進するための制度的な支援や、活用できる助成金について 解説します。
制度的バリアの解消(7選)

バリアフリーの整備には、設備の導入や改修にかかる費用の負担 が大きな課題となります。
特に中小規模の施設や個人がバリアフリーを進める際には、 資金面のハードル が障壁となることが少なくありません。
しかし、 すでに利用できる助成金や減税制度、バリアフリー推進のための認定制度 などを活用することで、負担を軽減しながら整備を進めることができます。
この章では、 制度を活用してバリアフリーを推進するための具体的な方法 を7つ紹介します。
|
制度 |
対象 |
活用ポイント |
|
助成金の活用 |
施設・店舗・住宅 |
バリアフリー改修費用の補助を受ける |
|
バリアフリー整備計画の策定 |
公共施設・企業 |
計画的にバリアフリー化を進めるための指針 |
|
バリアフリー減税の適用 |
個人住宅・事業者 |
リフォーム時の税制優遇を受ける |
|
バリアフリー認定制度の活用 |
ホテル・商業施設 |
認定を取得し集客力を高める |
|
障がい者割引制度の導入 |
交通機関・商業施設 |
移動やサービス利用の負担を軽減 |
|
バリアフリー研修の義務化 |
企業・店舗 |
従業員の意識向上と対応力の強化 |
|
インクルーシブ教育の推進 |
学校・教育機関 |
障がいのある子どもと健常児が共に学べる環境 |
1. 助成金の活用
バリアフリー化を進めるためには、国や自治体が提供する助成金 を活用するのが有効です。
特に、 店舗・住宅のバリアフリー改修 に関する補助金制度があり、手すりの設置やスロープの導入、エレベーターの新設 などが対象になることが多いです。
◆ ポイント
・自治体によって助成金の内容が異なるため、申請前に確認が必要
・個人住宅向けのリフォーム補助制度も活用可能
・事業者向けには、中小企業向けのバリアフリー化補助金も存在する
2. バリアフリー整備計画の策定
建築物や公共施設のバリアフリー化を進めるためには、計画的な整備が不可欠 です。
国や自治体が策定する「バリアフリー整備ガイドライン」に沿って進めることで、より効果的な環境整備が可能 になります。
◆ ポイント
・計画を立てることで、限られた予算内で効率的に整備が進められる
・行政と連携し、地域全体でのバリアフリー化を促進できる
・補助金や助成金を受ける際にも、計画があると申請しやすくなる
3. バリアフリー減税の適用
バリアフリー改修にかかった費用について、 減税措置を受けられる制度 があります。
特に、 住宅リフォーム減税や固定資産税の軽減措置 などを活用することで、コスト負担を減らしながらバリアフリー化を進めることが可能です。
◆ ポイント
・住宅をバリアフリーリフォームした場合、所得税の控除を受けられる場合がある
・事業者向けにも、バリアフリー改修に関する法人税の軽減措置がある
・補助金と組み合わせることで、費用負担をより小さくできる
4. バリアフリー認定制度の活用
商業施設や宿泊施設などでは、バリアフリー認定を取得することで、集客力向上やブランド価値の向上 につなげることができます。
また、バリアフリー対応の施設は補助金や税制優遇を受けやすくなる場合もあります。
◆ ポイント
・認定を受けることで、利用者にとって安心できる施設であることをアピールできる
・自治体の観光促進施策と連携することで、補助を受けやすくなる
・バリアフリー対応を進めることで、高齢者・障がい者向けの新たな市場開拓にもつながる
5. 障がい者割引制度の導入
交通機関や公共施設では、障がい者割引を設けることで、移動の機会を増やし、アクセスのしやすい環境を提供することができる ます。
特に、鉄道・バス・美術館・映画館などでは、すでに多くの施設で割引制度が導入 されています。
◆ ポイント
・事業者が独自の割引制度を設定することで、利用者の増加が期待できる
・補助金を活用して、運営負担を軽減できるケースもある
・公共交通機関では、割引制度とバリアフリー化をセットで進めることが望ましい
6. バリアフリー研修の義務化
物理的なバリアを解消しても、スタッフが適切に対応できなければ、バリアフリー環境は十分に機能しません。
そのため、バリアフリー研修を義務化し、障がい者や高齢者に配慮した接客や対応を学ぶことが重要 です。
◆ ポイント
・福祉業界だけでなく、商業施設や観光業でもバリアフリー研修の導入が進んでいる
・正しい知識とスキルを持ったスタッフが増えれば、利用者の満足度が向上する
・研修を実施することで、従業員の意識向上にもつながる
7. インクルーシブ教育の推進
教育の現場でも、障がいのある子どもと健常児が共に学べるインクルーシブ教育 の推進が求められています。
特に、特別支援学校と通常学級の連携や、ICTを活用した教育支援 などが進められています。
◆ ポイント
・「共に学ぶ環境」を整えることで、すべての子どもにとって学びやすい環境をつくれる
・ICT機器を活用し、学習支援ツールを取り入れることで学びの幅が広がる
・学校だけでなく、地域全体でインクルーシブな環境を整えることが重要
制度を活用しながら、バリアフリーを推進する
バリアフリーの整備には、費用の問題や計画の策定が課題 になりますが、
すでに活用できる制度を知るだけでも、大きな一歩になります。
すべての費用を助成金でまかなうことは難しいため、自治体の補助金、税制優遇、バリアフリー認定制度を組み合わせて活用する視点が重要 です。
次の章では、実際に制度を活用してバリアフリーを推進した事例 を紹介します。
具体的なプロジェクトを通じて、どのような仕組みが活用されているのかを見ていきましょう。
制度的バリアの事例

制度を活用することで、資金の課題をクリアしながらバリアフリー化を進めることが可能 です。
ここでは、 助成金やバリアフリー認定制度、インクルーシブ教育の推進 など、実際に制度を活用してバリアを解消したプロジェクトを紹介します。
ラグビー選手を日本のリハビリ施設へ

障がい者スポーツは、身体機能の回復や社会参加の促進 に大きく貢献するものの、競技を続ける環境が整っていない地域も多くあります。
このプロジェクトでは、 海外の障がい者ラグビー選手を日本のリハビリ施設に招き、トレーニングや交流を行う取り組み が行われました。
〈プロジェクトの詳細〉
■『一緒に一歩を』ネパール女子ラグビー選手を、日本のリハビリ施設へ
■達成金額 ¥3,283,500
■目標金額 ¥3,000,000
■支援者数 324人
➡ 詳細を見る https://for-good.net/project/1000661
農業×福祉施設の融合施設の設立
障がい者が働く環境を整え、社会との接点を増やすために、農業と福祉施設を組み合わせた新しい形の事業 が生まれました。
このプロジェクトでは、 障がい者が農作業を通じて自立できる環境を作り、地域全体の活性化にもつなげること を目的としています。
 〈プロジェクトの詳細〉
〈プロジェクトの詳細〉
■東海村発!古来の生き方から学び、自分らしくいられる場所を、農×福祉×アートで創る
■達成金額 ¥3,384,000
■目標金額 ¥3,000,000
■支援者数 192人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/project/1001029
これらの事例からわかるように、 「制度を活用することで、バリアフリー化の実現が加速する」 ことが分かります。
他の事例を参考にしたり、地域の支援団体や専門家のサポートを活用したりすることが重要 です。
次の章では、 文化・情報のバリアの解消 に焦点を当て、バリアフリーをさらに広げるためのアプローチを紹介します。
文化・情報のバリアの解消(7選)

バリアフリーというと、物理的な設備や制度の整備に目が向きがち ですが、情報の伝え方や文化的な認識の違いも、大きなバリアとなることがあります。
たとえば、視覚障がい者がメニューを読めない、聴覚障がい者がイベントの内容を把握しにくい、言葉の壁で外国人が情報を得られない など、情報のバリアは日常のさまざまな場面に存在します。
この章では、情報伝達や文化的な理解を深めることで、バリアフリーを広げるための施策 を7つ紹介します。
1. 点字メニューの導入
視覚障がい者にとって、飲食店や商業施設で メニューを確認できない ことは大きなハードルになります。
点字メニューを用意することで、視覚障がい者が周囲に頼ることなく、自由に選択できる環境 を整えることができます。
◆ ポイント
・スマートフォンを活用した読み上げ機能付きメニューの導入も有効
・点字のほか、大きなフォントのメニューも視認性向上に効果的
2. 視認性向上デザインの採用
公共の案内表示や標識において、文字が小さい、背景と同化して見づらい などの問題があると、利用者にとって不便なだけでなく、安全上のリスク も発生します。
◆ ポイント
・コントラストを強くし、読みやすい色使いにする
・ピクトグラム(視覚的にわかるアイコン)を活用する
3. スマート家電の活用
最新の技術を活用することで、音声操作や自動制御を活用した、誰でも使いやすい環境 を実現できます。
◆ ポイント
・音声アシスト機能で、視覚・聴覚に障がいのある方も使いやすくなる
・照明や家電の操作をスマホやタブレットからできるようにすることで、身体の自由が効かない方にも利便性を提供
4. 多言語対応アプリの提供
外国人観光客や在住者にとって、日本語表記しかない施設や店舗は、利用しにくいものです。
多言語対応アプリや自動翻訳システムを導入することで、誰でもスムーズに情報を得られる環境を提供 できます。
◆ ポイント
・スマホアプリを活用したリアルタイム翻訳を提供する
・観光地や商業施設では、英語・中国語・韓国語の音声ガイドを整備する
5. 手話ガイドの導入
聴覚障がい者が観光地や商業施設を利用する際に、音声案内が使えないことで情報を得にくい という課題があります。
手話ガイドや字幕付き案内を提供することで、聴覚障がい者でも安心して利用できる環境を整えることが可能 です。
◆ ポイント
・デジタルサイネージで手話案内を提供する
・イベントや講演では、手話通訳者を配置し、誰でも情報を得られる環境を整える
6. 合理的配慮ルールの整備
企業や公共施設で、障がい者への配慮を義務付けるルールを設けることで、誰もが平等にサービスを受けられる環境 を作ることができます。
◆ ポイント
・合理的配慮とは、「過度な負担なく提供できる支援」のこと
・従業員向けに「どのような対応が適切か」を学ぶ機会を設ける
7. 筆談窓口の設置
聴覚障がい者や言葉を話すのが難しい方にとって、筆談によるコミュニケーションの選択肢があるだけで、安心感が大きく変わります。
◆ ポイント
・受付カウンターに「筆談対応できます」の案内を設置
・スマートフォンやタブレットを使った文字入力アプリの導入も有効
文化・情報のバリアは、設備の整備に比べて、比較的低コストで解決できるものが多い という特徴があります。
デジタル技術を活用したり、ルールを見直したりすることで、 すぐにでも取り組める施策が多数存在 します。
次の章では、 実際に文化・情報のバリア解消に取り組んだ事例 を紹介します。
具体的なプロジェクトを通じて、どのような工夫がされているのかを見ていきましょう。
文化・情報のバリアの事例

「やさしい日本語」の提供
外国人観光客や、日本語を母語としない人々にとって、難解な日本語表記や専門用語が多い施設案内は、情報を理解する障壁 になっています。
このプロジェクトでは、 「やさしい日本語」を活用した案内表示やマニュアルを導入する取り組み を実施しました。
 〈プロジェクトの詳細〉
〈プロジェクトの詳細〉
■日本語を母語としない子どもに「やさしい日本語」による教育支援を届けたい!
■達成金額 ¥540,500
■目標金額 ¥400,000
■支援者数 74人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/project/1000607
文化・情報のバリアは、設備投資が必要な物理的バリアと異なり、アイデアや工夫で解決できるものが多い のが特徴です。
特に、情報の伝え方を変えるだけで、より多くの人にとって利用しやすい環境を作ることができる ため、すぐにでも取り組める施策が多くあります。
意識のバリアの解消(7選)

バリアフリーの課題は、物理的・制度的・情報の整備だけでは解決しきれない側面があります。
たとえ施設がバリアフリー化されていても、「どう接すればいいかわからない」「障がいのある方に話しかけるのが不安」 といった意識のバリアがあると、実際に利用しづらい環境になってしまいます。
この章では、 意識のバリアを解消するための取り組み を7つ紹介します。
1. 接客研修の実施
商業施設や観光業では、障がいのある方や高齢者に適切な対応を行うことが求められます。
スタッフ向けのバリアフリー接客研修を行うことで、安心して利用できる環境を作ることが可能 です。
◆ ポイント
・車いす利用者や視覚障がい者への適切なサポート方法を学ぶ
・「どう接すればいいかわからない」という不安を取り除く
・実際の利用者の声を取り入れた研修が効果的
2. 意識改革プログラムの導入
施設や企業の従業員が、「障がいのある方の視点を知る」 ことで、バリアフリーの本質を理解することが重要です。
体験型の研修や意識改革プログラムを導入することで、実際の困りごとを理解し、適切な対応ができる人材を育てる ことができます。
◆ ポイント
・視覚障がい者の体験として「目隠しをして移動する」研修が有効
・車いすでの移動体験を通じて、物理的な障壁を実感できる
・「合理的配慮」の考え方を学び、個別のニーズに対応できる力を養う
3. バリアフリー意識の啓発
バリアフリーの重要性を広めるために、地域や企業が積極的に情報発信を行う ことも大切です。
SNSやイベントを活用し、「誰もが暮らしやすい社会づくり」をテーマにした啓発活動 を行うことで、意識改革を促進できます。
◆ ポイント
・バリアフリーに関する情報を発信し、関心を持ってもらう
・実際のバリアフリー施策や成功事例を共有する
・企業や自治体が啓発イベントを定期的に開催する
4. 適切な声掛けの普及
バリアフリー対応が整っていても、実際に利用者が困っているときに適切なサポートができなければ意味がありません。
「どのように声をかければいいのか」を学ぶことで、ちょっとしたサポートができる社会 を目指せます。
◆ ポイント
・「手伝いましょうか?」の一言が助けになる
・障がいのある方の意思を尊重し、無理にサポートしないことも大切
・定期的な啓発活動を通じて、社会全体での意識を高める
5. 交流イベントの開催
障がいの有無に関係なく、さまざまな人が交流できる場を作ることで、相互理解を深めることができます。
スポーツや文化イベントを通じて、「一緒に楽しむ」ことが自然な環境を作り出す ことが可能です。
◆ ポイント
・障がい者スポーツの体験会を実施する
・バリアフリーの街歩きイベントを開催する
・「特別扱い」ではなく、誰もが自然に参加できる仕組みを作る
6.ワークショップの開催
企業や自治体が、バリアフリーについて学ぶワークショップを開催 することで、地域や職場の意識を高めることができます。
障がいのある方の体験談を聞いたり、実際にどのような課題があるのかを考える機会を提供 することが大切です。
◆ ポイント
・実際に障がいのある方の声を聞き、課題を知る
・地域の人々が一緒に考え、バリアフリー推進のアイデアを出す
・企業や行政と連携し、具体的なアクションにつなげる
7. ダイバーシティ研修の実施
企業や学校において、多様性を尊重し、すべての人が生きやすい環境を作るための研修 を導入することも有効です。
バリアフリーは、単なる設備の話ではなく、意識の問題でもある ため、ダイバーシティの観点から考えることが重要になります。
◆ ポイント
・企業研修の一環として、ダイバーシティ&インクルージョンを学ぶ
・職場や学校で「誰もが働きやすい・学びやすい環境」を整える
・障がいの有無にかかわらず、お互いに理解し合う文化を醸成する
意識のバリアを解消するために
意識のバリアは、制度や設備が整っていても、解消されないことがある重要な課題 です。
そのため、個人・企業・地域が連携し、意識改革を進めることが必要 になります。
バリアフリーとは、「特別な配慮」ではなく、誰もが暮らしやすい社会を作るための共通の取り組み です。
次の章では、意識のバリア解消に取り組んだ具体的な事例 を紹介します。
意識のバリアの事例

意識のバリアは、見えにくいために気づきにくい という特徴があります。
しかし、 「障がいのある人と接する機会が少ない」「どのように対応すればいいのかわからない」 という不安が、バリアの一因になっていることも少なくありません。
この章では、 実際に意識のバリアを解消するために行われた取り組み を紹介します。
「見えにくい」を体験するイベント
視覚障がいのある方が日常でどのような困難に直面しているのかを、実際に体験することで理解を深める ことを目的としたイベントです。
参加者は アイマスクを装着し、白杖を使って街を歩く体験 を通じて、段差の高さや音の情報の重要性を実感 します。

〈プロジェクトの詳細〉
■「見えにくい」を体験できるロービジョンカフェを実現したい!
■達成金額 ¥743,000
■目標金額 ¥350,000
■支援者数 93人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/trn_project/79920
障がいの有無の隔たりをなくすイベント
障がいの有無に関係なく、誰もが自然に参加できるイベントを開催することで、相互理解を深めることを目的 としたプロジェクトです。
音楽ライブ、アートの展示、マーケットを通じて、「障がい者のための特別な場」ではなく、「みんなで楽しむ場」を作ることに重点を置いています。

〈プロジェクトの詳細〉
■障がいがある人もない人もアートや音楽を楽しみ、隔たりなく交わる状況を当たり前に!
■達成金額 ¥1,562,500
■目標金額 ¥1,500,000
■支援者数 72人
➡ 詳細を見る
https://for-good.net/project/1001276
意識のバリアを解消するために
意識のバリアをなくすためには、実際に体験し、障がいのある方と交流する機会を増やすことが重要 です。
こうしたイベントを通じて、 「特別扱いするのではなく、自然に共に過ごせる環境を作る」ことがバリアフリーにつながる ことを、多くの人が実感できるようになります。
次の章では、 これまで紹介した28の事例をふまえ、バリアフリーを実現するためにできることを考えます。
バリアフリーを実現するためにできること

バリアフリーは、一部の人のための特別なものではなく、すべての人が快適に暮らせる社会をつくるための取り組み です。
まずは、身近な場所のバリアに気づき、小さな改善から始めることが大切 です。
助成金や支援制度を活用しながら、地域や職場でできることを少しずつ広げていきましょう。
また、障がいのある方や高齢者の声を聞き、共に考えることで、本当に必要なバリアフリーが見えてきます。
ひとつのアクションが、やがて大きな変化を生み出します。今できる一歩を踏み出してみませんか?えていくことはできます。
まずは 身近なところから始めてみませんか?
クラウドファンディングに興味がある方は、
ぜひ「For Good」で一緒に取り組みましょう!