FOR
勉強の景色を変える
だれかの勉強を助けて成長できる場所「イツモココデ」、はじめの300人計画です。

現在の支援総額
¥56,380
目標
¥300,000

支援者
8
人

残り
終了

みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
プロジェクトのポイント
1.だれもが、勉強のモヤモヤを安心して相談できるようになります。
2.勉強でだれかを助けることが、学ぶ理由と成長につながります。
3.”誰一人取り残さない”に、小中学生が主体になって近づけます。
プロジェクトの詳細
支援金の使い道
さいごに
PROFILE

株式会社itsumo
株式会社itsumoは、後藤大介が代表を務める株式会社アイディアシップ(千葉市)と、Juan Ignacio Luque Sandovalが経営するCrowdland Technology SLU(アンドラ公国)の共同研究から生まれた会社です。後藤は組織の関係づくりの支援を、SandovalはWebシステム構築に取り組んできており、両者の視点の掛け合わせが形になりました。二人はヘルシンキ大学が監修するAI講座を通じて2018年に知り合いました。
現在6名の従業員は、大学講師・ファシリテーター・世界紀行者(コンテンツ作成)、3人のお母さん方(サービス運営/本社業務)、教職課程を取った大学生(モニタリングとコンテンツ監修)、初回実証試験に参加した高校生(サービス・PR全般への助言)です。それぞれが持つ力を出して取り組んでいます。
社外のさまざまな立場の方々にも助けていただいています。
リターンを選ぶ
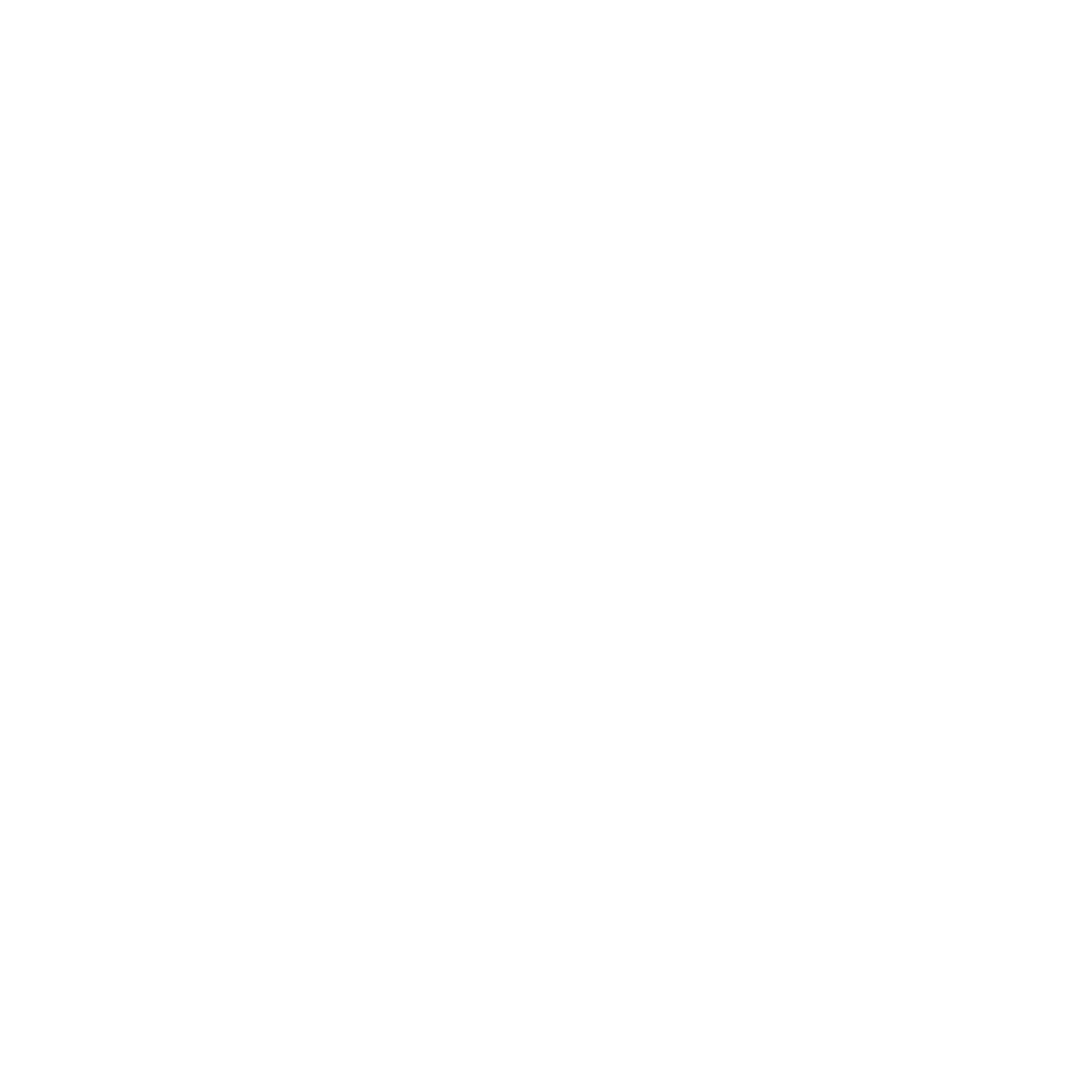
 画像処理中です...
画像処理中です...







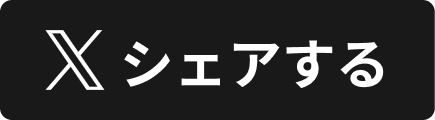








最新の活動レポート
まだ投稿がありません
みんなの応援コメント
kt
2024年11月2日
子供たちが楽しんで学習できるよう応援しております。
Cola
2024年10月24日
学習をつうじて誰かとつながる、学びあう経験ができる素敵な取り組みだと思います。たくさんの子どもたちに参加してもらいたいですね!
辛子せんべい
2024年10月23日
より多くの方に使ってもらえるよう 頑張ってください!