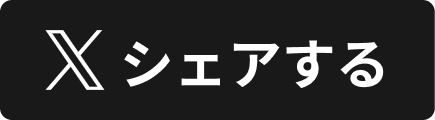ベトナム✖️有機農業
【日本とベトナムの有機をつなぐ】農の国際交流拠点「EANAファームステイ」を建設




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/3/21 21:45
水俣で自然農業のみかんを生産されている吉田さんからベトナム自然農業ツアーの報告書を頂きました。

ベトナム研修報告
ベトナム北部山岳地域のソンラ省バンホーと、中部高原地域のダクラク省バンメトートの2か所を2月に訪れた。今回の農業研修は、日本自然農業協会の協力のもと、ベトナムの有機野菜生産販売会社NICONICOYASAIの自社農場と周辺農家において、自然農業を普及するプロジェクトの一環として開催された。

まず同行したメンバーが個性的だった。日本自然農業協会代表の澤村氏は、有機トマト生産量日本一の傑物。農業技術はもちろん農業経営においても学ぶところが多い。協会の事務局を30年以上にわたって担っている姫野氏は韓国語が堪能で、自然農業の師である韓国の趙先生と日本の農家の橋渡しをされてきた。また福岡の有機農家で合鴨家族として知られた古野夫妻、元JICA職員の白石氏、そして私と、同じく水俣で柑橘栽培を行っている新田君という、30代から70代が長距離の移動をもろともせず、各地で農家の方々との交流と研修を行った。

ベトナムでは、NICONICOYASAIの代表である塩川氏を中心に、農場長のハー氏、ティエン氏、シン氏が、細やかに温かく迎え入れてくれた。彼らの案内があったればこそ充実した研修になったことは間違いない。塩川氏は有機農業を広めるボランティアに参加して以来20年、ベトナムの地で活動を続けてきた。2011年には有機野菜の生産と販売を担う会社を設立し、持続的な有機農業の発展に取り組んできた。今回は実際に、現地での取り組みを見て、今後の計画を知るための研修でもあった。
水俣で柑橘農家として就農して25年。当初2月3月で収穫出荷が終了してしまう2品種しかなかった農地を、数年かけて土地を改良し、品種を増やし、10月から6月の約9ヵ月間、柑橘を収穫できる果樹園にしてきた。集約化・効率化し労働力と収入の分散を図る目的で取り組んできた。
しかし苗が成木となり、収量が上がり、目標としていた状態になると、基本的にはひとりの労働力と仕事量が釣り合わなくなってきた。ここ数年、思い描いた状態であるのに、自分が育ててきた果樹園の労働者となり、仕事が「作業」になってしまっているのではないか、という疑念が湧いてきた。そこには創造性や工夫や楽しみがない。精神的にきつい状態にあった。不定期ではあったが、韓国や国内の他産地に研修に出かけ、新たな取り組みを学び刺激を得ていたこともあって、新型コロナの移動自粛期間中は、いま思うとかなりしんどかった。
私の課題は「作業」でない仕事がしたい、ということだった。私が今回のベトナム研修で学んだことは主に、アグロフォレストリー、古野氏の「思い込みは宝物」という言葉、持続性、の3点になる。
「アグロフォレストリー」
福岡空港からハノイに到着し、そこから車で揺られ5時間、ラオス国境までおおそよ
30㎞という北部山岳地域のバンホーに到着したのは夜中だった。幹線道路から迎えのピックアップトラック(私は喜んで荷台に)乗って山の上へ向かう。霧深い先に現れた山頂のゲストハウスの佇まいに歓喜した。素敵すぎたのだ。ここスカイラインファームは、ベトナム戦争後に農地を確保するため森が切り開かれ、禿山になっていた場所らしい。そこをリンさんとフンさんの女性2人が、7年の歳月をかけ、木材となる木や実のなる木、花の咲く木を植え、薬草やハーブ、農作物を育てる畑などを造ってきたらしい。背の高いものから土の中のものまで、高さの違いと拡がり、陰日向が心地いい。
2人はこの場所で有機野菜生産と加工、ファームステイを3本柱に経営している。オーガニックを基本において、土の再生に自分たち自身の再生を託しているそうだ。課題としては、いろいろな種類の作物を育てているので、個々の収量が少なく、専門性も高くならないということだった。しかし「農業は作物だけでなく景観も同時に造っている」という古野氏の言葉を実感できる場所であった。
中部高原地域のバンメトートで訪れたコーヒー園は、森の中にコーヒーの木もあります、という場所だった。いずれ材として伐採するための木とバナナやジャックフルーツ、ドリアン、胡椒など様々な作物が混植され調和した場所だった。全体としての調和が取れ始めたら、人間の仕事は段々少なくなってくるという話は興味深いと思った。

ちなみにベトナムはロブスタ種のコーヒー栽培が盛んで、生産量は世界一だ。そしてここバンメトートがその栽培の中心地である。日本ではあまり馴染みのないロブスタ種のコーヒーをお土産にしたら、妻がことのほか気に入って飲んでくれている。
生産量を求めようとするのは当たり前で、コーヒーの単一栽培農園は多く、そちらのほうがむしろ一般的だ。作業性や効率を考えるとプランテーション化することが当たり前といっていい。ここで私のみかん園ともつながってくる。他に単一でなくコーヒーと胡椒の混植園も広い。土地をどう活かすかは農家の考え方次第だということがよくわかる。
古野氏の農業からは学ぶことが多かった。ベトナムの方々向けの講演や実演だったが、必死にメモを取りながら聞き入ってしまった。古野氏は合鴨を活用した稲作で名の知れた方であり、以前水俣で開催された有機農業大会で顔を合わせてもいた。しかし稲作農家でない私は、勉強不足でその技術の本質を知らなかった。
私は、合鴨が田に生えてくる雑草を処理してくれる「手段」としか考えていなかった。そうではなく水稲と畜産を同時に行う「合鴨稲作同時作」が正しい。合鴨を活用する効果として、除草だけでなく害虫駆除、栄養(フン)補給、稲に触れることによる成長促進(エチレン発生)、そして畜産としての鴨肉、卵となる。さらにドジョウを養殖し田の周りにイチジクなどの果樹を植える。稲刈り後にはすぐにサブソイラーで深耕し畑作へ移行するという。知恵と技術で土地を最大限に活かす、目から鱗のはなしだった。
アグロフォレストリーを目の当たりにし、古野氏の農業を知り、単一栽培の在り方に、ある種の不自然さを実感した。もっと知恵を絞って、農地を活用する道もあるのだと気が付いた。
「思い込みは宝物」
農業の柱は土作りと除草だと古野氏はいう。除草がボトルネックとなって、栽培面積の拡大を阻み、生産コストの増大を招いている。農業は雑草との戦いだ、とは多くの農業者からよく聞く言葉だ。戦いであるならば勝利しなければならない。草取りは当たり前、戦費(除草剤・マルチ)を掛けて敵をせん滅(抑え込む)しかない、との思い込み。限られた労働力と時間的制約の中で、お金をかけずに知恵と工夫で勝ちを治めるにはどうすればいいのかと、深く探求しようとしないのは、経験や常識からくる「思い込み」が邪魔をするからだ。
古野氏はどのタイミングに、どういった方法で戦うかを試行錯誤した結果、そのボトルネックを解消した。強靭なプロレスラーも赤ちゃんの時に戦えば勝てる、とは技術のコツを平易な例えで言語化したもので、唸ってしまう。
田植えは田植え機でやるもの、との思い込み。古野家には田植え機はないらしい。ヒエとの競争に勝つために人手間かけた籾を、乾田直播でスタートダッシュをかけるという。その後赤ちゃんプロレスラーを抑え、合鴨にバトンタッチされる。
古野さんの奥様とは移動中ずっとお話しさせていただいた。結婚前のことから5人の子育てのこと、お孫さんのこと、話題が豊富で面白い。その中で最も印象的だったのが、草取りから解放されたという話だ。足腰の負担がなくなり、楽しく農業をしながら生活できている、という。「解放」という言葉が、それまでの戦いの辛さを物語っている。
「持続性」
次へ、次の世代、人へ。そういう思いを感じる研修でもあった。日本自然農業協会代表である澤村氏は、協会の師である趙先生から受けた教えを、次に伝えようという使命感をもっている。自社では、多くの農業研修生を国内外から受け入れ、包み隠さず農業技術を伝授している。今回ベトナムでお世話になったティエン氏やシン氏も、熊本の澤村氏の農場で長期研修を受けた人たちだ。事務局の姫野氏も同様で、今年1月に亡くなった趙先生の遺志を、次につなげようと国内外で奮闘されている。

NICONICOYASAIの塩川氏は、20年に渡ってベトナムの有機農業の発展のために粉骨
砕身で頑張っている。南北2か所の生産農場を立ち上げ、地元のスーパーに有機野菜を納入している。ベトナムの人たちが自律的に有機農業に取り組み、金銭的にも自立できるようにと農の国際交流拠点「EANAファームステイ」の建設計画を進行中だ。また古野氏のお子さんたちはそれぞれ独立して農業を営んでいらっしゃる。
次を意識しながら、自分の役割を認識して動いていらっしゃる方々と、充実した中身の濃い時間を過ごすことができて、本当に実りの多い研修だった。今回得た気づきと、訪れた場所や出会った人達からいただいた刺激は、みかん山で働かされていると受け身になっていた私に、力強い「喝」を入れてくれた。ベトナムから持ち帰ったパパイヤの種を見つめて、ワクワクしている自分がいる。
水俣市 柑橘農家
吉田浩司
リターンを選ぶ
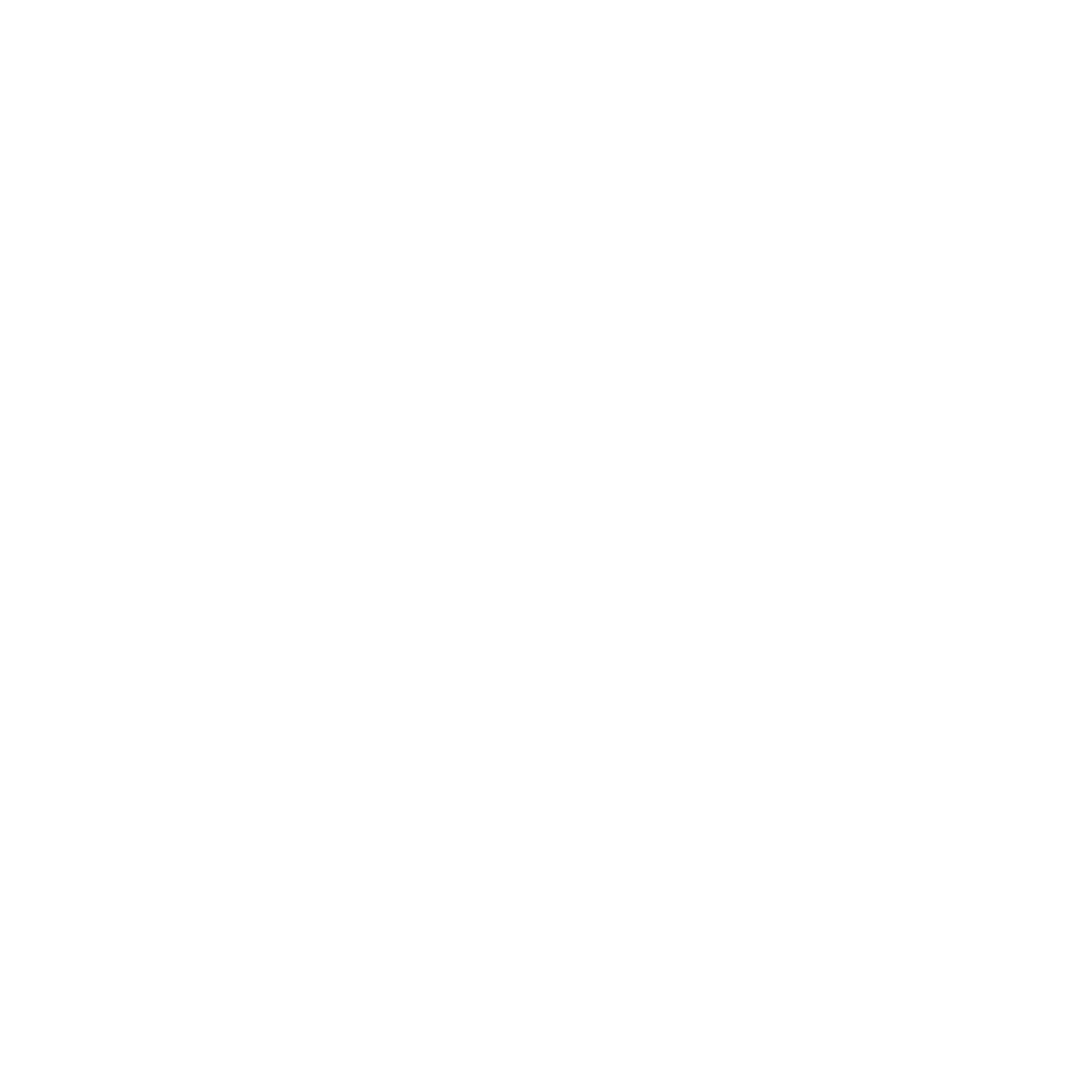
 画像処理中です...
画像処理中です...