伝統文化
侘び・寂びが絵になる~Wabi-Sabi Projectの支援のお願い~




みんなの応援コメント

田村敏樹
2024年9月28日
初めまして、田村と申します。 日本人でありながら、数千年途切れていない文化をほぼ知らずに生きているというのは、本当に嘆かわしいなと思う次第です。自分では行動出来ない文化の継承の為に...
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
プロジェクトのポイント
1.侘び・寂びの本質を絵画の比較を通じてあきらかにします。
2.外国の方が日本の精神性をどう捉えるか時間をかけて表現します。
3.様々なリターンをご用意しております。
プロジェクトの詳細
支援金の使い道
さいごに
PROFILE

徳永勇樹
1990年7月生まれ。東京大学先端研創発戦略研究オープンラボ(ROLES)連携研究員。株式会社住地ゴルフ勤務。元三井物産株式会社勤務(約10年)。早稲田大学政治経済学部卒。日本語、英語、ロシア語に堪能。英語・ロシア語通訳、ロシア国営ラジオ放送局スプートニクのアナウンサーを経て、2015年三井物産株式会社入社。三井物産では、4年半の鉄鋼製品海外事業開発、2年間のイスラエル留学を経て、社内シンクタンクである株式会社三井物産戦略研究所に出向。総合商社時代に担当した地域は約100か国。 2024年7月末に退職するまで、本業と同時並行で文化活動を4年続け、Culpediaを立ち上げた。株式会社住地ゴルフでは、一切の業務が免除され、勤務地・勤務時間全て自由という条件のもと、日本と世界の文化研究に専念。新潮社、ダイヤモンド社、文芸春秋社、講談社等で連載を担当。これまでに執筆した記事の数は50を超える。
リターンを選ぶ
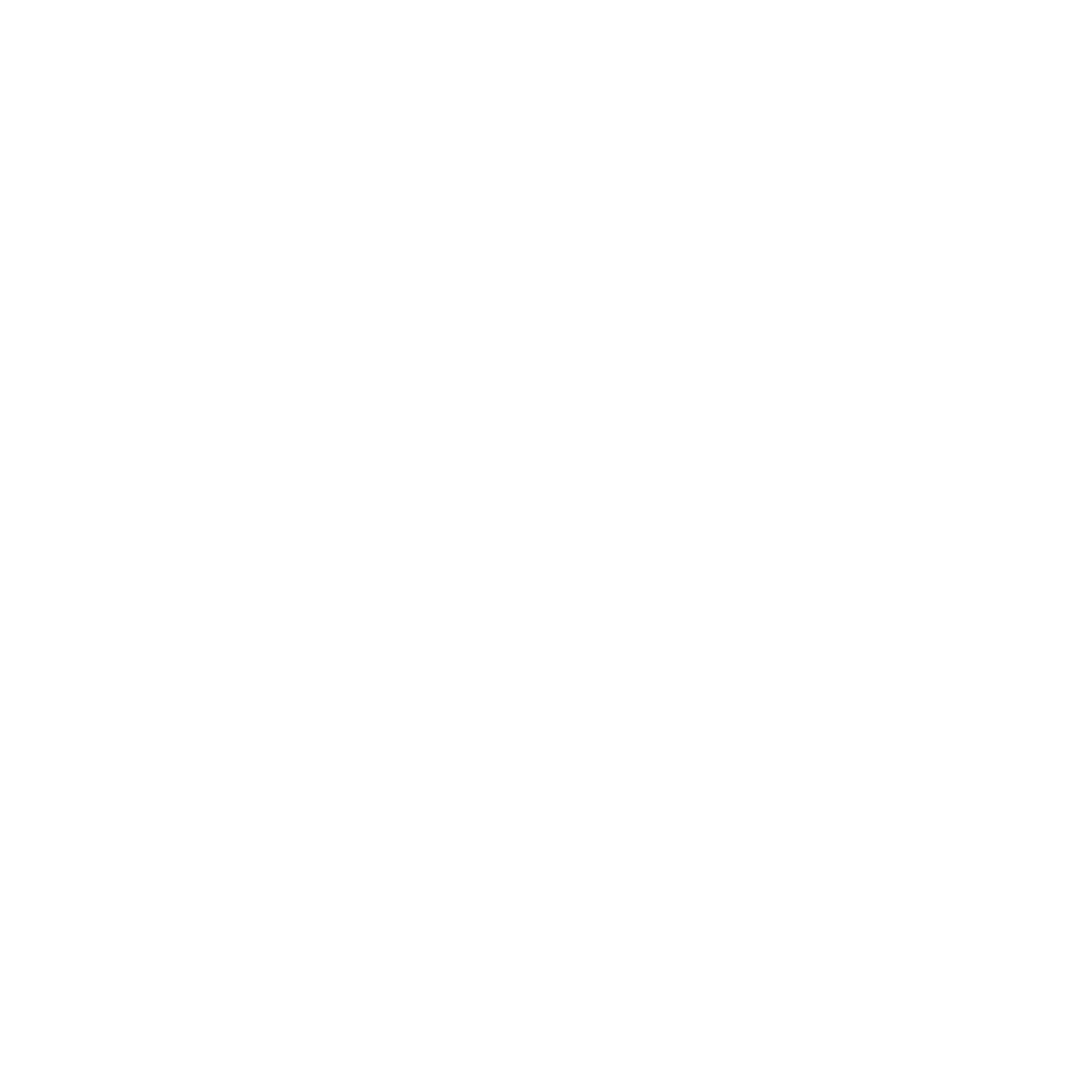
 画像処理中です...
画像処理中です...





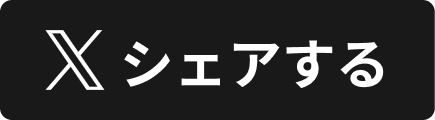








最新の活動レポート
まだ投稿がありません
みんなの応援コメント
亀屋良長株式会社
2024年9月30日
素晴らしい取り組み応援しています。
田村敏樹
2024年9月28日
初めまして、田村と申します。 日本人でありながら、数千年途切れていない文化をほぼ知らずに生きているというのは、本当に嘆かわしいなと思う次第です...
岩沙はるか
2024年9月22日
遅くなってしまいすみません。ほんの気持ちですが、引き続き応援しています!そして、徳永さんには、応援してくれる人がたくさんいるんだなぁと、人望の...