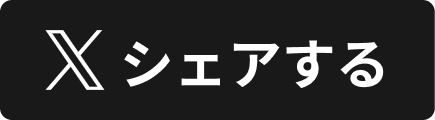アートと社会をつなぐ
アートと社会をつなぐ挑戦!ポートランドで学ぶソーシャル・アート実践




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/6/7 22:30
【インタビュー②】境界を越えるまなざし——Kiara Hillの創造のかたち

🧑🏫 研究・教育・実践を横断するアートの在り方
2025年6月4日、ポートランド州立大学(PSU) アートヒストリー・客員助教(Visiting Assistant Professor of Art History)のKiara HillさんにZoomでインタビューを行いました。
Hillさんは、アメリカにおけるブラック・アーツ・ムーブメントやブラック・フェミニスト・アートを専門とする研究者です。マサチューセッツ大学アマースト校にてアフロアメリカン研究の博士号を取得し、自らもブラック・ヴィジュアル・アートのキュレーターとして活動しています。現在はPSUで、学部生や大学院生とともに授業やプロジェクトに取り組みながら、学びのプロセスを支えています。また、KSMoCA(King School Museum of Contemporary Art)の実践にも深く関わっています。
🔍 ソーシャル・プラクティスと地域への関わり
“I had never heard of social practice.”
(ソーシャル・プラクティスという言葉を、それまで聞いたことがありませんでした)
HillさんはPSUに着任するまで、ソーシャル・プラクティスという概念自体に馴染みがありませんでした。しかし、ソーシャル・プラクティスに関するアートヒストリーの授業を教えるなかで、自身の研究やプロジェクトが実はこの分野と深く関わっていることに気づいたといいます。
“The kind of social practice lens… emphasizes aspects of the process.”
(ソーシャル・プラクティスの視点は、プロセスの側面を強調してくれます)
この視点は、これまで言葉にしづらかった自分の創造的な実践の背景や意義を明確にしてくれるものだったとHillさんは語ります。特に人との関係性を重視したプロジェクトにおいて、プロセス自体が重要な要素として再認識されたことで、活動に対する理解も深まったといいます。
🎥 映像プロジェクトとオーラル・ヒストリー
現在進行中の主なプロジェクトの一つは、1960〜80年代に活動していたポートランドのブラックアーティストへのインタビュー記録の収集です。12名のアーティストへの聞き取りとスタジオ訪問の記録を通して、地元に根付いたアートの歴史を掘り起こし、語り継ぐアーカイブづくりに取り組んでいます。
“I\'ve been interviewing Portland-based Black artists… from the sixties, seventies, eighties.”
(ここ2年ほど、ポートランドを拠点に活動していた1960〜80年代のブラックアーティストにインタビューを続けてきました)
このプロジェクトでは、オーラル・ヒストリー(口述記録)をNorth Portland Libraryに保管し、地域の人々が自由にアクセスできる状態にすることを目指しています。また、将来的には短編映画やシリーズとしての展開も視野に入れているとのことです。
さらに、ブラック・アーツ・ムーブメントを代表するAfriCOBRAのメンバー、Napoleon Jones-Henderson氏の自宅に保管されている約50年分の資料のアーカイブ整理にも取り組んでいます。
“What I really care about is accessibility and storytelling… social practice is the reason I’m able to come to that understanding.”
(私が本当に大切にしているのは、アクセシビリティとストーリーテリングです。そして、ソーシャル・プラクティスこそが、それを理解するきっかけになりました)
🤝 信頼と協働を軸とした実践
“Even though I’m Black, I’m not from this community… that trust part is really important.”
(私はブラックではありますが、このコミュニティの出身ではありません。だから信頼の構築がとても重要なのです)
Hillさんは、ポートランドという新しい土地で、自分が外部の存在であることを意識しながら、まずは地域の人々との対話と信頼構築を重視してきました。マサチューセッツでの経験を通じて、「同じ人種的背景を持っていても、文化的背景が異なれば信頼はゼロから築く必要がある」と実感していたといいます。
プロジェクト初期には、信頼できる地域の協力者の助言を受けながら、誰に話を聞くべきか、またアーティストへの報酬設定などについても丁寧に相談を重ねていきました。Hillさんはアーティストの時間や経験に敬意を示すため、謝礼(500ドル)と食事の提供を行いました。
“I’m not here to extract and not give back.”
(私は、何かを一方的に引き出して何も返さないためにここにいるのではありません)
こうした誠実な姿勢が、地域の人々からの信頼を深め、自身のネットワークを広げていく土台を築いていったのです。
🏫 KSMoCAと教育実践の広がり
“I am part of the kind of intimate team that runs KSMoCA.”
(私はKSMoCAを運営する親密なチームの一員です)
PSU着任2年目以降、Hillさんは展覧会設計やテキスト作成、外部連携の企画などに携わり、KSMoCAの活動を日常的に支えています。単なる授業の一環にとどまらず、KSMoCA プログラムマネージャーであるLaura Glazerさんと密に連携しながら、展覧会ラベルの作成、アーティストとのコラボレーション、地域とのつながりに日々取り組んでいます。
“Through KSMoCA, I\'ve been able to facilitate the Sankofa program.”
(KSMoCAを通じて、Sankofaプログラムの運営に関わってきました)
Sankofa プログラムでは、Laika Studiosのアニメーターを招いて、子どもたちとストップモーションアニメーションを制作するワークショップを実施。子どもたちが創造的な実践や文化的資源に触れる機会を設計しています。これらの活動は単発的なものではなく、教育者としての理念に根ざした「アクセスのデザイン」として一貫性を持っています。
“One of the things that is just a thread for me as an educator is I like to create systems. I like to create accessibility to things… through a kind of infrastructure.”
(教育者として私が一貫して大切にしているのは、制度をつくることです。人々がさまざまなものにアクセスできるよう、インフラを通じてその道筋を整えることが好きなんです)
こうした仕組みづくりの思想は、現在進行中の映画制作やアーカイブ活動にも通じており、地域に開かれた形での保存・継承の方法を模索しています。
🌱 教育観と今後の展望
“Start personal, and then work your way out.”
(まずは個人的なことから始めて、それを外に広げていけばいいんです)
Hillさんは、ソーシャル・プラクティスも人文学の研究も、「問い」を出発点とする点で共通しており、学生には「自分にとって大切なこと」から創造的な取り組みを始めるよう伝えています。
“You don’t need to go far outside of yourself.”
(自分の外側へ無理に出て行かなくていいのです)
このような姿勢は、文化交流や個人的経験から着想されたプロジェクトにも正当性を与え、学生の関心を深める土壌となっています。
“I want to be in a position where I can provide access and structure, but still be creative.”
(アクセスと構造を提供しながらも、創造性を保てるような立場にいたいと思っています)

📝 まとめ
Kiara Hillさんのお話からは、創造的な実践がいかに「関係性を築くこと」「語ること」「共有の場を設計すること」と深く結びついているかが浮かび上がります。教育、研究、キュレーション、地域とのコラボレーションなど複数の領域を往還しながら、「誰もが文化的資源にアクセスできる社会」を構想するその姿勢は、ソーシャル・プラクティスの枠を越えて、実践的な知のあり方を提示しているように思われました。
また、Hillさんにとってストーリーテリングは、学術研究と創造的な実践をつなぐ重要な軸であり、特に学術界の外にいる人々にも届く表現手段として重視されています。
今後も、Hillさんの活動がアーカイブとして蓄積され、より多くの人々との接点を生み出していくことが期待されます。
リターンを選ぶ
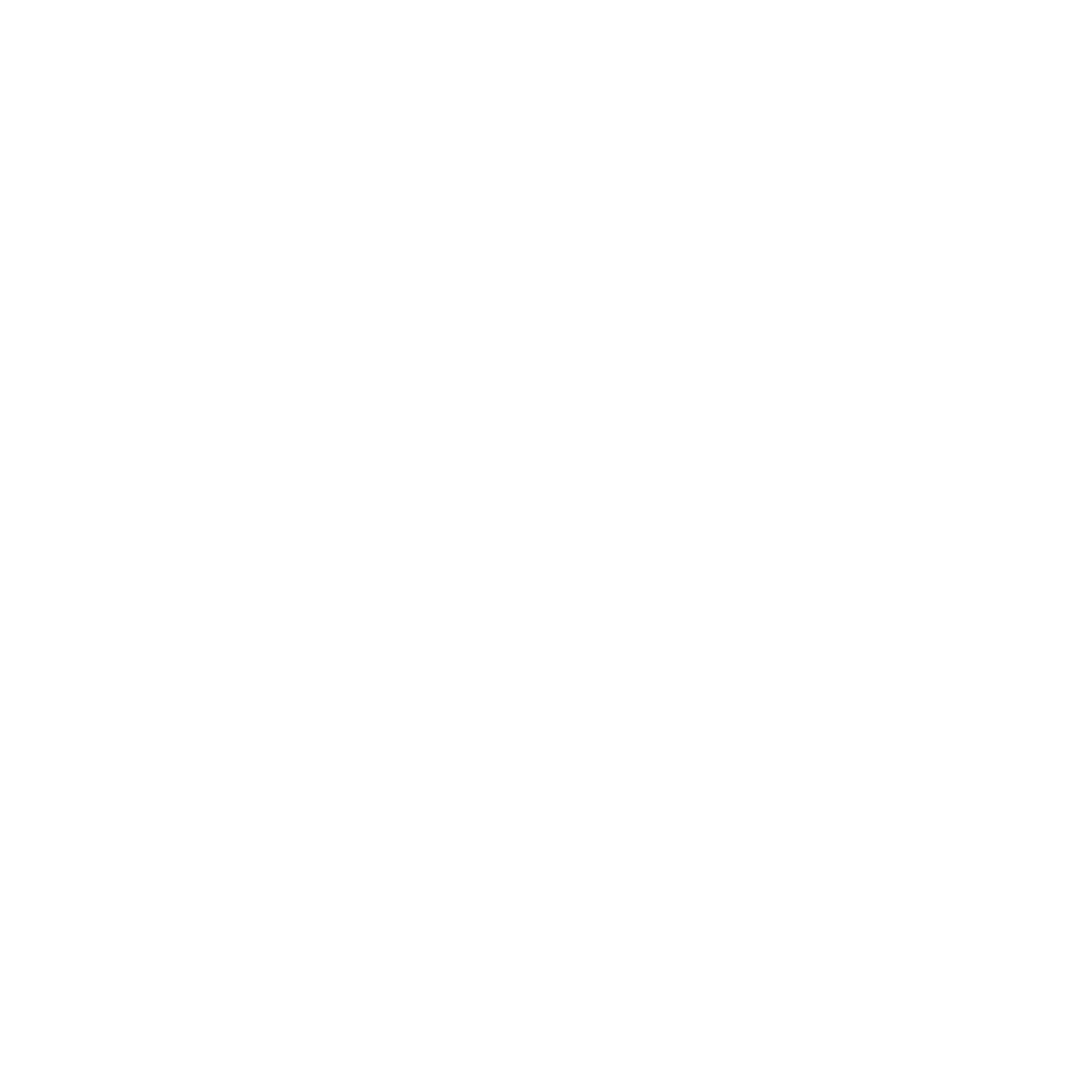
 画像処理中です...
画像処理中です...