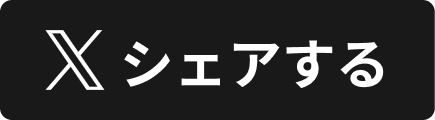長生炭鉱遺骨収容へ!
沖のピーヤからの潜水調査に目標を定める!障害物をどけて入っていく!




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/7/17 08:20
残りあと今日を入れて5日です!

ついに600万円超えました!
この6日間で100万円、ネクストゴール700万円の超過達成を!
あと5日間です、締め切り7月21日です
安全確保のための措置に資金が必要です、皆様のご支援をお願いします!
今回水深が深いために700万円が安全対策費として別途必要になりました。これについては刻む会の蓄積してきたクラファン以外の募金や、韓国での市民カンパ、国内篤志家様からの寄付を充てる予定です。しかし、それ以外にも安全対策としてピーヤ内の木材撤去に40万円を追加で予算化しました。ご遺骨発発見後の長時間潜水に向けて、循環呼吸器リブリーザー(1台200万円以上)の購入などに対応しなければなりません。まずは今回のクラウドファンデング700万円+40万円(ピーヤ内の木材撤去費用)を達成させてください。
クラファンのご支援はこちらをクリック
https://for-good.net/project/1001960
🔳潜水調査方法の選定について(伊左治さんの公開した報告書より)
長生炭鉱において潜水調査を実施するにあたり、以下の3点が主なリスクとして想定されます。
- 視界不良(水中の濁り)
- 崩落の危険性
- 水深および遺骨推定地点までの長距離移動
以下に、それぞれのリスクに対する対応方針と考え方を示します。
1.視界不良(水中の濁り)
現時点では、視界の極めて悪い区間については、幸いにも既に通過済みで経路の確保を完了し、大きな支障には至っていません。これまでも透視度の低さは作業や調査の進行に影響を及ぼす要因ではありましたが、致命的な障害とはなっていません。一度通過した箇所には、ラインを設置することで進路を明示しており、仮にこの先で視界が悪い区間がまたあったとしても、複数回の潜水を重ねることで到達距離を延ばすは可能であると考えています。
また、透視度の低い環境や、容易に視界が悪化する環境における潜水については、私自身がこれまでに多数の経験を有しており、対応可能であると考えています。
2.崩落の危険性
崩落のリスクは、以下の3つの地点に分けて考えることができます。
① 坑道入口部の崩落
今後の潜水開始地点として想定されている場所ではないものの、坑道入口は空気中に露出、あるいは空気に近い位置にあり、また、坑道の水位の変化によって濡れた状態と乾燥した状態を繰り返す環境にあるため劣化が進みやすく、ある程度の期間で崩壊すると予想されます。
一度崩落が発生すると、再度開口するための工事をするのは困難であるため、歴史的な遺物としてのとらえ方などを踏まえると、保存措置を講じることには一定の意義があると考えられます。
② 坑道内部の通路の崩落
坑道内部で呼吸により発生する排気の泡は、短期的にはその刺激による崩落を誘発するおそれがあり、また中長期的には泡が坑道内の天井部に滞留することで支持構造の安定性を損ねる可能性があること、泡に含まれる酸素が構造材(特に木材)を劣化させる可能性があります。
このため、当調査ではリブリーザー(呼吸ガスを循環再利用し、水中に排気を出さない潜水器材)を使用しています。リブリーザーでも水深変化に伴って少量の排気泡は発生しますが、通常の潜水方式に比べて影響を大幅に軽減することができます。
ただし、崩落のリスク自体はリブリーザーを使用しても完全に排除することはできません。
また、調査期間が延びると坑道内に泡が長期間蓄積され、リスクが累積していく懸念もあるため、調査期間は集中させ、短期間で成果を得ることが望ましいと考えています。
③ ピーヤ下部の構造物の崩落
ピーヤ下部には、鋼管や木材などの障害物が堆積しています。 宇部市のダイビング事業者による協力のもと、人力でピーヤ内の障害物の引き上げを実施しました。その結果、現在は「障害物の隙間を縫って坑道に進入可能な状態」まで改善していますが、引っかかったような形で支えられているだけの木材や金属パイプ類の隙間を潜降していくことになるため、浮上時に接触すると崩落を引き起こし、最悪の場合、浮上経路を塞ぐ可能性があります。
リスクを無くすため障害物をすべて撤去することが望ましいですが、完全に除去するには予算上の制約があり、当面は「ある程度の隙間を確保する」範囲での対応となる見込みです。この問題は、予算の確保により解決可能なため、今後継続的に潜水を行う段階までに解消を図るべき優先事項の一つと考えています。
3.水深および遺骨推定地点までの長距離移動
これまでの潜水調査により、坑道内の水深はおおむね42~44メートルであることが分かっています。遺骨が存在すると推定される地点までの正確な距離は不明ですが、事故当時の崩落地点までの距離は沖のピーヤから800メートルほどと考えられており、遺骨はその周辺、またはそれより遠い地点に遺骨があると想像されます(事故発生時、より手前で亡くなられた方もいると考えられます)。したがって、「まず遺骨の一片でも収容する」という段階であっても、水深42〜44メートルの環境下で最大800メートルの移動が必要となります。
このような40メートルを超える水深環境に対応するため、今回使用するガス(緊急時用の呼吸ガスおよびリブリーザーで希釈用に使用するガス)としては、酸素と窒素に加えヘリウムを混合した「トライミックス」を使用することとしました。
これは、水深が30メートルを超えると、呼吸ガス中に含まれる窒素(および酸素)は麻酔様作用を示すようになり、いわゆる「窒素酔い」によって認知機能や判断力の低下を引き起こすためです。特に閉所・暗所・高ストレス下ではこの作用が強くなる傾向があることが知られており、安全確保の観点から、ヘリウムを含むトライミックスの使用が不可欠と判断されました。
移動に必要な時間については、テクニカルダイビングにおける標準的な移動速度である毎分10〜12メートルを基準に、毎分10メートルの遊泳速度として見積もりました(この速度は、経路確保用のライン設置が完了していることを前提としています)。これに基づき、800メートルの片道移動に要する時間は約80分、往復では160分となるため、今回は安全を考慮し、片道75分・往復150分を上限とする運用としました。
使用するリブリーザーでは、同じ水深に滞在する限りは基本的に酸素のみが消費されますが、機材の故障時にはオープンサーキット方式(タンクから直接ガスを吸い、そのまま水中に排出する方式)への切り替え(ベイルアウト)が必要になります。
水深43メートルでは、オープンサーキットでのガス消費はタンク1本あたり15〜20分が目安であるため、緊急時に備え、150メートルごとに予備のタンクを1本ずつ設置することとしました。なお、分岐箇所では両方向に設置する必要があります。
これらのタンクは、トラブルが発生しなければ使用されないため、基本的に調査終了までは設置状態を維持する予定です。加えて、アルミニウムタンクの腐食防止のため、マグネシウム陽極棒を装着し、犠牲防食措置を施しています。
また本来は、緊急時だとしても排気の泡を出さないために、ベイルアウト用としても予備のリブリーザーを用意することが望ましい環境ですが、予算等の制約から今回の調査では実現していません。
大深度に長時間滞在した場合、体内に蓄積された不活性ガス(主に窒素)を安全に排出するため、減圧が必要となります。
水深43メートルに150分間滞在した場合、必要な減圧時間は約215分(3時間35分)と算出されており、これは、調査後にピーヤ内にて215分をかけて段階的に浮上する工程が必要となることを意味します。
減圧を適切に行わずに急浮上した場合、減圧症(通称:潜水病)を発症するおそれがあり、血管内で不活性ガスが気泡化して詰まり、重篤な障害を引き起こす可能性があります。
このため、リブリーザーが故障した緊急時であっても減圧工程を安全に完了するために必要な予備ガスをピーヤ内に十分に準備し、また減圧時間中に滞在可能なプラットフォームをピーヤ内部に設置することとしました。
これらの工程を含めた総潜水時間は約365分(=6時間5分)となり、これは私が使用しているリブリーザーに搭載可能な二酸化炭素吸収剤の使用上限にほぼ等しい時間です。
万が一、この潜水範囲内で遺骨が発見されない場合、またはより奥にある遺骨の回収を試みる場合には、リブリーザーを2機携行することで対応可能と考えられます。
※ 一部のダイバーから、「水深40メートル程度ではトライミックスは不要ではないか」「この水深には慣れているダイバーも多い」との意見が寄せられました。しかしながら、以下の理由によりトライミックスの使用を必須としています。高気圧作業安全衛生規則において、水深40メートル以深ではトライミックスの使用が推奨・指導されていること。
- 閉所・暗所・高ストレス環境ではガスの麻酔作用が強く現れることが知られていること。
- ガス麻酔作用(窒素酔い)は、慣れても症状が軽減されることはないという研究結果があること。
- ガス麻酔作用は自覚症状が乏しく、気付きにくいリスクであること。これらを踏まえ、今回の潜水調査では、高コストではあるものの、安全のためにヘリウムを含むトライミックスを使用することとしています。
リターンを選ぶ
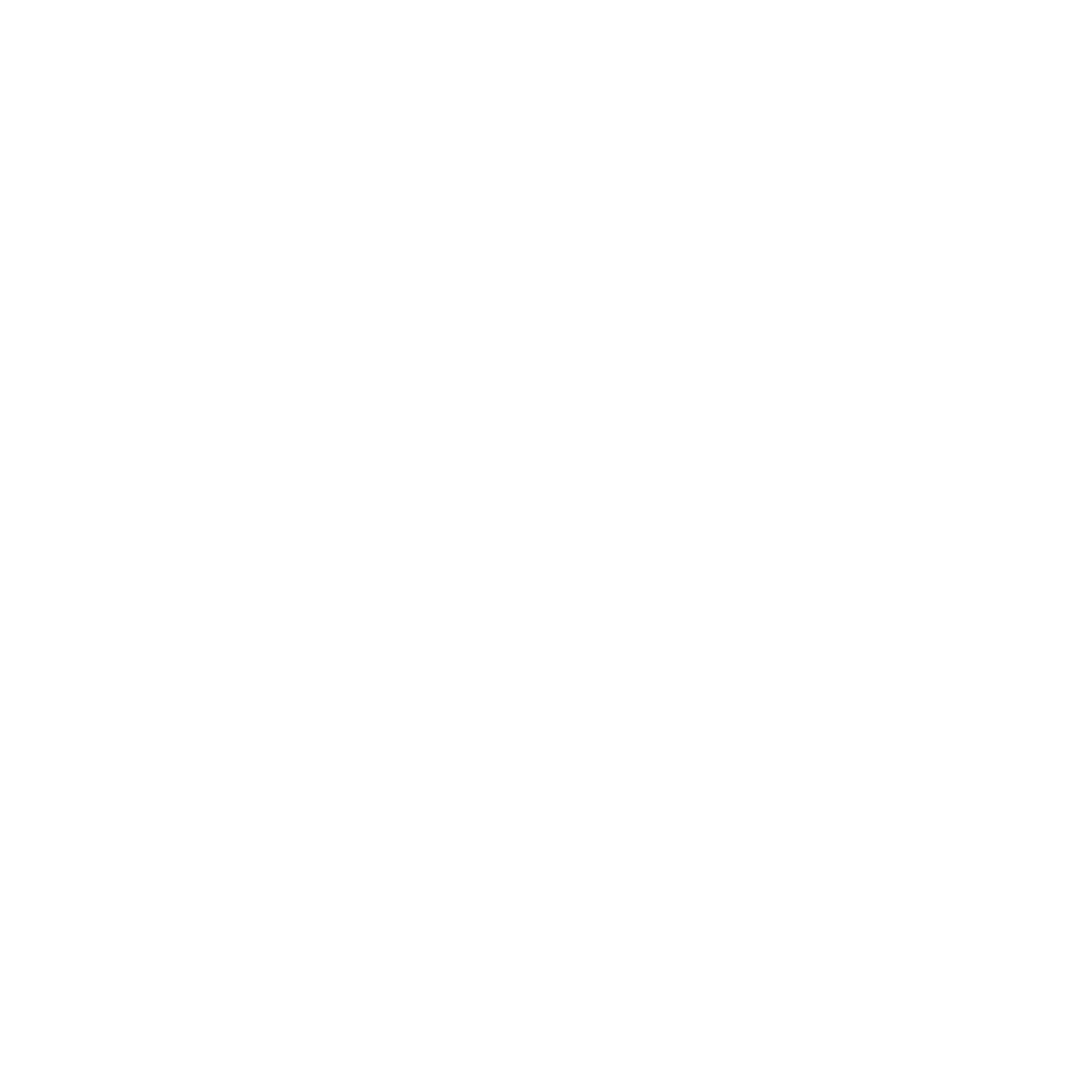
 画像処理中です...
画像処理中です...