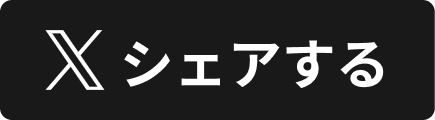伝統技術の継承
かまど炊き豆腐づくりの技術を次世代に継承したい




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/4/5 16:19
コラム:かまど炊き豆腐づくりが存続できる社会を次世代に継承したい

クラウドファンディングも1週間が過ぎました。毎日、色んな方に、色んな形で想いを寄せていただいており、本当にありがたく、感謝でいっぱいです。ありがとうございます。
ふっと湧き上がってきたことがあります。
今回のクラウドファンディングのテーマは、「かまど炊き豆腐づくりの技術を次世代に継承したい」としました。
これをもっと本質的に言い換えたら、「かまど炊き豆腐づくりが存続できる社会を次世代に継承したい」ということなのではいかと。
技術を繋いでいきたいという想いはもちろん強いです。それがなぜなのか、と突き詰めていくと、この技術の中に、これからの社会を創っていくためのエッセンスがあると僕が確信しているからだと思います。
それは、かまど炊き豆腐だけにあるのではなくて、他の手仕事の食べ物づくりや、もっと広く手仕事全般にも言えるかもしれないし、ものづくり以外の様々な分野の中に存在するだろうと思います。
なぜなら、そのエッセンスというのは、「自他のいのちと調和する感性」のようなものだと言えるからです。きっとそれが、物質的で拡大的で、ヒエラルキーに基づいて発展してきた社会から、次の社会に移行するのに必要な要素ではないかと思うのです。
だとすれば、僕が願っているものの本質は、かまど炊きの豆腐屋が存続していけるような社会ではないか、と思いました。
かまど炊きの豆腐屋が存続していける社会とはどんな社会でしょうか?
まず、大量生産でないことは確かなので、価格が高くても品質の良いものに価値を見出す人が一定程度いるでしょう。
食べ物が作られる過程や、作り手に対して関心を持ち、作り手を支えようとする人たちがいるように思えます。
一人一人が固定観念や常識にとらわれずに、やりたいことに挑戦できる社会かもしれません。
他にどんなことが思い浮かぶでしょうか?まだまだあると思います。
ぜひお一人お一人が、ご自身の視点から想像してみていただけたら嬉しいです。
経済合理性から言ったら最も分が悪いけれど、最もシンプルで、人の五感を頼りにして、自然に寄り添った作り方の豆腐屋が存続できる社会とは…?
もしそんな社会になったらいい、と思えるようでしたら、ぜひこのプロジェクトにご支援いただけたら幸いです。
これは僕の利益のために取り組むわけでもなく、豆腐業界のために取り組むわけでもなく、もっと広くこれからどんな社会を創っていきたいかというテーマなのだと思っています。
自分の命の時間は限られている。どんな未来を次世代に繋いでいきたいか、という問いでもあると思います。
リターンを選ぶ
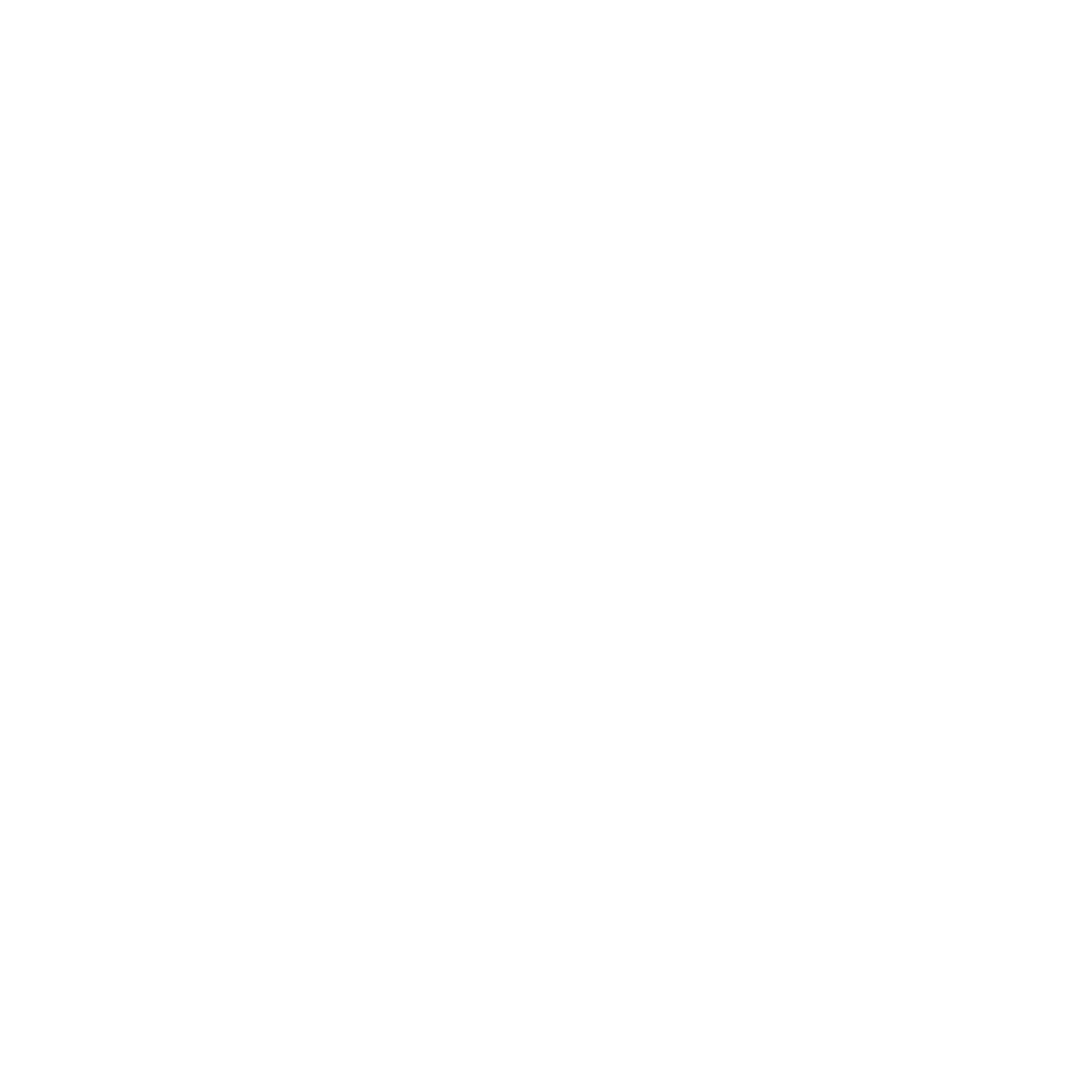
 画像処理中です...
画像処理中です...