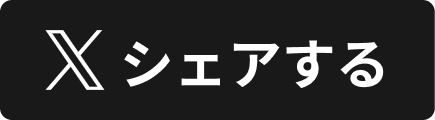伝統技術の継承
かまど炊き豆腐づくりの技術を次世代に継承したい




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/4/7 17:22
コラム:町に小さな豆腐屋があるという文化を守りたい

「町に小さな豆腐屋があるという文化を守りたい」
今回のクラウドファンディングは、「かまど炊き豆腐づくりの技術を次世代に継承したい」としました。
このテーマに定めるのにあたって、一つの心配がありました。それは、かまどで豆腐を作ることが他の作り方よりも優れていて、特にこれを守っていくべきだと誤解されやしないかということです。
ページの中に書きましたが、現代の豆腐屋さんでは、火を使って大豆を加熱せずに、ボイラーの蒸気を使うのが一般的です。僕は、これにくらべてかまどが優れているとは申し上げていません。
17年前に僕が豆腐屋を始めるとき、右も左も分からないまったくの素人でしたから、たくさんの豆腐屋さんを見学させていただきました。当然ながらそのほとんどが、蒸気で炊く豆腐屋さんです。皆さんご親切に何でも教えてくださり、どれほど助けられたか分かりません。また、どの豆腐屋さんもそれぞれの信念を持って取り組んでいらっしゃいました。
僕が学生時代に衝撃を受けるほどの感動を覚えた豆腐屋さんも、ボイラー炊きです。
そもそも、豆腐屋の仕事というのは、ほぼすべての豆腐屋さんが手仕事です。どれほど機械の性能が上がったとしても、人間の五感なしに良いものは作れません。
大豆は生き物で常に変化しています。それは、大豆が畑に蒔けば芽(根)を出す種だからだと考えています。その大豆の変化に寄り添って感じ取ることが、豆腐を作る上で最も大切なことであって、それは作り方や技術を越えていると思います。
豆腐屋の仕事は、朝早くからの水仕事で、体は冷え、長時間の重労働です。これだけ豆腐屋を続けることが困難な時代において、まだこの仕事を続けているというだけで大拍手ものだと僕は思っています。
豆腐はこの国の食生活には欠かせない食べ物であり、それを支えているのが多くの町の小さな豆腐屋さんです。
僕が創業した2008年当時、ここ長野県伊那市には僕を含めて8軒の豆腐屋さんがありました。現在は2軒まで減ってしまいました。特にコロナ以降に廃業が続いたように思います。皆さんの周りでも、馴染みの豆腐屋さんがやめてしまった事例があるのではないでしょうか。
かつては豆腐と言えば豆腐屋で買うのが当たり前であり、ボールを持っておつかいに行った経験を懐かしくお話になる方がたくさんいます。ラッパを吹いて売りに来るのも日常の光景だったのでしょう。それは、日常の人と人とのコミュニケーションでした。
町に豆腐屋があるというのは、僕はこの国の大切な文化の一つだと思っています。
このクラウドファンディングは、かまど炊きの豆腐屋だけを守っていくのが目的ではりません。町の豆腐屋を守っていきたいというのが僕の想いです。
そのために、従来の豆腐屋の枠組みに囚われずに、若い職人がこれを生業にしていける事業を育てていくことが、一つのモデルケースになるのではないかと考えています。
リターンを選ぶ
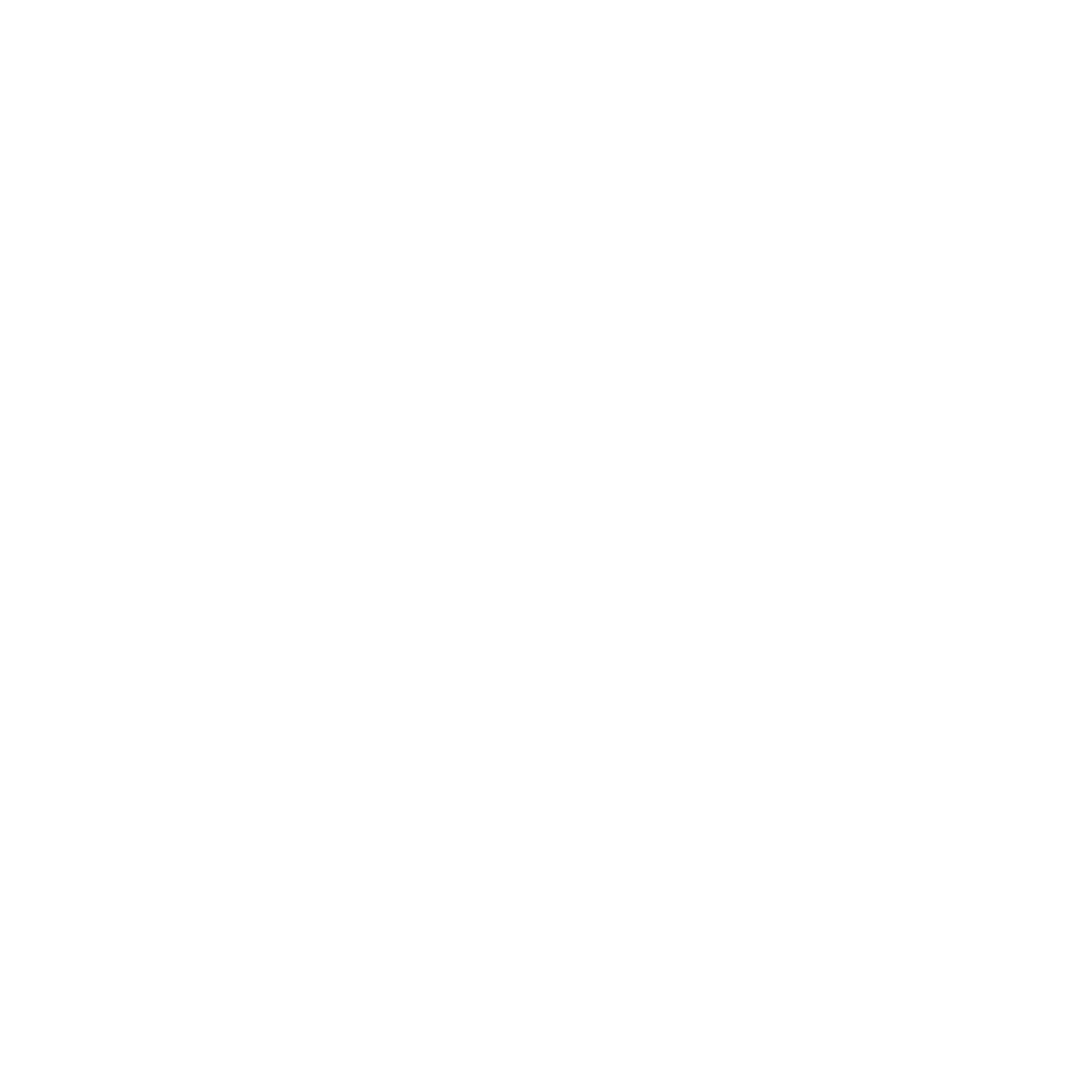
 画像処理中です...
画像処理中です...