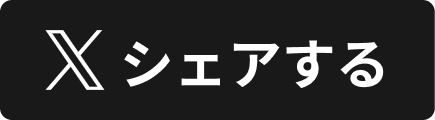伝統技術の継承
かまど炊き豆腐づくりの技術を次世代に継承したい




みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/3/31 18:17
コラム:他力で生きる

今朝、豆の仕込みのために工場に行くと、外の薪小屋に薪が高く積まれていた。先週の仕事で薪を使い切って空になっていたのに、休みの間に友人が届けてくれていたのだ。
高校の友人が、時々薪を割って届けてくれる。彼女は、たまたま丸太がたくさん手に入る状況にある。「使い切れないし、置き場にも困るから」というのが一応の理由のようだ。
しかし、経験のある人なら分かると思うが、丸太をチェーンソーで玉切りするだけでも大変なことだ。それを割るのも重労働。さらに、その重たい薪を車に積むのは大仕事だ。運ぶ距離も決して近いわけではない。平坦でない山道を行く。そして、薪小屋に積むのがまた一苦労なのだ。
彼女は二児の母だ。春休みで子供の面倒もみなければならない。それなのに「朝飯前」だとさらっと言ってのける人がどこの世界にいるのだろう。すべて無償なのだ。
どうしてこんなことが僕の身に起こるのか。それは、「他力」が働くからだと考えている。
僕がこの言葉を知ったのは、2013年のことだった。その頃、僕は豆腐屋を始めて5年が経っていて、とても忙しく働いていた。その2年前に工場を新設して、生産量も取引も大きく広げた。従業員さんも雇い入れた。
それでも、かまど炊きである。そもそもたくさん作れるはずがないのだ。にも関わらず、たくさん作ろうと不自然なことをしていた。結果として、毎日数時間だけの睡眠で、労働時間はとんでもなく膨れ上がっていた。その年の暮れに、大量のお歳暮セットを作り上げたところで、自分の心身がもう動けないと悲鳴を上げてくれた。
そんな時に、知人からある仕事の立ち上げをやらないかと声をかけてもらった。「他力塾」というオルタナティブスクールの仕事だった。ホースセラピー牧場を学校にして、牧場暮らしをしながら子供たちが学ぶのだ。むろん僕は馬に触れたこともなければ、教育に携わったこともない。わけも分からないまま、とりあえず取り組んでみた。
「馬や自然に頼って生きる」というのが、他力塾の中心にある思想だった。ファシリテーターとして子供たちと共に牧場暮らしをした2年の間、とうとう僕は「他力」とは何かが分からずじまいだった。
乗馬の境地は「人馬一体」という感覚らしい。そんなものは僕には到底分からなかった。子供たちは、例えば長い間引きこもりだった子や、自閉症の子がいたりした。みな純粋で繊細な少年たちだ。僕の言動は彼らを傷つけた。たくさんの反発がかえってきた。
僕は、自分が中心にいて、外の世界のものは、自分の力で動かせるものだと思っていたのだろう。他者は自分の思い通りにならないということを、きっと理解できていなかったのだと思う。
自然や動物も含めて、他者を信じ、尊重し、委ね、寄り添うという感覚が分かるようになったのは、ずっと後のことだ。それは、自分自身の中心にある願いに触れて、自分を受け入れられるようになってからのことだ。
他力の思想というのは、自分を大きないのちのめぐりの中にいる、小さな小さな粒だと感じ取る感覚に依るものだと思う。吹けば飛んでしまうようなちっぽけな粒だけれど、内に光源を持つ確かな粒だという自己承認ができた時、外側に向かって光を放つようになる。他力が発動するには、まずは自分の内側と繋がることが必要なのだと思う。
放たれた光は、めぐりめぐって何かしらの形で自分の元へ返ってくる。それが「他力」の働きだ。
他者や自然との分断が進み、欲望やエゴが膨らみやすい資本主義社会を生きてきた僕らは、自力に頼りすぎてきたのだと思う。もう一度、自分たち自身が自然な存在であることを思い出す時に来ているのかもしれない。それは、振り子をもう少し他力の方へ揺り戻す時とも言えるのだ。
リターンを選ぶ
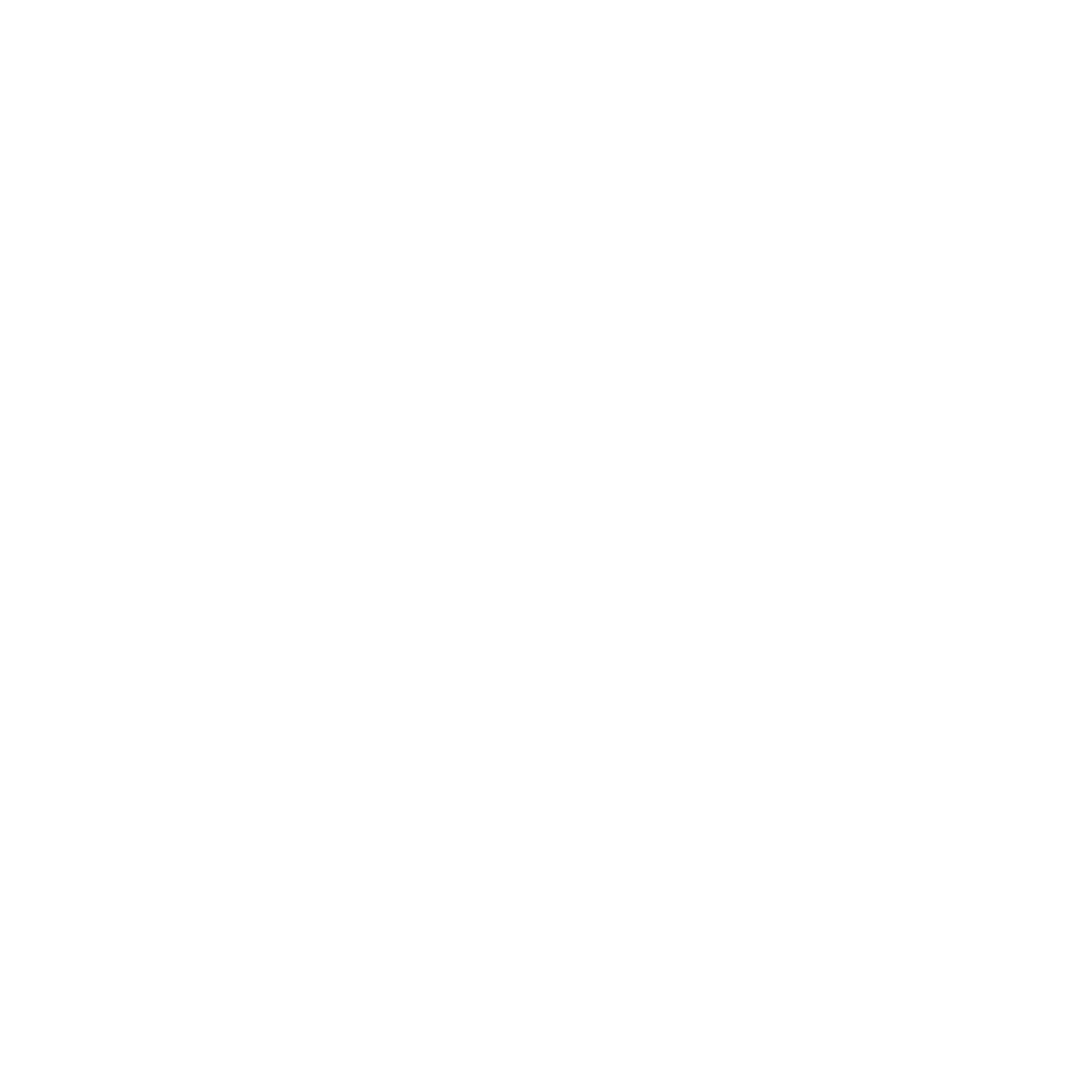
 画像処理中です...
画像処理中です...